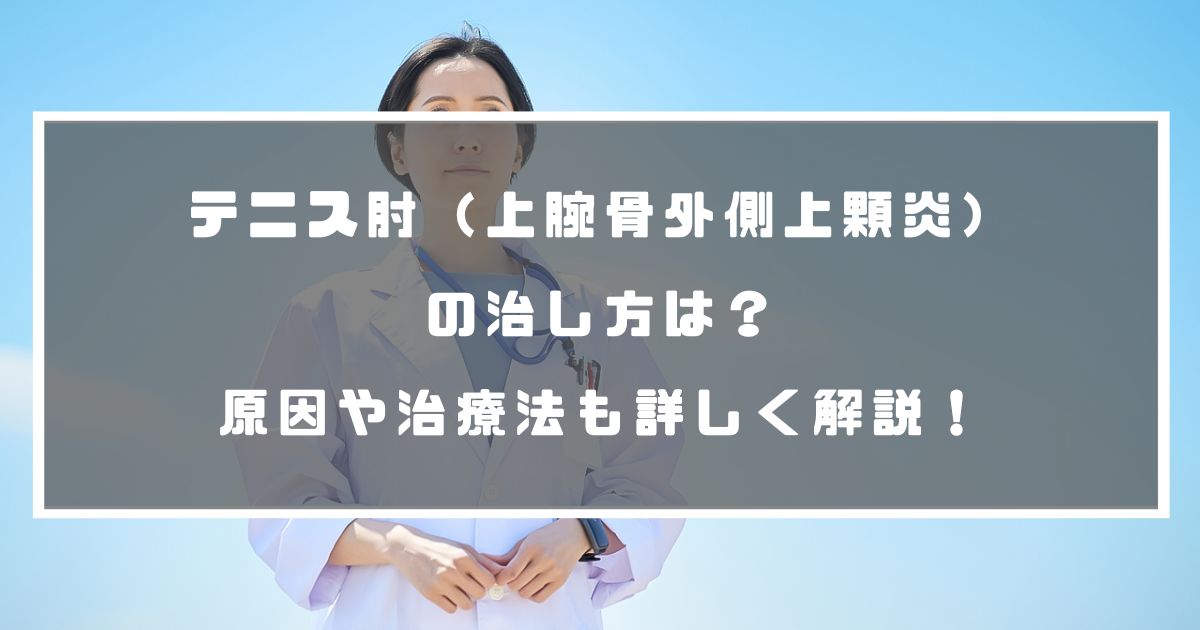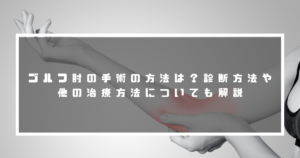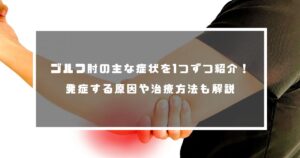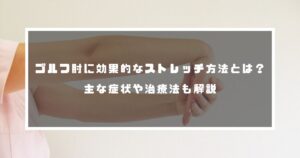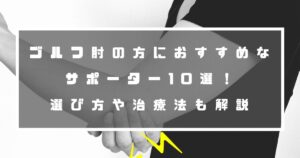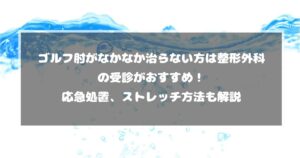肘に痛みを感じる場合、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を発症している可能性があります。
「スポーツをしないのにテニス肘になるなんて」と驚かれる方も多くいますが、肘は日常生活でよく使う部分であるため、どのような方でも発症するリスクがあります。
とくに家事や仕事などで、腕に負担をかけている方は注意が必要です。少しでも痛みを感じたら、専門医へ相談するようにしましょう。
今回の記事では、テニス肘の治し方について紹介します。テニス肘のメカニズムから予防方法まで、さらにはテニス肘の治療実績が豊富なシン・整形外科についても詳しく解説します。
まだ症状が軽い方も長引く痛みに悩まされている方も、ぜひ今回の記事を参考にして快適な日常生活を取り戻しましょう。
テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とは?

肘に痛みを感じても「スポーツはしないから、テニス肘の心配はない」と勘違いする方も少なくありません。
しかし、テニス肘はテニスやバドミントンなどのラケットを使用するスポーツの経験にかかわらず、誰でも発生する可能性がある疾患です。
まずは、テニス肘のメカニズムや主な症状について紹介します。自身の症状と照らし合わせて、症状が悪化する前に適切な処置がおこなえるようにしましょう。
テニス肘のメカニズム
テニス肘(外側上顆炎)は、肘の外側にある骨の出っ張り(外側上顆)に付着する前腕の伸筋群が繰り返し使われることで、筋肉や腱に微細な損傷や炎症が起こることで発症します。名前の通りテニスプレーヤーに多いことから「テニス肘」と呼ばれますが、実際にはテニス以外の日常動作や仕事でも発症することが多い障害です。
テニス肘のメカニズムは、ラケットのスイングやボールを打つ動作で手首を反らしたりひねったりする際、前腕の伸筋群(特に短橈側手根伸筋)が繰り返し収縮して肘の外側の腱付着部に過度なストレスがかかることが原因です。このストレスが蓄積すると腱に微小な断裂や変性が生じ、炎症や痛みを引き起こします。
また、テニス以外でもパソコンのキーボードやマウスの操作、重い物を持つ動作、ペットボトルのキャップを開ける動作など、手首を繰り返し反らすような動きが原因で起こることがあります。特に40代以降では腱の柔軟性や再生力が低下するため、些細な負担でも痛みが出やすくなります。
テニス肘の症状
テニス肘(外側上顆炎)の症状は、肘の外側から前腕にかけての痛みが中心です。初期の段階では、特定の動作をしたときに違和感や軽い痛みを感じる程度ですが、進行すると日常生活にも支障が出るほどの痛みに悪化することがあります。
痛みは肘の外側にある骨の出っ張り(外側上顆)周辺に集中して起こり、手首や指を伸ばす動作をしたときに強くなります。例えば、タオルを絞る、ドアノブを回す、カバンを持ち上げる、マグカップを持つといった動作で鋭い痛みを感じることが多いです。また、ペットボトルのキャップを開ける、料理で包丁を使うなど、手首や前腕の筋肉を酷使する動作でも痛みが誘発されます。
症状が悪化すると、安静時にもズキズキとした痛みを感じたり、物をしっかり持てなくなるほど握力が低下することもあります。肘から前腕にかけて重だるさや張り感が出る場合もあり、炎症が強いと夜間痛が生じて睡眠を妨げることもあります。
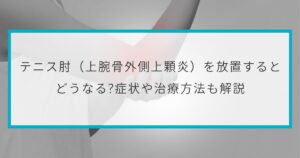
テニス肘の主な原因

テニス肘に悩まされている場合は、「肘の痛みを回避したい」「症状を悪化させたくない」と考える方が大半でしょう。
しかし、日常生活を送るうえで肘を使う動作は必要不可欠です。安静を続けて痛みを回避するよりも、原因を追究して適切な対処をおこないましょう。
ここからは、テニス肘の主な原因を紹介します。思い当たる項目がないか、確認してみてください。
スポーツで肘や手首を酷使している
テニスやバドミントン、卓球、ゴルフ、野球などのスポーツは、ラケットやクラブ、バットを振る動作が繰り返されるため、肘や手首の筋肉が常に負荷を受けます。特にテニスではバックハンドショットやトップスピンなど、手首を強く反らせたりひねったりする動作で外側上顆に大きなストレスが集中しやすくなります。ラケットの重さやガットのテンション、グリップサイズが合わない場合、前腕の筋肉が過剰に緊張し、腱の付着部に微細な損傷が繰り返されることで炎症が悪化します。また、フォームが崩れていたり、練習量が多すぎる場合もテニス肘を発症しやすくなるため、プレーの質と量のバランスを取ることが重要です。
仕事や家事で肘や手首を酷使している
テニスをしていない人でも、デスクワークや家事で手首を使う機会が多い人はテニス肘になることがあります。パソコンのマウスやキーボードを長時間使う動作、筆記作業、重い荷物を持ち運ぶ仕事などは、前腕の伸筋群を繰り返し使うため腱の負担が蓄積しやすくなります。料理でフライパンを振る、包丁を使う、タオルを強く絞るなどの家事動作も、手首を反らす動きを伴うためテニス肘の引き金となります。また、工具を扱う仕事や楽器の演奏など、細かい手首の動作を繰り返す職業では、特に外側上顆炎の発症率が高いことが知られています。
加齢や性別の影響
40代以降になると腱や筋肉の柔軟性が低下し、修復能力も落ちるため、軽い負担でも炎症が起きやすくなります。特に女性は家事や育児で手首や肘を酷使する機会が多く、ホルモンバランスの変化により腱や靭帯が弱くなることもあり、テニス肘を発症しやすい傾向があります。さらに、日常生活での小さなストレスが積み重なることで、気付かないうちに症状が悪化してしまうこともあります。年齢を重ねた人は特に、手首や肘を無理に使わない動作の工夫や、こまめなストレッチが予防のカギとなります。
テニス肘の診断・検査方法

テニス肘の疑いのため病院の受診を考えている方の中には、どのような検査をされるのか診断方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
一般的に、外来で簡単におこなえる診断や検査方法が用いられるため、心配は不要です。ここからは、テニス肘の診断でおこなわれる主な4つの検査方法を紹介します。
いずれの検査でも、肘の外側に痛みが生じた場合はテニス肘と診断されるでしょう。病院への受診を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
レントゲン検査
レントゲン検査は骨の異常や関節の状態を確認するために行われます。テニス肘自体は軟部組織(腱や筋肉)の炎症が主体であるため、レントゲンには直接的な異常は映らないことが多いです。しかし、骨の変形、骨棘(骨のとげ)、関節のすり減り、疲労骨折など、痛みの原因となり得る他の病気を見つけるためには有効な検査です。また、肘周辺の関節リウマチや変形性関節症など、骨や関節に関連する疾患を除外するためにも役立ちます。レントゲンで異常が確認されなかった場合は、必要に応じてMRIや超音波検査など、より詳細な画像検査が行われることもあります。
Thomsenテスト
Thomsenテストは、テニス肘の診断で非常に一般的な徒手検査の一つです。このテストでは、患者が肘を伸ばしたまま手首を上に反らせ(背屈)、検者が手の甲を押さえて下方向に力を加えます。その状態で患者が手首を上に押し返そうとした際に、肘の外側(外側上顆)に痛みが出る場合、テニス肘の可能性が高いと判断されます。このテストは伸筋群にピンポイントで負荷をかけるため、炎症が起きている部位がはっきりと確認しやすいという特徴があります。
Chairテスト
Chairテストは、日常生活の動作を模したシンプルな検査で、肘の外側に痛みが出るかを確認します。患者には手のひらを下に向けた状態(前腕回内位)で、2〜3kg程度の軽い椅子を持ち上げてもらいます。このとき、肘の外側や前腕に鋭い痛みが生じる場合は、外側上顆に負担が集中している証拠となり、テニス肘の可能性が示唆されます。特に、重いものを持つ、ドアを開けるといった日常動作で痛みが出やすい人に有効な検査法です。
中指伸縮テスト
中指伸展テストでは、患者が肘を伸ばしたまま中指をまっすぐ前に出し、検者がその中指を下方向に押し下げようとします。患者がその力に抵抗して中指を伸ばすときに肘の外側に痛みが現れる場合、短橈側手根伸筋を中心とした伸筋群に炎症が起きていると判断されます。この検査は筋肉を選択的に刺激するため、痛みの原因となっている筋や腱を特定するのに役立ちます。特に軽度〜中度のテニス肘でも痛みが再現されやすく、診断精度を高めることができます。
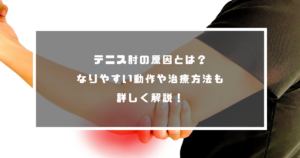
テニス肘の治療方法

テニス肘は症状が落ち着いても、痛みが再発するケースが多くあります。何度も再発する痛みに悩まされている場合「治療で痛みから解放されたい」「日常生活を早く取り戻したい」と願う方が大半でしょう。
では、テニス肘は完治させられる疾患なのでしょうか。ここからは、テニス肘の治療方法について解説します。治療してもすぐに再発するだろうと諦めてはいけません。
痛みの慢性化を防ぐためにも、早期の治療やケアを目指しましょう。
保存療法
テニス肘には保存療法が有効だといわれており、6か月~1年以内に治癒するケースが多くあります。痛みを緩和させるほか、痛みを慢性化させないためにも、症状が出るたびに保存療法をおこないましょう。
保存療法にはさまざまな種類があります。症状が軽い方は、腕のストレッチを取り入れて筋力を鍛えましょう。
症状が強い方は、スポーツや肘を使う動作を控えることがポイントです。湿布や外用薬を使用すると、痛みの緩和につながります。
ほかにも、ステロイド注射やテニス肘用のバンドを用いる場合もあります。自身で適切な保存療法を選択するのは難しいため、専門医へ相談してアドバイスを受けましょう。
再生医療
テニス肘の症状が慢性化している、保存療法では痛みが緩和されないなどの方におすすめの治療方法は、再生医療を取り入れた治療です。
テニス肘の根本的な治療が可能だと期待されているため、注目すべき治療方法です。患者本人の血液や細胞を使用し、ダメージを受けている部分の修復や再生をおこないます。
注射のみで治療をおこなえることから、手術の必要がありません。さらに、自身の血液や細胞を使用するため、副作用や合併症のリスクも少ないと考えられています。
手術療法
さまざまな治療法を試しても効果がない、完全に痛みが取りきれないなどの方は手術療法を検討する必要があるでしょう。
手術療法にも、いくつか方法があります。痛みが伴う部分の腱や滑膜ひだを切除し、残る腱を再び骨に縫合する「オープン手術」、内視鏡を使用する「関節鏡視下手術」の2つが主流です。
手術をおこなえば、腱の痛みがある部分を確実に切除できるため大半の方が痛みから解放されます。
しかし、手術にはデメリットもあるため注意が必要です。手術後にはリハビリ期間が必要となるほか、症状が再発しないとは限らない点がデメリットとして挙げられます。あくまでも手術は、最終手段として用いることが大切です。
テニス肘の予防方法

「テニス肘にはなりたくないが、趣味であるスポーツも諦めたくない」「肘に負担がかかりがちだが、仕事を辞めるわけにはいかない」などの方も多いのではないでしょうか。
心の健康のためにも、スポーツで汗を流す機会は失いたくないものです。日頃から実践できるテニス肘の予防方法があれば、テニス肘のリスクも少なくなるでしょう。
ここからは、すぐに取り入れられるテニス肘の予防方法を紹介します。テニス肘に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
肘や手首のストレッチ
ストレッチはテニス肘の発症を予防するほか、痛みを緩和する効果も期待できます。自宅で簡単におこなえるため、こまめにストレッチをして肘にかかる負担を軽減させましょう。
右腕にテニス肘の症状がある場合のストレッチを紹介します。まずは、肘を伸ばした状態で右腕を前に出します。
左手で右手を持ち、右手首の関節を手のひら側に曲げましょう。手首を曲げたまま指も曲げ、30秒間保ちます。右肘の外側が伸びている感覚が重要です。毎日3回おこなうと効果的でしょう。
テニス肘は、一度発症すると完治しにくいといわれています。痛みが軽減した場合でも、再び肘に負担をかけると再発する可能性があります。ストレッチを日常的におこない、痛みの発症を予防しましょう。
肘や手首の筋力トレーニング
幹部周辺の筋肉が日頃の負担に負けないようにするためにも、肘と手首を動かす筋肉を鍛えましょう。右腕にテニス肘の症状がある場合の筋力トレーニングを紹介します。
手のひらを下にした状態で右肘を伸ばし、ペットボトルのような重りを持ちます。手首を上に反らし、重りを持ち上げましょう。
ゆっくりと5秒かけて手首を戻します。10回を1セットとして、1日に3セットおこなうと効果的です。筋力トレーニングは、痛みの症状があるときは避けるようにしてください。
痛みがあるときは、無理のない程度にストレッチをおこなう、痛みがなくなれば筋力トレーニングに切り替えるなどの工夫が大切です。
運動後に患部をアイシングする
テニスやバトミントン、ゴルフなどのスポーツ後に痛みを感じる場合は、筋肉が炎症を起こしている可能性が高いといえます。
運動後の痛みには、患部の炎症を鎮めるためのアイシングが有効です。患部のアイシングは、15分程度おこないましょう。冷やし過ぎは逆効果になるため注意が必要です。
肘に熱を感じる場合は炎症が強いことから、温める行為は禁物です。シャワーや入浴などは、アイシング後にしましょう。
サポーターやテーピングの使用
テニス肘の症状がある場合は、肘の負担を軽減させるためにサポーターやテーピングの使用がおすすめです。
サポーターは日常生活に取り入れられるような薄手の物から、テニス肘専用やスポーツ用など種類が豊富に展開されています。
そのため、肘に痛みを感じるときはいつなのか、サポーターの使用場面により購入するタイプを考えましょう。次にテーピングの巻き方を紹介します。
ますは肘を曲げた状態で、親指の付け根から肘の外側まで引っ張りながら貼ります。そして、手首の関節に圧迫を加えながら一周貼ります。
最後、腕の一番太い部分に内側から外側に向けて圧迫しながら貼りましょう。最後に巻くテーピングは、肘関節にかからないように注意してください。
テーピングはドラッグストアやネットで簡単に購入可能です。色や厚みに種類があるため、自身に適したものを購入してください。サポーターやテーピング選びに悩んだ際は、主治医への相談がおすすめです。
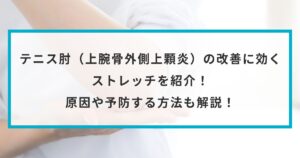
手術をせずにテニス肘の痛みを治療するならシン・整形外科がおすすめ!

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
テニス肘の治療方法や病院選びに悩みを抱えていませんか。長い通院や入院を必要とする治療法は、日常生活に支障をきたすため躊躇する方が多いのではないでしょうか。
再発を避けるために、リハビリにも力を入れている病院がおすすめです。シン・整形外科であれば最先端の再生医療を受けられるほか、患者それぞれに適したリハビリもおこなえます。
ここからは、シン・整形外科の特徴を紹介します。病院選びに悩んで切る方は、ぜひ参考にしてください。
切らずに痛みを取り除く再生医療が充実している
長引くテニス肘の痛みに悩んでいる場合でも、手術やメスを使う治療には踏み切れずにいる方が多くいます。
シン・整形外科がおこなう再生医療は、手術をおこなわずに注射のみを用いるため、日帰りでの治療が可能です。再生医療は短期間で治療がおこなえるほか、リスクの少なさからも注目されています。
患者自身の血液や細胞を使用するため、合併症のリスクが低い治療法です。大切な日常生活を守りながら、痛みからの解放を目指しましょう。
整形外科の専門医による診察が受けられる
シン・整形外科では、日本整形外科学会認定の専門医が診察をおこないます。豊富な知識や十分な実績により、適切な治療を提案するため安心して診察を受けられます。
聞き慣れない「再生医療」に不安を抱く方も少なくありません。まずは無料電話相談を活用し、不安を取り除きましょう。その後、専門医が丁寧にカウンセリングをおこない、患者それぞれにあう治療を提供します。
患者にあわせたオーダーメイドのリハビリで再発を予防できる
再発の不安があるテニス肘の場合は、リハビリが必要不可欠です。リハビリはマニュアル通りにおこなえばよいのではなく、患者それぞれに合わせたリハビリ方法を取り入れる必要があります。
シン・整形外科では、再生医療の効果を最大化させるほか、再発しにくい体づくりのためのリハビリを提供しています。
患者一人一人に合わせたオーダーメイドメニューを提案しているため、安心して取り組めるでしょう。
シン・整形外科はリハビリのほか、自宅でも簡単に取り入れられる運動についてのアドバイスも実施しています。痛みの根本を取り除き、快適な日常生活を取り戻しましょう。
まとめ
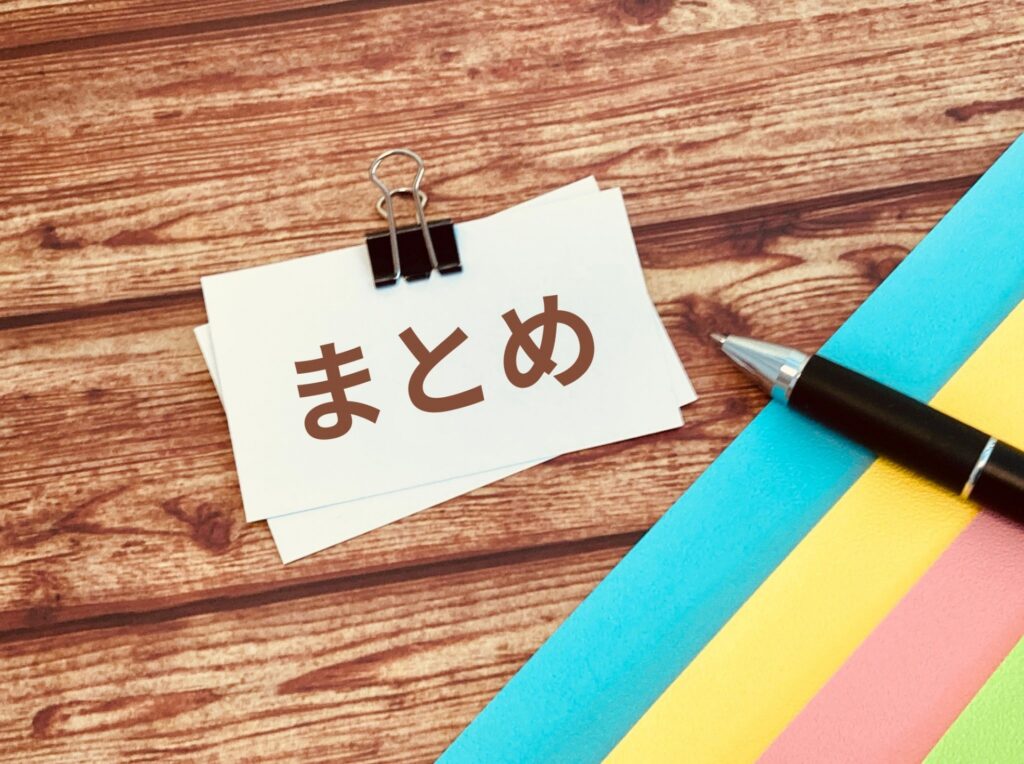
テニス肘は、スポーツ以外に日常生活の仕事や家事が原因で発症する疾患です。ストレッチや筋力トレーニングにより多少痛みを軽減させられますが、症状が進行すると痛みが慢性化する可能性があります。
根本的な治療をおこなわなければ、強い痛みに悩まされることになるでしょう。シン・整形外科では、痛みを除去するべく患者一人一人に最適な治療を提供しています。
メスを使用しない再生医療を取り入れれば、入院や痛みが伴う治療の心配からも解放されるため、日常生活のほか大切な趣味も継続できます。
長引く痛みに悩まされている方は、シン・整形外科に相談して根本的な解決を目指しましょう。