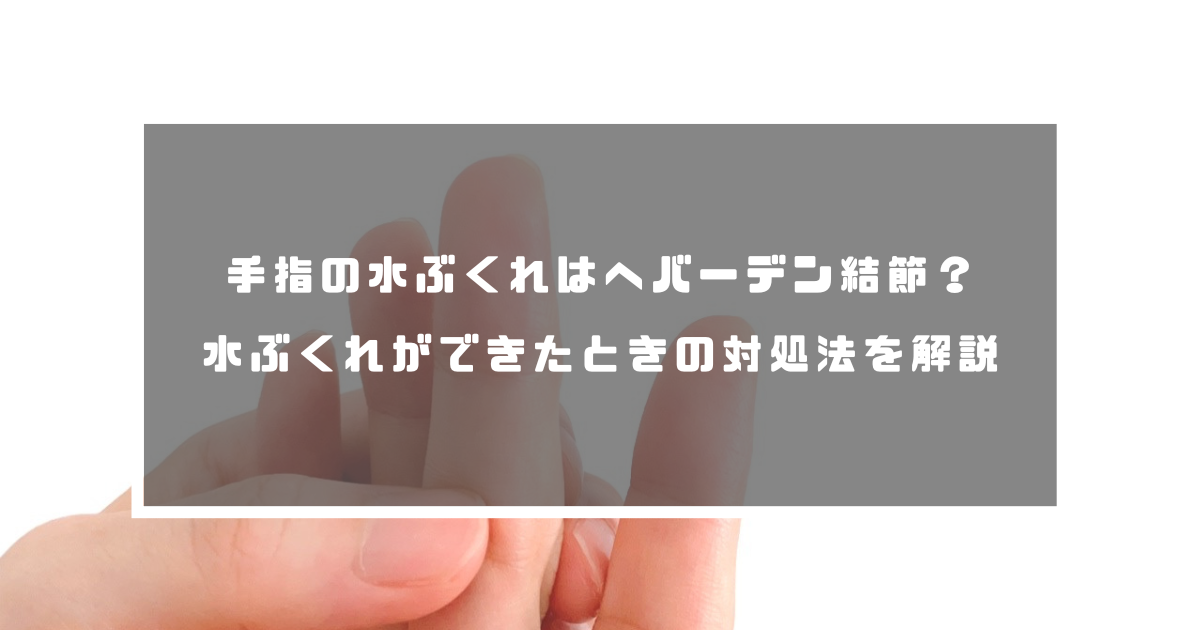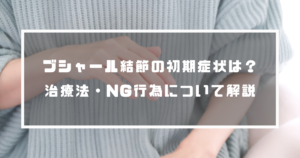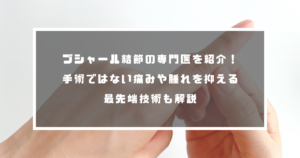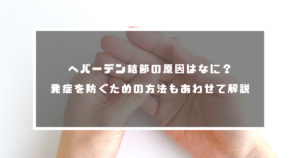指の先の関節が痛む、変形する、水ぶくれのようなでっぱりができるという場合には、へバーデン結節かもしれません。
本記事ではへバーデン結節や、病気の経過でできる水ぶくれについて解説します。
ぜひ参考にして、へバーデン結節の症状や対処法、治療法について理解し、根治に導きましょう。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない指へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
へバーデン結節の水ぶくれは潰すと危険?

へバーデン結節とは、指の第一関節、つまり指先の曲がる関節のうち、一番先端の関節が変形し、曲がる病気です。
指の変形性関節症に位置付けられ、同様の疾患にブシャール結節があります。ブシャール結節は、指の第二関節におこります。
腫れて痛みがでたり、動きが悪くなり強く手を握れなくなったりして日常生活を妨げる厄介な病気です。
進行すると第2関節も影響を受け、反ったり(過伸展)、小指側に指全体がだんだん寄ったり(尺側偏位)する場合もあります。
複数の指に生じることが多いのも特徴で、原因は明確に解明されていません。
なかには、へバーデン結節の患者の指に、水ぶくれができる場合があります。本章では水ぶくれの正体と対処法を解説します。
手指の第一関節の水ぶくれは粘液嚢腫(ミューカスシスト)
手指の第一関節にできる水ぶくれのような膨らみは、粘液嚢腫(ミューカスシスト)と呼ばれる良性の腫瘤である可能性があります。特に、へバーデン結節に伴って発生することが多く、中高年の方に比較的よく見られます。関節の変形や関節内の圧力が高まることで、関節液やゼリー状の物質が皮膚の下に漏れ出し、小さな袋状にたまってふくらみとして現れるのが特徴です。
見た目は小さな水ぶくれに似ており、押すとぷよぷよした感触があります。ときには破れて液体が出たり、皮膚が薄くなって破けやすくなったりすることもあります。しかし、このような膨らみを自分で潰すのは非常に危険です。無理に潰すことで傷口ができ、そこから細菌が入り込むと感染を引き起こすおそれがあります。感染が進むと、膿がたまったり、炎症が皮下組織や骨にまで広がる可能性もあり、重症化することもあります。
また、粘液嚢腫は潰したところで原因が解消されたわけではないため、何度でも再発することがあります。根本的な治療を行わなければ、腫れや痛みを繰り返す結果となってしまいます。さらに、皮膚が薄くなっている部分は自然に破れてしまうこともあり、その場合も感染のリスクが高まります。
もし粘液嚢腫が気になる場合や痛み、違和感を伴っている場合は、自分で処置をせず、整形外科や手の外科の専門医を受診することが大切です。医療機関では、状態に応じて穿刺による液体の除去、ステロイドの注入、場合によっては手術による摘出などが検討されます。併せて、原因となっているへバーデン結節に対しても治療を行うことで、再発の予防につながります。
へバーデン結節の水ぶくれを潰してはいけない理由
へバーデン結節の症状のひとつとして、指の第一関節(DIP関節)に水ぶくれのような膨らみができることがあります。これは「粘液嚢腫」と呼ばれるもので、関節の変形に伴って関節液が皮膚の下にたまることで生じます。見た目は小さな水ぶくれや腫れのように見えるため、気になって自分で潰そうとする人もいますが、これは非常に危険な行為です。
粘液嚢腫を潰してはいけない最大の理由は、感染のリスクがあることです。自分で針や爪などを使って潰すと、そこから細菌が侵入し、炎症や化膿を引き起こすおそれがあります。皮膚の薄い部分にできることが多いため、一度感染が起こると炎症が広がりやすく、重症化すると骨や関節にまで影響が及ぶこともあります。
さらに、潰したからといって嚢腫が完全になくなるわけではなく、根本的な原因が解決されていないため再発する可能性が非常に高いです。一時的にしぼんでも、時間が経てば再び同じ場所に膨らみが現れることがよくあります。
水ぶくれができたらすぐにクリニックを受診する
へバーデン結節に伴って指の第一関節に水ぶくれのようなふくらみができた場合、それは粘液嚢腫である可能性があります。見た目は小さな水ぶくれに見えますが、これは関節の変形により関節液が皮膚の下にたまってできるもので、放っておいたり、自己処置をしたりすることは危険です。
とくに、自分で潰すことは絶対に避けるべきです。皮膚が薄くなっている部分に針を刺したり、押しつぶしたりすると、そこから細菌が入り込み、感染や炎症を引き起こすリスクがあります。症状が悪化すると、膿がたまったり、皮膚がただれたりすることもあり、場合によっては手術が必要になることもあります。また、潰しても原因が取り除かれたわけではないため、再発を繰り返すことが多いのも特徴です。
このような水ぶくれを見つけた場合は、できるだけ早く整形外科や皮膚科などのクリニックを受診することが大切です。医師による適切な診断のもとで、必要に応じた処置(液体の除去や切除、感染予防のための抗生剤の使用など)が行われます。へバーデン結節そのものに対する治療方針も含めて、専門的に対応してもらうことで、症状の悪化や再発を防ぐことができます。
へバーデン結節の水ぶくれを放置するとどうなる?

水ぶくれの対処を知らずにそのままにしたり、知っていても病院を受診する時間がとれなかったりする方もいるでしょう。本章では、水ぶくれを放置した場合どのような危険性があるか解説します。
破裂して感染症を引き起こす場合がある
まず、水ぶくれ部分の皮膚は薄くなっていることが多く、自然に破裂してしまうことがあります。破裂すると、関節液やゼリー状の内容物が外に漏れ出し、傷口から細菌が入りやすくなります。
その結果、感染症を引き起こすリスクが高まります。感染が起こると、腫れや赤み、痛みが強くなり、膿がたまることもあります。さらに炎症が進むと、皮膚だけでなく、関節や骨にまで炎症が広がり、重症化する場合もあります。このような状態になると、治療に時間がかかるだけでなく、場合によっては手術が必要になることもあります。
また、粘液嚢腫は根本的な原因である関節の変形や関節液の漏れが改善されていないため、放置すると繰り返し再発しやすいのも特徴です。
関節が変形する可能性がある
へバーデン結節にともなって指の第一関節にできる粘液嚢腫を放置すると、いくつかの問題が生じる可能性があります。まず、この水ぶくれは関節内部の変化により関節液が皮膚の下にたまってできるものであり、見た目以上に関節の変形が進行しているサインであることがあります。放置を続けることで、指の関節はさらに変形し、指が曲がったり太くなったりする変化が目立つようになる可能性があります。
また、水ぶくれが自然に破裂してしまうと、その傷口から細菌が入り込み、感染を引き起こすおそれもあります。感染が進むと腫れや熱感、強い痛みをともない、場合によっては膿がたまったり、関節や骨にまで炎症が広がってしまうこともあります。こうした状態になると、治療が難しくなり、手術が必要になることもあります。
さらに、粘液嚢腫は潰したり放置したりしても根本的な原因が解決されるわけではなく、何度も繰り返すことが多いです。膨らんでは破れ、またふくらむというサイクルを繰り返すうちに、皮膚が弱くなり、関節の機能も低下していきます。
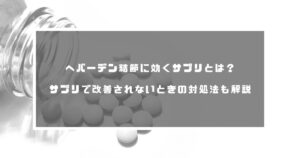
へバーデン結節の水ぶくれはすぐに治療が必要!クリニックで施される治療

へバーデン結節の水ぶくれができた方は、感染や関節の変形を防ぐためクリニックの受診が必要です。
本章では、具体的にクリニックでおこなわれる治療を解説します。
潰して適切な処置を施す
へバーデン結節にともなってできる粘液嚢腫は、見た目は小さくても放置せず、できるだけ早く医療機関で治療を受けることが大切です。破裂して感染を起こすリスクがあるほか、関節の変形が進行しているサインであることもあります。
クリニックでは、状態に応じた適切な処置が行われます。まず、針を使って水ぶくれを穿刺し、中にたまったゼリー状の液体を抜く治療が行われることがあります。この際、必要に応じて炎症を抑える薬剤を注入することもあります。ただし、こうした処置だけでは再発することが多く、何度も繰り返す場合には、粘液嚢腫そのものを切除する手術が検討されます。手術といっても局所麻酔で行える比較的簡単なもので、日帰りで済むケースもあります。
また、水ぶくれの背景にはへバーデン結節による関節の変形があるため、根本的な治療として、指の関節への負担を減らすリハビリや装具の使用などもあわせて行われることがあります。
固定すると治る場合がある
粘液嚢腫は、指の第一関節の変形により関節液が皮膚の下にたまってできるものです。見た目が小さくても、自然に破裂して感染を起こしたり、関節の変形が進行したりするおそれがあるため、早めの治療が必要です。
医療機関では、症状の程度に応じた処置が行われます。一般的には、膨らみの中のゼリー状の液体を専用の針で抜く穿刺処置が行われ、必要に応じて炎症を抑える薬を注入することもあります。この方法は比較的簡単ですが、再発することも多いため、繰り返す場合には粘液嚢腫を切除する手術が検討されることもあります。局所麻酔で行われ、日帰りで済むこともあります。
また、状態によっては関節の動きを制限することで腫れが落ち着く場合もあり、固定による保存的な治療が選ばれることもあります。特に、関節への負担が大きい動作を控え、テーピングや装具などで関節を安静に保つことで、水ぶくれの再発や悪化を防ぐ効果が期待できます。
自己判断で潰してしまうと感染や炎症のリスクが高まり、治療が長引く原因にもなります。見た目が小さな膨らみであっても、違和感を感じたら早めに整形外科や手の専門医を受診し、適切な治療を受けることが大切です。早期の対応が、関節の変形や症状の悪化を防ぐための大きな鍵となります。
根本的な治療は骨を削る手術
クリニックでは、まず穿刺と呼ばれる処置が行われることがあります。専用の針で粘液嚢腫にたまったゼリー状の液体を抜き、必要に応じて炎症を抑える薬を注入する方法です。この処置で一時的に腫れは引きますが、原因となっている関節の変形はそのままのため、嚢腫が再発することが少なくありません。
水ぶくれを繰り返す場合や痛みが強い場合、または見た目が気になる場合などには、外科的な治療が検討されます。根本的な治療方法としては、関節に生じた余分な骨(骨棘)を削ったり、変形した骨の一部を切除したりする手術があります。必要に応じて、粘液嚢腫そのものを切除する処置が同時に行われることもあります。これにより、圧力の原因を取り除き、再発を防ぐことができます。
また、状態によってはテーピングや装具などで関節を固定し、安静にすることで症状が改善する場合もあります。保存的な方法で経過を見ながら対応するケースもありますが、根本的な解決を目指す場合には手術が必要になることもあります。
へバーデン結節の根本的な治療におすすめの治療法

本章では、へバーデン結節自体を治療する方法を解説します。
症状の進行により適応となる治療が異なります。ぜひ参考にしてください。
初期症状なら薬物療法
初期症状の段階であれば、まず薬物療法が有効です。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や痛み止めを使用することで、関節の炎症や痛みを抑えることができます。湿布や外用薬も併用されることがあり、日常生活に支障があるほどでなければ、これらの保存的な治療で様子を見ることが多いです。また、関節に負担をかけないような生活指導や、必要に応じて装具やテーピングで指を保護することも効果的です。
一方で、関節の変形が進んでいる場合や、粘液嚢腫の再発を繰り返すようなケースでは、より根本的な治療が求められます。このような場合には、外科的な手術が選択肢となります。手術では、変形した関節の骨棘(とげのような骨)を削ったり、関節の一部を切除したりすることで痛みや腫れを軽減し、再発を防ぐことを目的とします。また、粘液嚢腫がある場合には同時に切除することもあります。
治療法の選択には、症状の程度や生活への影響、年齢や職業なども考慮されるため、医師との相談のうえで自分に合った方法を選ぶことが大切です。
中・後期症状には手術療法
へバーデン結節の根本的な治療法は、症状の進行度によって異なります。初期であれば保存的な治療が中心となりますが、中期から後期にかけては変形や痛みが強くなり、日常生活に支障をきたすようになるため、手術療法が検討されます。
初期段階では、薬物療法が基本となります。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や湿布薬などを使い、痛みや炎症を抑えます。あわせて、関節に負担をかけないようにする生活指導や、指の安静を保つためのテーピングや装具も取り入れられます。これらの方法で症状が落ち着く場合も多く、比較的軽い状態であれば手術は必要ありません。
しかし、中期から後期になると、関節の変形が進行し、痛みが慢性化したり、指の動きが制限されたりするようになります。このような場合には、保存療法では根本的な改善が難しくなり、手術が選択肢となります。代表的な手術には、変形した骨を削る骨棘切除術や、関節内の処置、さらには関節を固定して痛みを軽減する関節固定術などがあります。また、水ぶくれ(粘液嚢腫)を繰り返している場合には、それを切除する処置も同時に行われることがあります。
最先端技術の再生医療も視野に入れる
へバーデン結節の根本的な治療には、症状の進行度に応じてさまざまな方法があります。初期であれば薬物療法や生活指導、装具による保存療法が基本となりますが、進行した場合には手術療法、そして近年では再生医療といった新しい選択肢も視野に入ってきています。
初期症状で痛みや腫れが軽度な場合は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などを用いた薬物療法や、テーピング、装具による関節の安静保持が行われます。また、関節への負担を減らす生活指導も重要です。これらの方法で炎症を抑え、進行を遅らせることが期待されます。
中期から後期の段階では、関節の変形や痛みが強くなるため、保存療法では改善が難しくなり、手術療法が検討されます。手術には、変形した骨を削る骨棘切除術、粘液嚢腫の切除、さらに痛みの原因となる関節を固定する関節固定術などがあります。これにより痛みの軽減や見た目の改善が期待できます。
さらに、近年注目されているのが再生医療です。自分の血液や脂肪から採取した幹細胞や成長因子を利用し、関節の修復や軟骨の再生を促す治療が研究・実用化されつつあります。こうした再生医療は、手術に抵抗がある人や、できるだけ身体への負担を減らしたい人にとって、将来的に有望な選択肢となる可能性があります。ただし、再生医療はすべての医療機関で受けられるわけではなく、費用面や適応条件などもあるため、慎重な検討が必要です。
へバーデン結節は進行性の疾患であるため、症状が軽いうちに適切な治療を受けることが大切です。従来の治療に加え、再生医療のような新しい方法も含めて、自分に合った治療法を専門医と相談しながら選択していくことが望まれます。

へバーデン結節で手術したくない方はシン・整形外科への相談がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
へバーデン結節の患者は多く、痛みや動きの制限で日常生活に支障をきたす方も多数います。
しかし、急速に悪化したり生命にかかわる症状になったりする確率が低いため、専門病院にかからず放置している患者も多いのではないでしょうか。
先述のように、放置すると症状が進行したり変形が強くなったりして、保存治療で軽快しないことがあります。
手術はしたくないと抵抗感のある方や、機能低下など手術のリスクを懸念している方も多いでしょう。
手術をせず効果的な治療を受けたくない方におすすめな病院が、シン・整形外科です。シン・整形外科をおすすめする理由を解説します。
再生医療に特化したクリニック
シン・整形外科は手術なしの再生医療を専門とするクリニックです。
再生医療による痛みの治療に特化しているため、強力な鎮痛効果と長期的な作用が期待できます。
治療内容は先述のPRP療法のみでなく、幹細胞培養治療や、ヒアルロン酸注入やステロイド注射などその他の保存療法を患者にあわせて選択します。
整形外科の専門医が常駐
シン・整形外科では、整形外科の専門医が常駐し、診療にあたります。
再生医療では自身の血液を使った治療のため副作用が少ない点が特徴です。
しかし、合併症や副作用が不安な方でも、専門医常駐のため安心していただけます。
また、専門医による診断により、再生治療のうちそれぞれの患者に最適な治療を選択可能です。
さらに、再生医療以外の保存治療やリハビリまで再発防止を含めた治療を提案します。
安心して治療をはじめられる保証制度
再生医療は最新医療であり、自費診療のため、効果を心配する方もいるでしょう。
そのような方のため、二段階の保証制度があります。一つ目の保証制度は、再治療保証です。
提案した治療をおこなったにもかかわらず、治療効果が出なかった場合には治療が追加で1回分、無料で提供されます。
保証対象は幹細胞培養治療を2回以上契約した方で、リハビリスタンダードコースを6か月以上継続した方で、保証期間は初回治療から1年間です。
二つ目に、再生医療の施術により健康被害を被った場合のリスク保証があります。
シン・整形外科では再生医療サポート保険に加入しており、患者に万が一被害があった際にも保証可能です。
まとめ

手指の第一関節にできる水ぶくれのような膨らみは、へバーデン結節にともなう「粘液嚢腫(ミューカスシスト)」である可能性があります。これは、関節の変形が進むことで関節液が皮膚の下にたまり、ゼリー状のふくらみとして現れるもので、中高年の女性に多く見られます。見た目は小さな水ぶくれでも、関節内部の異常が原因で起きているため、皮膚の問題とは異なります。
こうした水ぶくれが現れた場合、絶対に自分で潰すことは避けるべきです。針や爪で潰すと、そこから細菌が侵入し感染を引き起こす危険性があり、炎症や膿がたまるなど症状が悪化するおそれがあります。もし破れてしまった場合は、患部を清潔に保ち、消毒とガーゼなどでの保護を行い、できるだけ早く整形外科や手の専門医を受診することが重要です。
医療機関では、針で中の液体を抜く穿刺や、必要に応じて嚢腫の切除といった処置が行われることがあります。また、関節への負担を減らすための装具やテーピング、炎症を抑える薬の使用なども検討されます。指を安静に保ち、再発や悪化を防ぐことも治療の一環となります。
水ぶくれのように見えても、へバーデン結節が原因の場合は根本的に関節の問題があるため、早期に専門医の診察を受け、適切な対処をすることが進行を抑える鍵となります。
<参考>
シン・整形外科