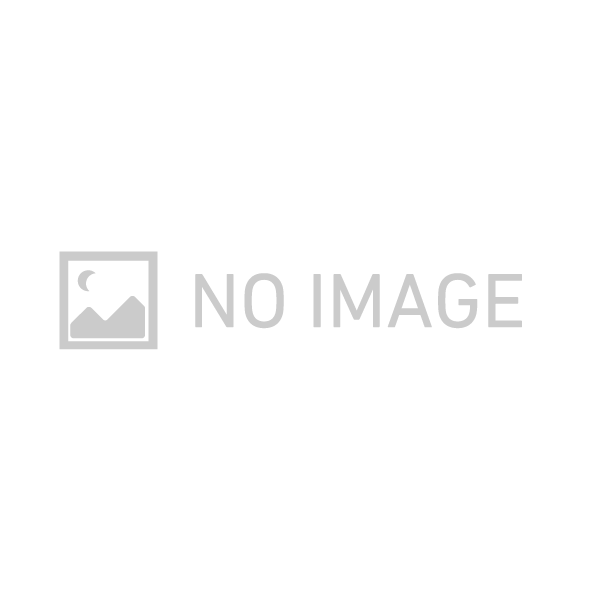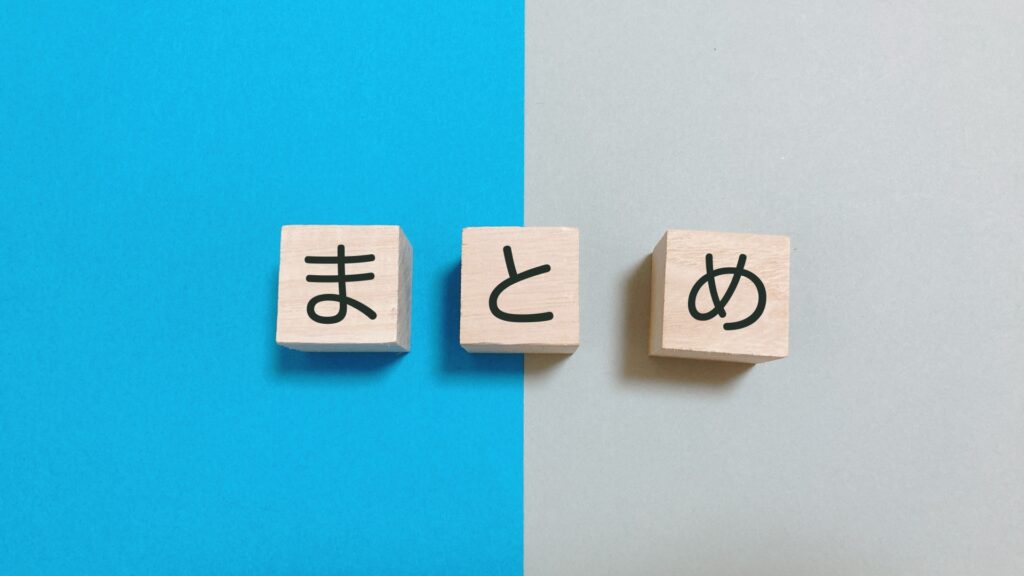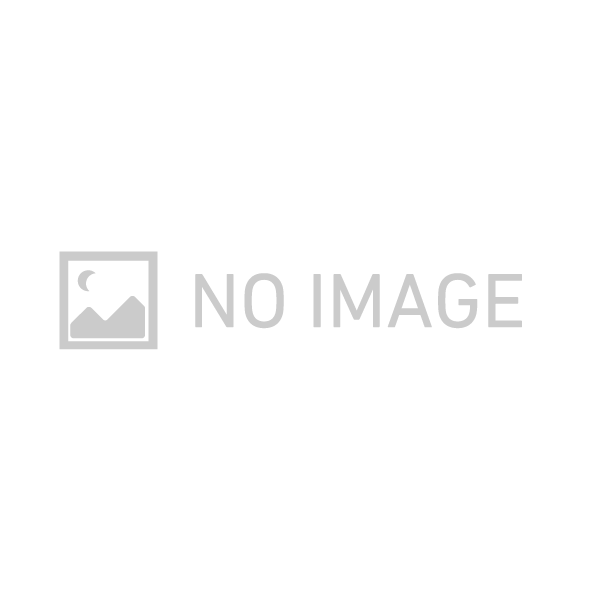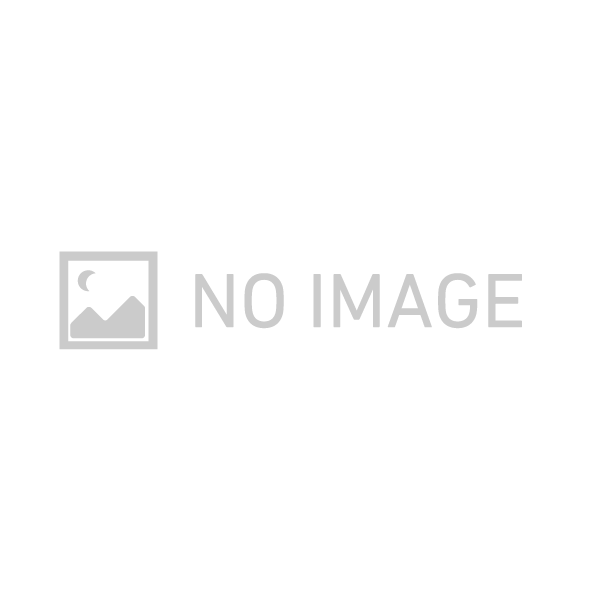運動中や仕事中に肘の痛みや違和感を覚えた経験のある方も多いのではないでしょうか。
普段の生活における肘の痛みや違和感の原因が、実はテニス肘と呼ばれる症状である可能性もあります。
本記事では、
テニス肘の原因について詳しく紹介します。
また、テニス肘を発症しやすい動作や、テニス肘の治療方法についてもあわせて解説します。
テニス肘にお悩みの方や、テニス肘の原因や治療法について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とはどのような病気?

テニス肘は、上腕骨外側上顆炎と呼ばれるスポーツ障害です。
肘と腕をつなぐ腱と呼ばれる部位に炎症が起こることで発症します。
テニス肘の特徴は、
指先や手首を動かしたときに肘関節の外側に痛みが出ることです。
テニス肘は軽度の場合、しばらく安静にしておけば痛みが緩和しますが、放置すると痛みが慢性化し、最終的に手術が必要になるケースもあります。
そのため、肘の痛みが長引く場合は、早期に適切な処置をおこなう必要があります。
テニス肘の原因

テニス肘の主な原因は、肘や手首への過度な負荷です。
肘や手首を酷使すると、肘周辺の筋肉や腱に炎症が生じます。
一時的な炎症であれば患部を安静にしていると改善しますが、毎日のように負荷がかかる動作を続けていると症状が強まり、痛みや腫れなどが現れます。
そのため、
肘や手首をよく利用するスポーツや職業はテニス肘を発症するリスクが高いことも特徴です。
テニス肘になりやすい動作

ここでは、テニス肘になりやすい動作について詳しく紹介します。
スポーツ中や仕事中など、普段の生活における自身の動作もぜひチェックしてみてください。
肘や手首を酷使するスポーツ
肘や手首を酷使するスポーツは、テニス肘の発症リスクを高めます。
病名の一部でもあるテニスをおこなう場合、スイング動作には注意が必要です。
テニスのスイング動作に必要な筋肉は上腕部に集約しており、一つの腱として存在しています。
そのため、テニスのスイングをおこなうと上腕部に負荷がかかり、筋肉の疲労や腱の炎症につながる場合があります。
肘や手首への負荷を減らすためには、
スイングフォームやラケットの握り方の見直しが大切です。
スイング時に手首をひねりすぎていたり、ラケットを握る手に力が込められすぎていたりすると、腕への負荷を強めます。
手首や腕に過度な力が入らないように注意しながら、プレーや練習をおこないましょう。
肘や手首を酷使する職業
肘や手首を酷使する職業も、テニス肘の発症リスクを高めます。
テニス肘はハンマーやドライバーなどの工具を扱う職人の方や、ハサミや櫛を扱う美容師の方などに生じやすい特徴があります。
また、
キーボードやマウスを扱うデスクワークが原因で発症するケースもあります。
長時間のパソコン操作もテニスのスイング同様の負荷がかかるため、筋肉や腱の炎症につながる場合があります。
仕事中に肘の痛みや違和感を自覚した際には、適度に休憩を取ったり軽くストレッチしたりして手首を休めましょう。
肘や手首に過度な負担がかかる家事
テニス肘は、肘や手首に過度な負担がかかる家事が原因で発症する場合もあります。
洗濯の際に衣類を絞ったり、料理の際に包丁やフライパンを扱ったりする場合など、家事には肘や手首に過度な負担がかかる動作が多数存在します。
家事中に肘の痛みが出る場合は適度に休憩を取り、なるべく患部を安静に保ちましょう。
また、
日常動作に特化した肘用サポーターの利用もおすすめです。
サポーターの装着により、肘への負担や患部の痛みの軽減にも期待が持てます。
テニス肘とゴルフ肘の違い

テニス肘とゴルフ肘は、肘関節の炎症部位の違いにより区別されます。
テニス肘は肘関節の外側、ゴルフ肘は肘関節の内側の筋肉や腱に炎症が認められます。
いずれも固有のスポーツ名がついていますが、必ずしもテニスやゴルフが原因で発症するわけではなく、
誰にでも発症の可能性があるスポーツ疾患です。
テニス肘の痛みと症状

テニス肘の痛みは、
肘の外側から前腕部にかけて出現する特徴があります。
軽度の場合は腕を動かした際のみ痛みが現れ、安静時には痛みが緩和します。
テニス肘が悪化すると安静時にも痛みが現れ、慢性化すると手術が必要になるケースもあるため注意が必要です。
テニス肘の診断と検査

テニス肘はさまざまな方法を利用して診断や検査がおこなわれています。
ここでは、テニス肘の診断と検査について詳しく紹介します。
Thomsenテスト
Thomsen(トムセン)テストは、
特定の状態における痛みの有無を調べる診断方法です。
肘を伸ばし、かつ手首を上に反らせた状態で、医師が手首に逆向きの力を加えます。
また、肘と指先をまっすぐに伸ばした状態で、医師が中指を上下に動かします。
いずれの方法も、医師が手首や指先に力を加えた際に肘の外側に痛みを感じる場合、テニス肘の可能性が高いと考えられます。
Chairテスト
Chairテストは、
診断名の通り椅子を利用する診断方法です。
肘を伸ばしたまま椅子を持ち上げた際に肘の外側に痛みを感じた場合、テニス肘と診断されます。
中指伸縮テスト
中指伸縮テストは、
中指に力を加えた際の痛みを確認する診断方法です。
中指をまっすぐに伸ばした状態で医師が上から中指に力を加えます。
上からの力に抵抗する際に肘の外側や上腕部に痛みが生じた場合、テニス肘と診断されます。
レントゲン検査
レントゲン検査では、骨折をはじめとする他の疾患との判別がおこなわれます。
また、
テニス肘の慢性化に伴う炎症部位の石灰化の有無も確認可能です。
肘周辺の骨に異常がない場合や、肘周辺の石灰化が認められる場合にテニス肘と判断されるケースがあります。
テニス肘の治療方法

テニス肘は症状の程度により、さまざまな方法で治療が進められます。
ここでは、テニス肘の主な治療法について詳しく解説します。
保存療法
テニス肘の治療では、まず
保存療法がおこなわれることが一般的です。
保存療法では、安静療法や薬物療法が実施されます。
まずは手首や肘に負荷のかかる運動や仕事を控えて経過観察をし、場合により薬物療法で湿布や鎮痛剤などを併用します。
また、痛みや炎症の程度によりステロイド剤を投与して症状を改善します。
リハビリテーション
テニス肘の治療では、運動療法とも呼ばれるリハビリテーションをおこなう場合もあります。
医師や理学療法士の指示に従い、腕の筋肉を維持したり可動域を広げたりする効果のある運動療法を進めます。
リハビリテーションの効果はすぐに現れないため、
長期的な実施が必要です。
また、ストレッチやトレーニングのみならず、普段の生活において注意したほうがよい動作やセルフケアなどを提案してもらえる場合もあります。
再生医療
テニス肘の治療では、再生医療を実施する場合もあります。
肘に関する再生医療では、PRP療法や体外衝撃波治療が主に実施されています。
PRP療法は、自身の血液を利用する治療法で自己多血小板血漿注入療法とも呼ばれています。
自身の血液中に含まれる血漿と血小板を抽出し、PRPと呼ばれる多血小板血漿を作成して患部へ注射します。
組織の修復をサポートする血漿と止血作用を有している血小板の働きをうまく活用した治療法のため、組織の修復を促すとともに痛みや炎症の改善に期待が持てます。
また、自身の血液を利用するため、拒絶反応やアレルギー反応などのリスクを低減できます。
体外衝撃波治療は、
患部に衝撃波を与えて故意に炎症反応を生じさせる治療法です。
炎症反応が生じた組織は患部周辺の代謝活性を増加させるとともに、新しい血管の形成を促進させて損傷組織の再生を促します。
体外衝撃波治療は、テニス肘をはじめ、慢性的な肩こりや五十肩の改善などにも効果が期待されています。
手術療法
保存療法による効果が認められない場合や症状が長引く場合には、手術療法の必要性が出てきます。
テニス肘の手術療法は、炎症している腱を切除する方法や損傷組織を取り除く方法などさまざまです。
自身のテニス肘の症状や患部の状態に応じた、適切な手術法が提案されます。
テニス肘の予防や改善に有効なセルフケア方法
ここからは、テニス肘の予防や改善に有効なセルフケア方法を紹介します。
肘や手首のストレッチ
肘や手首のストレッチは、
テニス肘の予防や改善に効果的です。
肘を真っ直ぐにぴんと伸ばし、手首を地面のほうへ曲げて静止します。
当ストレッチは肘周辺の筋肉をやわらげるのみならず、痛みの緩和にも期待が持てるため、毎日数回実施してみてください。
肘や手首の筋力トレーニング
テニス肘の予防や改善には、
ストレッチのみならず筋力トレーニングも有効です。
とくにテニス肘の症状が長引いていたり、慢性化していたりする方におすすめです。
筋力トレーニングには軽めのダンベルやトレーニングチューブを活用しましょう。
1kg程度のダンベルを持ち上げたりチューブを引っ張ったりすると、肘や手首が鍛えられます。
ただし、筋力トレーニングは同時に負荷もかかるため、患部の痛みや熱感などの症状を強めてしまうリスクもあります。
テニス肘の症状を悪化させないためにも、過度な筋力トレーニングはおこなわないようにしましょう。
患部のアイシング
患部のアイシングも、テニス肘の予防や改善に効果的です。
テニス肘の原因は肘周辺の筋肉や腱に生じている炎症です。
炎症を鎮めるためには患部のアイシングが有効とされており、同時にマッサージを実施すれば痛みの緩和にも期待が持てます。
ただし、テニス肘が慢性化している場合は患部を冷やすのではなく、温めることが必要であるため注意しておきましょう。
テーピングやサポーターの装着
テニス肘の予防や改善には、
テーピングやサポーターの装着も効果的です。
肘や手首を利用する運動や仕事をおこなう必要がある方は、テーピングにより患部周辺をサポートしましょう。
また、サポーターの装着により患部周辺を守り、負荷を軽減できます。
テニス肘専用のサポーターも市販されているため、ドラッグストアやスポーツ用品店などで自身にあう製品をチェックしてみてください。
手術をせずに短期間でテニス肘を治療したい場合はシン・整形外科がおすすめ!
手術をせずに短期間でテニス肘を治療したい場合には、シン・整形外科がおすすめです。
シン・整形外科は東京都中央区にあり、銀座駅から徒歩で約1分とアクセスも良好です。
土日診療もおこなわれているため、平日の仕事でなかなか時間が取れない方にもおすすめの医療機関でもあります。
ここからは、
シン・整形外科でおこなわれている治療方法や特徴などを紹介します。
テニス肘の治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
切らずに痛みを取り除く再生医療が充実している
シン・整形外科の特徴は、再生医療が充実していることです。
再生医療は、私たちの体が持つ治癒力を用いて、
症状を治療する最先端の治療法です。
シン・整形外科では、患者に負担のない形で関節の痛みを取り除き、従来通りの生活を送れることを目的としています。
そのため、従来の医療では実現が難しい組織の再生や痛みの除去に効果的な再生医療を豊富に採用しています。
シン・整形外科の再生医療には、幹細胞培養治療やPRP治療などの複数の手法があるため、一人一人にあわせた治療法を提案できることも強みです。
整形外科の専門医による診察を受けられる
シン・整形外科の強みは、
整形外科の専門医による診察を受けられることです。
シン・整形外科に在籍している医師は、日本整形外科学会認定の専門医です。
整形外科専門医による丁寧な診察による安心感をはじめ、診断の正確さにも期待が持てます。
また、医師は専門分野の知識はもちろんのこと、再生医療に関する十分な実績も有していることも強みです。
そのため、的確な診断とともに最適な治療法の提案にも期待が持てます。
そして、シン・整形外科は完全予約制のため、診療当日は待ち時間を持て余すことがないこともメリットです。
経験豊富な理学療法士によるマンツーマンのリハビリ体制
シン・整形外科の特徴は、リハビリ体制にも力を入れていることです。
シン・整形外科の理学療法士は、厳格な審査に通過したうえで在籍しています。
経験豊富な理学療法士によるリハビリは週に1回、マンツーマン体制で実施されます。
マンツーマン体制のため安心してリハビリをおこなえるほか、気になる症状や疑問なども相談しやすい環境が整えられています。
また、
リハビリ内容は再生医療の効果を最大化できるように考慮されている特徴もあります。
そして、リハビリのみならず、自宅でおこなえる運動指導やアドバイスも受けられます。
リハビリとセルフケアにより、テニス肘の改善や再発防止効果にも期待が持てます。
まとめ
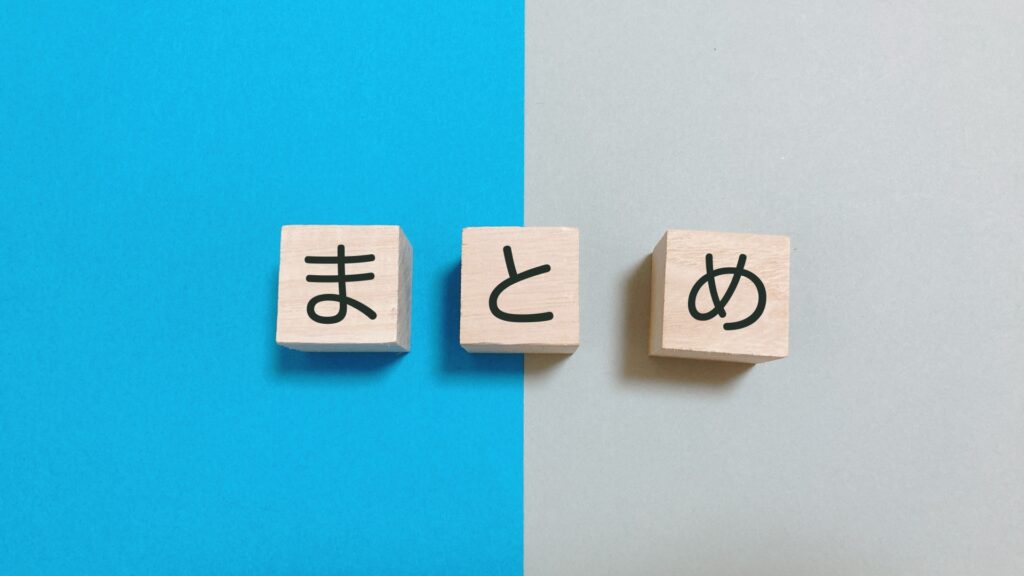
今回紹介したように、テニス肘は上腕骨外側上顆炎と呼ばれるスポーツ障害です。
肘と腕をつなぐ腱と呼ばれる部位に炎症が起こることで発症し、指先や手首を動かしたときに肘関節の外側に痛みが出る特徴があります。
テニス肘の主な原因は、肘や手首への過度な負荷です。
そのため、肘や手首をよく利用するスポーツや職業はテニス肘を発症する可能性を高めます。
テニス肘は、ThomsenテストやChairテスト、中指伸縮テストやレントゲン検査などの方法により診断されています。
また、テニス肘の治療では、まず薬物療法を取り入れ、必要に応じてリハビリテーションや再生療法が行われるケースが一般的です。
そして、薬物療法やリハビリテーションでも効果が認められず、症状が改善しない場合には手術療法が採用される場合があります。
テニス肘の可能性がある場合、早期診断と早期治療を受けることが大切です。
肘の外側に腫れや痛みがある方は、自己判断で放置せず、速やかに医療機関を受診しましょう。
テニス肘の治療には、シン・整形外科がおすすめです。
シン・整形外科では、さまざまな再生医療が取り入れられているため、自身の症状や状況に適した治療を提案してもらうことができます。
再生医療はメスを入れずにおこなえる治療のため、手術療法以外でテニス肘を治したい方にもおすすめです。
テニス肘にお悩みの方や、テニス肘の症状が疑われる方は、ぜひシン・整形外科の利用も検討してみてください。