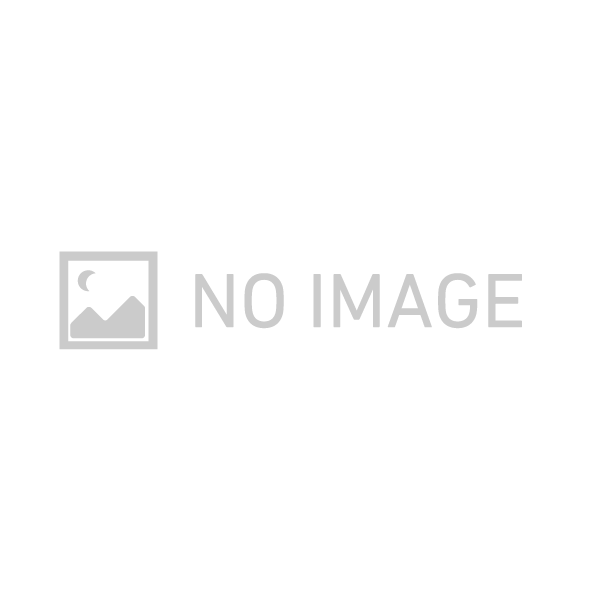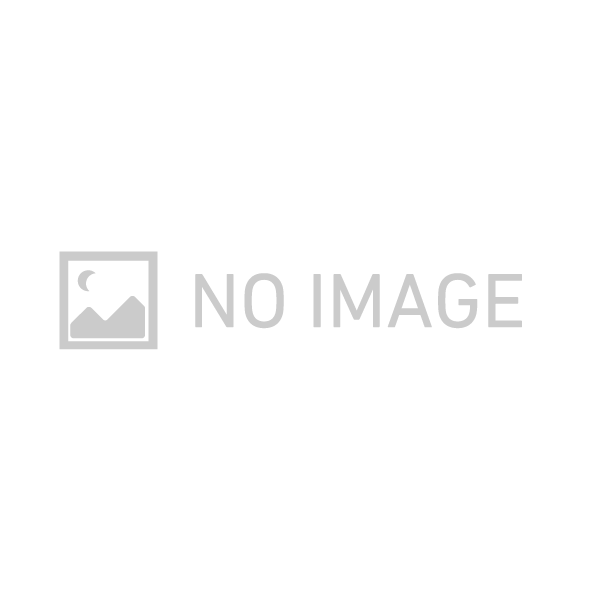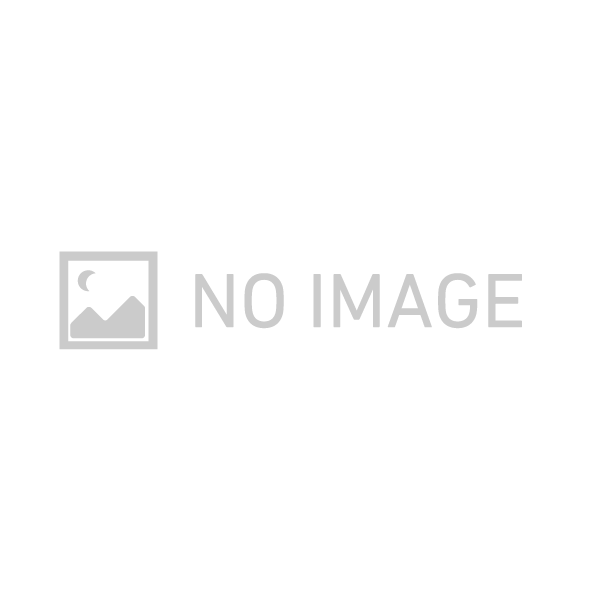加齢とともに衰えていく代表的な体の部位が膝関節です。膝は複雑な構造を持つ部位であり、衰えると多くの場合痛みが生じます。
歩行時や起床時、膝を動かし始めたときに痛みを感じる方は注意が必要です。
痛みが軽微だからと言って放置しておくと、自然に治らないばかりか変形性膝関節症をはじめとする深刻な病気に進行する可能性が高まります。
今回は、膝に痛みを感じたときに症状を自身でチェックできるリストを用意しました。リストをチェックすることで、膝の痛みの原因が病気であるのかどうかが分かります。
さらに膝の痛みの原因となる病気の種類、症状と原因、主な対処および治療法についてもあわせて解説しています。
記事を最後まで読めば、膝の痛みへの不安を取り除く方法が必ず見つかるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
膝の痛みの症状チェックリスト

膝の痛みでお悩みの方は、次のリストで当てはまる項目がいくつあるのかチェックしてみてください。
- 正座がつらい
- 膝が腫れている
- 歩き始めたとき痛む
- 膝の内側を押すと痛む
- しゃがむ姿勢がつらい
- 立ち上がるときに痛む
- 歩き続けていると痛くなる
- 階段の上り下りのときに痛む
- 膝を動かすときしむ音がする
- 膝のケガで医者にかかったことがある
チェックした項目の数に応じて、疾患の可能性がある、もしくは疾患の予備軍になっているのどちらかに分類できます。
詳しく見ていきましょう。
疾患の可能性のある方
チェックした項目の数が4つ以上の方は、膝の疾患を患っている可能性が高いです。
膝の疾患は通常、急に悪化することはまれです。しかし、痛みを放置しておくと変形性膝関節症や大腿骨顆部骨壊死などの重篤な症状へと進行する恐れがあります。
膝の疾患は、他の部位と同じく症状が軽度なほど治療しやすくなります。痛みを放置して自然に治まるのを待つことは、悪化するリスクを考慮すれば危険な判断と言えるでしょう。
なるべく早めにクリニックで医師の診察を受け、適切な治療を施すことをおすすめします。
疾患の予備軍に入る方
チェックした項目の数が3つ以下の方は、膝の疾患の予備軍と言えます。
膝の疾患は、初期症状が現れないケースも少なくありません。日常生活に影響を与えない範囲であれば、そのまま経過を見てみるのもよいでしょう。
とはいえ膝の疾患は、放置しておくと自然に治らないばかりでなく、症状が進行して悪化する可能性もあります。痛みが続いたり不安を感じたりする場合は、速やかにクリニックでの受診をおすすめします。
膝の痛みを感じる主な原因・症状

膝の痛みを感じる際、考えられる主な原因と症状は次のとおりです。
- 体重増加
- 運動不足
- 関節リウマチ
- 痛風・偽痛風
- 変形性膝関節症
- 大腿骨顆部骨壊死
それぞれ詳しく見ていきましょう。
体重増加
座る、立つ、歩くなどの日常生活の動作で、膝には常に負荷がかかっています。歩行時に体重の2~3倍、階段の上り下り時には6~7倍もの負荷がかかるとされ、体重が増えるほど膝の負担は大きくなります。
負担が大きくなると影響を受ける部位が軟骨です。軟骨は、膝への衝撃を和らげるクッションのような役割を担っています。
体重が増えるほど軟骨はすり減りやすくなります。軟骨がすり減ると骨と骨がぶつかる頻度が高まり、その結果生じる症状が炎症です。炎症の多くは痛みを伴います。
また、体重が増えすぎた方は、いわゆるO脚になりやすい傾向があります。O脚になる原因は、体重増加によって膝の内側への負荷が大きくなることです。
負荷が大きくなると軟骨がすり減りやすくなり、炎症による痛みのリスクも高まります。
運動不足
痛みの原因に膝の筋力と関節の柔軟性の低下があります。筋力と柔軟性は運動によって高まるため、運動不足が恒常化している方は注意が必要です。
膝は、関節にかかる負荷の一部を筋力で支えていますが、運動不足により筋力が低下すると負荷を支えづらくなります。
その結果、
関節に負荷が集中し、軟骨への負担が増して摩耗が早まり、痛みの原因となる炎症を引き起こします。
運動不足によるもうひとつの弊害が膝関節の柔軟性の低下です。関節は、動きが少なくなると細胞の代謝が滞って硬くなってしまいます。
関節が硬くなると膝をスムーズに動かすことが困難になり、曲げ伸ばしがしづらくなるほか、周囲に痛みが生じます。
関節リウマチ
関節に生じた炎症が骨や軟骨を侵食して関節部を変形させてしまう病気です。原因は免疫の異常によるものとされています。
関節液が膝に溜まって腫れる、歩行時や階段の昇降時に痛むなどが主な症状です。
関節リウマチの患部はやわらかく熱を帯びており、起床時にこわばって動かしにくくなる点が特徴です。腫れの度合いによっては、夜寝ているときにも痛みを感じます。
痛風・偽痛風
痛風は主に足の親指の付け根に激痛が起こる病気ですが、膝関節にも発生するケースが見られます。
血液中の尿酸が一定量を超え、結晶が関節部に蓄積されることが原因です。偏った食生活、運動不足、肥満やメタボリックシンドロームなどが尿酸増加の一因とされています。
偽痛風は、膝に水が溜まって腫れる、痛む、動かせなくなるなどの症状が見られるほか、発熱するケースもある病気です。何の前触れもなく突然発症することが多く、膝のみではなく全身の関節に起こる点が特徴です。
尿酸以外の結晶(ピロリン酸カルシウム)が関節内に蓄積することが原因ですが、なぜ蓄積するのかは解明されていません。一部は遺伝によるものと考えられています。
変形性膝関節症
膝が痛む病気のなかでも発症例が非常に多いものが変形性膝関節症です。
主な原因は加齢で、長年繰り返し膝に負担がかかることで軟骨がすり減り、痛みや腫れを引き起こします。
変形性膝関節症の症状は、初期、中期、末期の3つに分かれます。
初期
起床時や歩行時など、膝を静止した状態から動かし始めるときに違和感や軽い痛みが生じます。しばらく膝を動かさず安静にしていると痛みが治まる点が初期症状の特徴です。
中期
歩いている間、常に痛みを感じるようになります。スムーズに膝の曲げ伸ばしができなくなるケースも多くなります。
末期
階段の昇降がつらくなる、正座ができなくなるなどの動作への支障のほか、膝に水が溜まって腫れたり熱を帯びたりする症状が現れます。
関節が変形し、いわゆるO脚となって、膝をまっすぐに伸ばして歩くことが困難になるケースも見られます。
大腿骨顆部骨壊死
大腿骨と呼ばれる、太ももの骨の下側の端が大腿骨顆部骨です。大腿骨顆部骨が壊死、すなわち骨の細胞が死滅する病気が大腿骨顆部骨壊死です。
原因はまだ解明されておらず、血流障害が関係しているのではないかと考えられています。
突然激痛が走る、または少しずつ痛みが増していく症状が見られます。進行した場合は、壊死した部位が陥没するケースもあります。
高齢の女性に多く発症する点が特徴で、初期は自覚症状がなく、レントゲン検査でも壊死が見つからない場合が大半です。
膝の痛みの対処・治療法

膝に痛みが生じた際の対処および治療法を紹介します。主な方法は次のとおりです。
それぞれ解説します。
筋トレ
痛みの原因が運動不足である場合に効果的な方法です。
膝周辺の筋力を強化し、関節にかかる負荷を軽減させることが目的です。
痛みを抑えるためには、膝関節と密接な関係を持つ太ももや脛の筋肉を重点的に鍛えるとよいでしょう。
スポーツジムで器具を用いたトレーニングのほか、運動が苦手な方や高齢の方には、階段の上り下りやスクワットなど自重を利用した方法がおすすめです。
膝を動かすことで、関節の柔軟性を高める効果も期待できます。柔軟性が高まれば膝の動きも滑らかになり、思いどおりに曲げ伸ばしができるほか、痛みの予防につながります。
医師監修のサポーター使用
膝の痛みの原因となる病気そのものを治療することはできませんが、痛みの緩和や症状の進行を遅らせる効果が期待できる方法です。
サポーターを使用するメリットには、患部を温めて血流を促せる点と、膝を固定し安定させることで関節への負担を減らせる点の2つが挙げられます。
現在はさまざまなサポーターが販売されています。選ぶ際は、効果が期待できる医師監修の製品がおすすめです。
ダイエット
ダイエットで体重を減らすことも有効な膝の痛みの対処法です。痛みの予防や緩和のためには膝への負担を和らげることが大切です。
歩行時、膝にかかる負荷は体重の2~3倍とされています。すなわち、
1kgダイエットすれば、2~3kgも負担を減らすことが可能です。
膝を守るために、食事制限や運動習慣を取り入れて、少しずつでも着実に体重を減らしていくことをおすすめします。
膝の病気の治療方法
膝の痛みの原因となる、代表的な3つの病気は次のとおりです。
現在確立されている、それぞれの治療法を解説します。
変形性膝関節症
変形性膝関節症の主な治療法は、薬物療法、理学療法、手術療法の3つです。
まず薬物療法では、鎮痛薬等の内服薬の服用、塗り薬や湿布等の外用薬の添付があります。また膝関節内にヒアルロン酸やステロイドなどを直接注射し、鎮痛の緩和や炎症の抑制を期待する治療もあります。
理学療法では運動療法や装具療法、温熱療法があります。運動療法では、リハビリや筋トレ、ストレッチなどで、大腿四頭筋と呼ばれる太もも前側の筋肉を鍛えます。大腿四頭筋の筋力を鍛えることで膝にかかる負荷を減らし、痛みを緩和させる効果を狙います。
装具療法では、膝の内側に体重が偏ることを防ぐために足底板(インソール)を使用して体重のかかる場所を変える方法や、サポーターを用いて膝を固定し、痛みの出やすい動作を防ぐ方法があります。
温熱療法では、長時間の入浴やサポーターの着用で膝を温め、周りの血流を良くすることで痛みの緩和を図ります。
上記のような保存療法を一定期間続けても効果が見られず、改善の見込みがない場合には手術療法が検討されます。
変形性膝関節症の治療には、金属製の人工関節に置き換える手術が主流です。手術は体への負担も少なからずあるうえ、術後は入院や長期のリハビリがともなうため、実施の際は医師や家族と十分に相談することをおすすめします。
関節リウマチ
関節リウマチの主な治療法は、薬物療法、理学療法、手術療法の3つです。
薬物療法は、発病初期に多く用いられる方法です。痛みを和らげ、症状の進行を予防することが目的です。
免疫異常に作用する抗リウマチ薬、痛みをやわらげる効果のあるステロイドまたは非ステロイド系消炎鎮痛剤などの薬剤を使用します。
理学療法は、関節周りの筋肉や腱の働きをリハビリによって改善する方法です。薬物療法と併用されるケースが多く見られます。
リハビリは医師、理学療法士、作業療法士などの医療スタッフの指示のもと行われます。
症状が悪化し、関節の破壊が進行した場合は手術療法が検討されます。変形性膝関節症と同じく、人工関節に置き換える手術が一般的です。
大腿骨顆部骨壊死
大腿骨顆部骨壊死の場合、壊死した部位の範囲によって治療法を選択します。
範囲が小さい場合は、運動療法、薬物療法、サポーターの使用などの保存療法によって症状の緩和を図ります。
壊死が進行し、範囲が大きくなった場合の有効な治療法は手術療法です。人工関節置換術のほか、自身の骨または軟骨を移植する手術が用いられます。
膝の痛みに関するよくある質問

膝の痛みに関する代表的な質問を2点ピックアップして回答します。
膝の痛みを感じる場合は病院に行くべきですか?
膝の痛みの原因はさまざまですが、適切な治療をせず放置した場合、治る可能性よりも悪化する可能性の方がはるかに大きいと言えます。
変形性膝関節症や大腿骨顆部骨壊死などの病気であれば、進行すると手術が必要となるケースも珍しくありません。
どのような病気でも、早期に治療をおこなうほど短期間に軽度の処置で済む場合が大半です。痛みの軽重にかかわらず、できるだけ早くクリニックで受診することをおすすめします。
レントゲンでは疾患がみつからない場合にも膝の痛みを感じるのはなぜですか?
レントゲン検査で分かることは、骨の形状に関する情報のみです。膝の痛みの原因は骨の形状以外にも、筋肉や靭帯の異常、炎症など多岐にわたります。
レントゲンはあくまで検査のひとつとして捉え、他の方法で骨以外の原因を探ることが大切です。
たとえばMRI検査なら、骨以外の体内部の状態を確かめることが可能です。
不安な方は、MRI設備のあるクリニックで検査することをおすすめします。
膝の治療にはシン・整形外科がおすすめ
シン整形外科の膝の治療は、以下の理由からおすすめです。
・専門知識と経験豊富な医師陣
・最新の医療技術
・安心の手術
・パーソナライズされたケア
専門知識と経験豊富な医師陣
シン整形外科は
専門知識を持つ医師がいるため、患者の症状や状態について本質的な診断や治療プランを提供しています。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、
幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、
患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。
親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ

今回は膝の痛みの症状をセルフチェックできるリストをもとに、病気の可能性の有無、病気の症状と原因、対処および治療法について解説しました。
膝の痛みの原因は病気を含めさまざまですが、放置しておくと重篤な症状に進行する恐れは否めません。
チェックリストで病気の可能性があると判明した方はもちろん、病気の予備軍に入っている方も、痛みを感じた時点でなるべく早期にクリニックで医師の診察を受けることをおすすめします。
どのような病気も、早期発見と早期治療が最も効果的な手段です。悪化して後悔する前に、クリニックへ出向いてください。