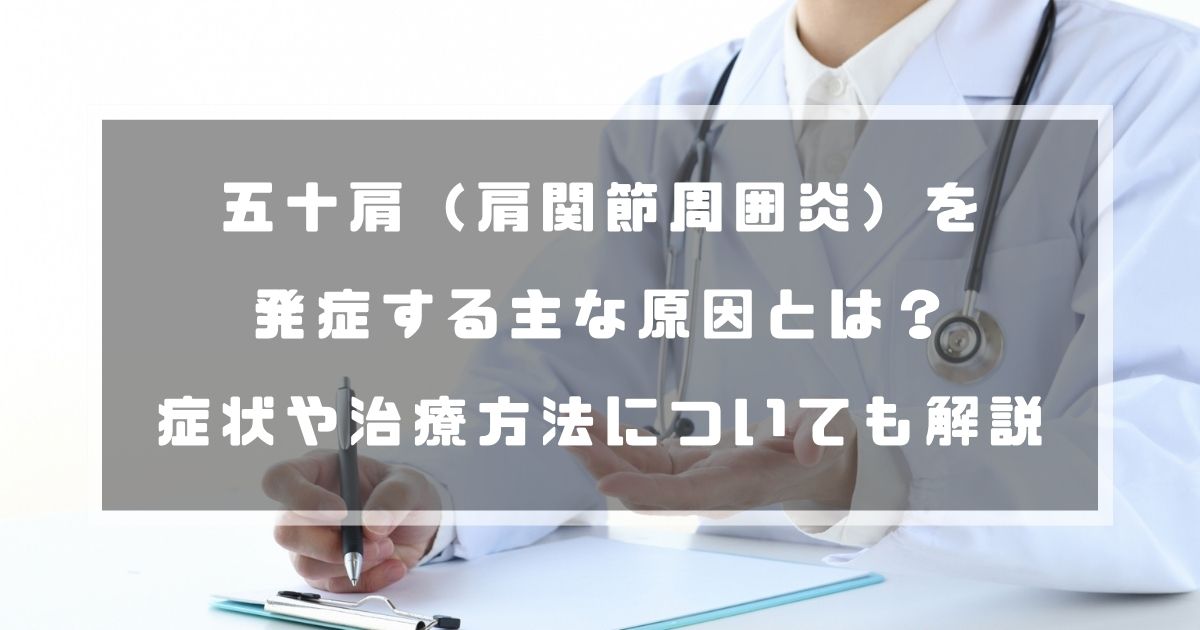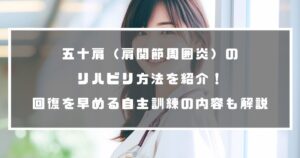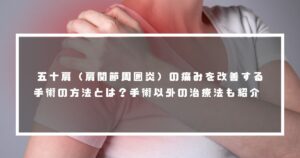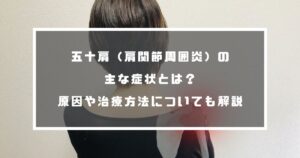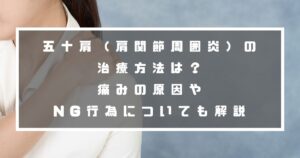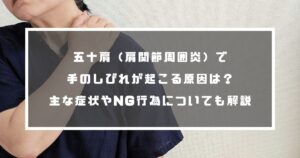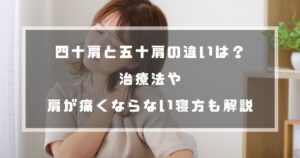五十肩は50代で発症する関節痛であり、肩を上げる日常的な動作が難しくなります。
歳を重ねれば誰でもなり得る病気ですが、どのように対策すれば改善されるのかわからず悩んでいる方も多いでしょう。
そこで本記事では、五十肩(肩関節周囲炎)を発症する原因や症状、治療法について詳しく解説します。
五十肩に似た疾患についてもあわせて紹介しているので、肩の痛みに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
五十肩(肩関節周囲炎)とは

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれ、肩の関節やその周辺にある筋肉や腱、靭帯、関節包などに炎症が起こることで発症する病気です。40代後半から60代にかけてよく見られ、特に50代に多く発症することから「五十肩」という名称で広く知られています。
この病気は、肩の痛みと動かしにくさを主な症状とし、特に腕を上に上げたり、背中に回したりといった動作が困難になります。発症の仕方には個人差がありますが、突然強い痛みが出て肩が動かせなくなる場合もあれば、徐々に痛みが強くなっていくケースもあります。また、夜間に痛みが増すことが多く、寝ている最中に痛みで目が覚めることもあります。
原因ははっきりとは解明されていませんが、加齢によって肩関節を構成する組織に変性が起きることが大きく関係していると考えられています。肩を動かさない状態が長く続くことや、過度な負担がかかったことなどが発症のきっかけになる場合もあります。
五十肩は自然に治ることが多い病気ですが、治るまでに半年から一年以上かかることも珍しくありません。病気の進行には段階があり、まず炎症による激しい痛みの時期が訪れます。この時期は特に夜間の痛みが強く、日常生活にも支障が出ることがあります。次に、痛みが少しずつ和らいでくると同時に、肩の動きが悪くなってくる時期があります。これを拘縮期と呼び、肩関節の動きが制限されてしまうため、腕が上がらない、背中に手が回らないといった不便を感じるようになります。最後に、少しずつ可動域が回復してくる回復期を迎え、日常動作も楽になっていきます。
五十肩(肩関節周囲炎)を発症する主な原因

先述したとおり、五十肩(肩関節周囲炎)のはっきりとした原因は解明されていません。
しかし、次のようなトラブルが引き金となり発症する場合があります。
- 老化
- 肩関節を構成する組織の炎症
- 肩に負担がかかるスポーツ
- 血流の低下
それぞれの原因について詳しく解説するので、症状を悪化させないためにも確認しておきましょう。
老化
肩関節は、上腕骨、肩甲骨、鎖骨などの骨に加えて、腱や靭帯、関節包、滑液包といった多くの組織で構成されています。これらの組織は、年齢とともに徐々に柔軟性や弾力を失い、摩耗や変性が進みやすくなります。特に、関節を包み込む関節包という膜の柔軟性が低下すると、炎症が起きやすくなり、動かすたびに痛みを感じるようになります。
さらに、肩を構成する腱の一部である腱板にも老化による変性が起きると、肩の安定性や滑らかな動きが損なわれ、関節周囲の摩擦や炎症が生じやすくなります。これが五十肩の直接的な引き金となることがあります。
また、年齢を重ねるにつれて運動量が減ったり、デスクワークなどで肩をあまり動かさない生活習慣が続くと、肩関節の可動域が狭まりやすくなります。こうした状況も、肩の組織に負担をかけ、炎症を引き起こす原因のひとつになります。
したがって、五十肩の発症には、加齢による組織の変性と、肩をあまり使わない生活スタイルが重なることが大きく関係しています。特に明らかな外傷や無理な運動をしていなくても、自然に発症することが多いのが特徴です。
肩関節を構成する組織の炎症
肩関節は、上腕骨の骨頭と肩甲骨の関節窩が接する構造になっており、それを取り囲むように関節包や靭帯、腱、滑液包といった軟部組織が存在しています。これらの組織が、加齢や使いすぎ、または逆に長期間肩を動かさなかったことによって傷んだり、柔軟性を失うことで、微細な損傷が生じ、そこに炎症が発生することがあります。
炎症が起こると、関節包が厚くなって硬くなり、滑らかな動きができなくなります。この状態が進行すると、肩の痛みや動かしにくさといった典型的な五十肩の症状が現れます。特に関節包の内側で炎症や癒着が起きると、腕を上げたり、背中に回したりといった動作が著しく制限されるようになります。
肩関節周囲の炎症は、はっきりした外傷がないまま起こることが多く、本人もいつから症状が始まったのか分からないケースが少なくありません。繰り返しの細かい刺激やストレスが関節周囲に蓄積され、それがやがて炎症として現れると考えられています。
このように、肩関節を構成する組織に炎症が起きること自体が、五十肩の発症の大きな要因となっています。炎症を起こす背景には、加齢による組織の弱化だけでなく、日常生活における姿勢や動作のクセも関係しているとされます。
肩に負担がかかるスポーツ
肩関節は、身体のなかでも非常に可動域が広い関節であり、日常動作はもちろん、多くのスポーツでも頻繁に使われます。特に野球の投球動作、テニスやバドミントンのスマッシュ、水泳のクロールやバタフライなど、腕を大きく振り上げたり、繰り返し速く動かしたりするスポーツでは、肩関節にかなりの負担がかかります。こうした動作では、腱板や関節包といった肩の安定に関わる組織が酷使され、微細な損傷が生じやすくなります。
長期間にわたり同じような負荷がかかり続けることで、肩の筋肉や腱、靭帯に疲労がたまり、炎症を引き起こすことがあります。若い頃は組織の回復力があるため問題になりにくいこともありますが、加齢とともに再生能力が低下してくると、こうした蓄積された負担がきっかけとなって、五十肩を発症することがあります。
また、過去に肩を痛めた経験がある人が無理をしてスポーツを続けていた場合や、フォームが崩れて誤った使い方をしていた場合なども、関節周囲にストレスが集中しやすくなり、結果的に炎症を引き起こす要因になります。
このように、肩に強い負荷がかかるスポーツを長年続けている人や、身体のケアを怠ってきた人は、五十肩を発症するリスクが高くなる傾向があります。年齢を重ねた後も運動を続ける場合には、肩を酷使しないフォームの見直しや、筋肉の柔軟性を保つためのストレッチ、無理のない運動量の調整が大切になります。
運動不足
肩関節は非常に可動域が広く、日常的に使っていないと動きが硬くなりやすい部位です。運動不足が続くと、肩を動かす機会が減り、関節を支える筋肉や腱、靭帯が衰えていきます。その結果、肩関節の動きが悪くなったり、血流が滞ったりして、関節包や腱板といった組織の柔軟性が失われてしまいます。こうした状態になると、少し肩を動かしただけでも炎症が起こりやすくなり、五十肩の引き金となることがあります。
特に、デスクワークやスマートフォンの長時間使用といった現代の生活スタイルは、腕を前に出したまま同じ姿勢を続けることが多く、肩を大きく動かす機会がほとんどありません。このような姿勢が長時間続くと、肩甲骨の動きも制限され、肩周囲の筋肉が硬くなってしまいます。その結果、肩関節にかかる負担が増し、関節包などに炎症が生じやすくなります。
また、運動不足によって体全体の筋力が低下すると、肩にかかる負荷を周囲の筋肉で分散できず、肩関節そのものに無理がかかるようになります。これもまた、五十肩の発症リスクを高める要因となります。
つまり、肩をあまり使わない生活が続くことで、肩関節周囲の組織が硬くなったり、炎症を起こしやすくなったりし、結果的に五十肩を引き起こすことにつながるのです。定期的に肩を動かすストレッチや、腕を大きく動かす軽い運動を日常に取り入れることは、予防にとって非常に重要です。
血流の低下
肩の関節やその周囲の組織は、細い血管によって栄養や酸素が届けられています。ところが、加齢や運動不足、長時間同じ姿勢を保つ生活習慣などによって、これらの血流が次第に悪くなると、関節を構成する腱や靭帯、関節包などの組織に十分な栄養が届かなくなります。栄養不足に陥った組織は、柔軟性を失いやすく、わずかな刺激や動作でも傷ついたり炎症を起こしたりしやすくなります。
また、血流が悪くなると、疲労物質や老廃物の排出も滞り、組織に慢性的な炎症が起こりやすくなります。このような状態が続くと、肩関節のまわりに慢性的なダメージが蓄積され、あるとき急に肩の痛みや動かしにくさとして現れることがあります。これが五十肩の発症につながると考えられています。
特に肩関節の血流は、もともと循環が豊富とは言えない部位であり、さらに冷えや運動不足によって血行が悪化しやすいという特徴があります。実際に、五十肩の患者には冷え性を伴っている人や、肩まわりをあまり動かさない生活をしていた人が多く見られます。
五十肩(肩関節周囲炎)の症状

五十肩(肩関節周囲炎)の症状は次のとおりです。
- 関節の動きが悪くなる
- 動かすと痛くなる
- 夜中に肩が痛む
- 痛みで腕が上がらない
- 安静時でも肩が痛む
五十肩には急性期、拘縮期、回復期の流れがあり、それぞれ症状が異なります。
病期ごとの症状を細かく解説するので、自身に当てはめながらチェックしてみてください。
関節の動きが悪くなる
五十肩では、肩関節の周囲にある関節包や腱、靭帯などの組織に炎症や硬化、癒着が起こることで、関節全体の滑らかな動きが失われていきます。これにより、肩の可動域が徐々に制限され、日常の何気ない動作にも支障をきたすようになります。たとえば、腕を上にあげる、背中に手を回す、物を取るために手を伸ばすといった動きが難しくなるのが特徴です。
初期の段階では痛みによって動かしにくさを感じることが多く、その後、痛みが和らいでも関節の硬さやこわばりが残り、思うように動かせない状態が続くことがあります。特に肩の前方や外側にかけての動きが制限されやすく、無理に動かそうとすると強い違和感や痛みを伴うことがあります。
このような可動域の制限は、炎症が落ち着いたあとでも数か月から長いときは1年以上続くことがあり、日常生活の質を大きく下げる原因になります。そのため、早期の段階からリハビリやストレッチなどで関節の動きを保つ努力が重要になります。
動かすと痛くなる
この病気では、肩関節を構成する関節包や腱、靭帯といった周囲の組織に炎症が起こるため、動かしたときにその部分が刺激され、痛みが引き起こされます。特に、腕を上に上げる、後ろに回す、服を着替える、荷物を持ち上げるなどの日常的な動作で痛みを感じることが多く、場合によってはちょっとした動きでも鋭い痛みが走ることがあります。
初期の段階では、動かしたときの痛みに加えて、じっとしていても痛むことがありますが、特に動作時の痛みが強く現れるのが特徴です。さらに、肩の動きが制限されることで無理な動かし方をすると、周囲の筋肉や他の関節にも余計な負担がかかり、痛みが広がることもあります。
また、痛みがあるために肩をかばって動かさなくなると、関節の可動域が狭まり、さらに動かすと痛いという悪循環に陥ることがあります。このような状態が続くと、炎症が落ち着いた後でも関節が硬くなってしまい、肩の動きが制限される「拘縮」という状態に進行することがあります。
夜中に肩が痛む
夜中に肩が痛むというのは多くの人が経験するつらい特徴のひとつです。
この痛みは、特に症状の初期や炎症が強い時期に現れやすく、夜間痛と呼ばれています。日中はなんとか我慢できていた痛みが、横になって身体を休めた途端に強まり、眠っている最中に肩の痛みで目が覚めてしまうというケースも少なくありません。睡眠の妨げになるだけでなく、疲労が蓄積しやすくなるため、心身の不調にもつながります。
夜間に痛みが強まる理由は、いくつか考えられています。まず、横になることで肩にかかる圧力や体重の影響が変わり、関節内の圧力や血流が変化することによって痛みが増すことがあります。特に痛む側を下にして寝ると、肩に直接負荷がかかりやすく、痛みが強くなる傾向があります。また、夜間は交感神経の働きが落ちて血流が減少しやすく、炎症物質が周囲にとどまりやすくなることも、痛みを助長する一因と考えられています。
このような夜間の痛みによって肩を動かすことがさらに億劫になり、結果的に可動域が悪化していくという悪循環に陥ることもあります。そのため、夜間痛が強い場合には、無理に動かさずに安静を保ち、枕の高さを調整したり、腕の下にクッションを入れて肩の負担を軽減したりするなど、寝るときの姿勢を工夫することが大切です。
痛みで腕が上がらない
この症状は、肩関節の内部で起きている炎症や、それに伴う関節包の癒着や拘縮が原因で、腕を上にあげる動作が強く制限されるものです。炎症の初期には、肩を動かそうとすると鋭い痛みが生じ、その痛みのために自然と動かすのを避けるようになります。結果として筋肉や関節まわりの組織が硬くなり、さらに動かしにくくなるという悪循環に陥ります。
とくに多くの人が困るのは、腕を真上に伸ばす動作や、頭より上にある物を取ろうとする動作、髪を結ぶ、洗濯物を干すといった日常的な動作ができなくなることです。また、背中に手を回す動作も困難になるため、下着をつけたり脱いだりするのにも苦労するようになります。
このような動作制限は、単に痛みの問題だけでなく、肩関節の可動域が実際に狭くなっていることが背景にあります。関節を包んでいる膜が硬く縮んでしまうと、動かそうとしても物理的に動かすことができなくなります。そのため、痛みがある程度治まっても、関節の動きが回復しない状態が続くこともあります。
安静時でも肩が痛む
この安静時の痛みは、特に炎症が強い初期の段階で現れやすく、何もしていなくても肩の奥がズキズキと痛んだり、重苦しさを感じたりするような状態になります。じっとしていても痛むため、仕事や家事に集中できなかったり、精神的なストレスがたまったりする原因になることもあります。
また、夜寝ているときなど身体を横たえているときに、痛みが一層強まるのも特徴です。これは横になることで肩周囲の血流や内圧が変化し、炎症部分に刺激が加わるためと考えられています。さらに、寝返りを打ったときに肩が引っ張られたり圧迫されたりすると、突然鋭い痛みを感じて目が覚めてしまうこともあります。
こうした安静時の痛みは、肩関節の内部で強い炎症が起きているサインであり、五十肩の初期段階では特に注意が必要です。日常生活でなるべく肩に負担をかけないようにしながら、必要に応じて消炎鎮痛薬の使用や冷却、あるいは医療機関での注射治療などを行うことで、痛みをやわらげることができます。
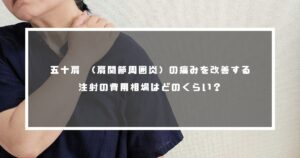
五十肩(肩関節周囲炎)と類似する疾患

五十肩(肩関節周囲炎)と類似する疾患は次のとおりです。
- 烏口突起炎
- 上腕二頭筋長頭腱炎
- 肩峰下滑液包炎
- 肩関節腱板炎
- 石灰沈着性腱板炎
- 肩関節拘縮
- 関節包炎
症状が似ていても異なる疾患では治療のアプローチも変わるため、よく見極める必要があります。
それぞれの疾患について解説するので、あわせて確認しておきましょう。
烏口突起炎
烏口突起炎とは、肩甲骨の前面にある「烏口突起」と呼ばれる小さな突起部分に炎症が生じ、痛みが出る状態を指します。烏口突起には、小胸筋、烏口腕筋、上腕二頭筋の短頭といった複数の筋肉が付着しており、これらの筋肉の使いすぎや外傷などが原因で、突起部分に負担がかかり炎症が起こります。
症状としては、肩の前側、特に鎖骨の下あたりに局所的な痛みが出ることが多く、腕を前に出したり、肩を内側にひねったりといった動作で痛みが強くなる傾向があります。肩の奥に重だるい違和感を覚えることもあり、烏口突起の部分を指で押すと鋭い痛みがはっきりするのが特徴です。
原因としては、ベンチプレスや投球など、肩の前方に反復的な負荷がかかる運動や、長時間パソコンやスマートフォンを使って肩が前に突き出た姿勢を保ち続ける生活習慣が挙げられます。また、転倒や打撲などによる局所的な衝撃、あるいは他の肩の病気をかばうために偏った動作を続けることで、烏口突起に過剰な力が加わる場合もあります。
上腕二頭筋長頭腱炎
上腕の力こぶをつくる筋肉である上腕二頭筋のうち、長頭と呼ばれる部分の腱に炎症が起こる状態を指します。上腕二頭筋には短頭と長頭の2本の腱がありますが、長頭腱は肩関節の中を通って上腕骨の溝に沿って走っており、その位置関係から特に摩擦や圧迫を受けやすく、炎症が生じやすいのが特徴です。
この病気は、主に肩を頻繁に使う動作を繰り返すことによって発症します。たとえば、野球やテニス、水泳などのスポーツ、あるいは日常生活の中で腕を上げる作業や重い物を繰り返し持ち上げるような動きが続くと、腱に過度な負担がかかります。その結果、長頭腱がこすれたり引っ張られたりして、腱の表面や周囲の組織に炎症が起きるのです。また、加齢によって腱の柔軟性が失われると、比較的軽い負荷でも炎症が起きやすくなります。
症状としては、肩の前面、特に肩のやや下あたりに痛みを感じることが多く、腕を前に出す、物を持ち上げる、肘を曲げるといった動作で痛みが強くなる傾向があります。安静時にはそれほど痛みを感じないこともありますが、肩を動かすたびにズキッとした鋭い痛みを伴うことがあり、悪化すると夜間にも痛みで目が覚めるようになります。また、肩を押さえたときにピンポイントで痛む場所があるのも特徴のひとつです。
診断は、肩の痛みの部位や動作による症状の変化を観察し、上腕二頭筋長頭腱に対する圧痛の有無、あるいは筋肉の力を入れたときの痛みなどを確認することで行われます。必要に応じて、超音波検査やMRIで腱の状態を詳しく調べることもあります。
肩峰下滑液包炎
肩関節の上部にある「肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)」という袋状の組織に炎症が起こる状態を指します。この滑液包は、肩峰という骨の下に位置し、腕を動かすときに腱や筋肉と骨がこすれないようにクッションの役割を果たしています。肩関節の動きが多い人にとって、この滑液包は非常に重要な存在ですが、使いすぎや外的な刺激によって炎症を起こすことがあります。
肩峰下滑液包に炎症が生じると、肩の上の部分ややや外側に痛みが出るのが特徴です。特に腕を上にあげる動作や、肩より高い位置での作業をすると痛みが強まることが多く、洗濯物を干す、棚の上のものを取るといった動作がつらくなります。また、夜寝ているときに痛みが強くなり、睡眠を妨げることもあります。痛みは鋭く出ることもあれば、じんわりとした鈍痛として続くこともあり、症状の程度には個人差があります。
この病気は、スポーツや重労働などで肩を頻繁に使っている人に多くみられますが、姿勢の悪さや肩の動きのバランスが崩れている場合にも起こることがあります。また、加齢によって肩周囲の組織が硬くなり、滑液包に過剰な負担がかかることでも発症します。腱板損傷や五十肩など、他の肩の疾患と合併しているケースも少なくありません。
診断は、痛みの部位や動きによる反応を観察することで行われます。肩を一定の角度まで上げたときに強い痛みが出ることが特徴のひとつです。必要に応じて、レントゲンやMRI、超音波検査などで滑液包の腫れや周囲の組織の状態を確認します。
治療としては、まず炎症を抑えるために肩を安静に保ち、消炎鎮痛薬の使用や湿布の貼付を行います。場合によっては滑液包内にステロイドを注射し、局所的に炎症を抑えることもあります。痛みが軽減してきたら、肩関節の可動域や筋力を回復させるために、リハビリやストレッチが導入されます。無理に動かしすぎると症状が悪化することがあるため、段階に応じた適切な運動が大切です。
肩関節腱板炎
上腕を動かす筋肉である腱板に炎症が起きると、肩関節腱板炎と診断されます。この状態では肩の可動域が制限され、特に腕を横に上げる動作や、頭上に物を持ち上げる動作で強い痛みを感じることがあります。日常生活ではシャツを着替える、髪をとかすといった動きでも違和感が出やすく、肩関節に繰り返し負担がかかることが発症の引き金になります。また、加齢により腱板がもろくなっていると、ちょっとした動作でも炎症が生じやすくなります。肩関節腱板炎は五十肩と間違われることもありますが、原因となる部位や治療方法が異なるため、専門的な診断が重要です。
石灰沈着性腱板炎
石灰沈着性腱板炎とは、肩の腱板にカルシウムの結晶(石灰)が沈着し、その部位に強い炎症が起こる病気です。突然、何の前触れもなく激しい肩の痛みが生じるのが特徴で、特に夜間に痛みが強くなりやすく、眠れないほどの苦痛を訴える人もいます。痛みのために腕を動かすことが困難になり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。原因ははっきりと解明されていませんが、加齢や血流の低下、肩にかかる慢性的なストレスなどが関係していると考えられています。レントゲン検査で石灰の沈着が確認されることが多く、急性期には消炎鎮痛薬や注射、冷却療法が行われ、慢性期にはリハビリや体操などで可動域の改善を図ります。
肩関節拘縮
肩関節拘縮とは、肩の動きが徐々に悪くなり、腕を上げたり背中に手を回すといった日常の動作がしづらくなる状態のことを指す。動かそうとしたときに痛みを感じるほか、症状が進むと安静にしているときや夜間にも痛みが出るようになり、眠れないこともある。五十肩の進行や、けが・手術のあとに肩を長く動かさずにいたことがきっかけとなるケースが多い。
原因にはいくつかの要素がある。肩まわりに炎症が起きると、関節包や靱帯、滑液包などの組織が癒着し、関節の動きが制限されるようになる。また、長期間肩を動かさないことで関節が固まってしまう場合や、糖尿病や甲状腺の病気といった全身の疾患が影響することもある。
症状としてよくみられるのは、腕を途中までしか上げられなかったり、髪をとかす・エプロンのひもを結ぶといった動作がしにくくなったりすること。痛みをかばって肩を使わない状態が続くと、さらに拘縮が進んでいく悪循環に陥ることもある。
診断では、問診や動きの確認に加えて、必要に応じてレントゲンやMRI、超音波検査などを行い、ほかの病気との見分けをつける。腱板断裂や石灰沈着性腱炎など、似たような症状の疾患との区別が重要になる。
関節包炎
関節包炎というのは、関節を包んでいる「関節包」と呼ばれる膜に炎症が起きた状態のことを指します。関節包には、関節を安定させたり、関節の中にある潤滑液を保ってスムーズに動かす働きがあります。肩や股関節、膝などさまざまな関節に存在しますが、特に肩で起こることが多く、肩関節包炎は五十肩の代表的な原因のひとつとされています。
肩の関節包炎になると、肩を動かそうとしたときに痛みが出たり、動かせる範囲が狭くなったりします。初めは何となく肩が重い、動かしにくいと感じる程度でも、次第に腕が上がらない、背中に手が回らないといった明らかな可動域制限が出てきます。夜間にうずくような痛みで眠れないという症状が現れることもあります。
炎症が起こる原因ははっきりしないこともありますが、加齢にともなう変化、肩の使いすぎ、けがや手術のあとで肩を長期間動かさなかったことなどがきっかけになる場合があります。炎症が長引くと関節包が硬くなり、さらに動かしにくくなる「拘縮」という状態につながることもあります。
治療は、まず痛みや炎症を抑えることから始まります。消炎鎮痛薬の服用や湿布、必要に応じて肩に注射を行うこともあります。ある程度痛みが落ち着いてきたら、無理のない範囲で肩を動かすリハビリを取り入れていきます。温熱療法やストレッチなどを組み合わせながら、少しずつ動かせる範囲を広げていくことが大切です。
五十肩(肩関節周囲炎)の診断方法

五十肩(肩関節周囲炎)の診断は、次のような方法でおこなわれます。
- 問診
- 視診
- 画像所見
それぞれの内容を詳しく解説します。
問診
五十肩(肩関節周囲炎)の診断において、最初に行われるのが問診です。問診では、患者さんが感じている肩の痛みや動かしにくさが、どのような状況で始まり、どのように変化してきたかを詳しく確認します。
たとえば、「いつごろから肩が痛くなったのか」「特定の動きで痛みが強くなるのか」「夜間にも痛みがあるか」「肩を動かしたときにどの程度まで腕が上がるか」「過去に肩をけがしたことがあるか」などを尋ねます。また、日常生活や仕事で肩に負担のかかる動作をしていないか、他の病気(糖尿病や甲状腺疾患など)がないかどうかも確認します。
問診で得られた情報は、他の肩の疾患(たとえば腱板断裂や石灰沈着性腱炎など)との見分けをつけるための重要な手がかりとなります。さらに、リウマチ性疾患や頚椎の病気による肩の痛みといった別の可能性も視野に入れて、総合的に判断していくため、患者さんが自分の症状について正確に伝えることが診断の精度を高めるうえでとても大切になります。
視診
視診とは、医師が肩の見た目や動き方を直接観察することで、異常の有無を確認する診察の方法です。
視診ではまず、肩の左右差や腫れ、変形、皮膚の変色、筋肉のやせ(萎縮)がないかを注意深く見ていきます。特に、肩を動かさずにじっとしている状態でも片方の肩がやや下がっている、あるいは力が入りにくいといった変化がある場合には、肩関節周囲の炎症や拘縮が疑われます。
また、患者さんに腕を上げたり後ろに回したりといった基本的な動作をしてもらい、そのときの動きのスムーズさや動作の範囲、痛みが出る位置などを確認します。五十肩の場合、ある角度を超えると急に動きが止まる「運動制限」が特徴的に見られることが多く、これも視診の中で重要なポイントとなります。
視診だけで確定診断に至るわけではありませんが、関節の状態や動作の特徴から他の病気との違いを見分ける手がかりが得られるため、診断において欠かせないステップのひとつです。
画像所見
問診と視診のあとは、次のような検査をおこないます。
- レントゲン検査
- MRI検査
- 関節造影検査
- 超音波検査
上記の検査により、五十肩以外の疾患の可能性を除外し、最終的な診断をおこないます。
次項からは、それぞれの検査について詳しく解説します。
レントゲン検査
必要に応じてレントゲン検査(X線検査)が行われます。ただし、五十肩そのものはレントゲンに直接は写りません。関節の炎症や癒着といった変化はX線では映らないため、レントゲンの目的は「ほかの病気が原因ではないかどうかを調べること」にあります。
たとえば、肩の痛みや動かしにくさは、腱板断裂や石灰沈着性腱炎、変形性関節症、関節内の骨折、腫瘍などでも起こる可能性があります。これらの病気はレントゲンで確認できることがあるため、まずはそれらを除外するために撮影が行われます。
実際のレントゲン画像では、肩関節の隙間の広さや骨の形、石灰の沈着の有無、骨の変形の程度などがチェックされます。五十肩と診断された場合は、レントゲン上には特に大きな異常が見られないことがほとんどです。つまり、他に明らかな異常がなく、症状と身体所見から五十肩と診断される、という流れになります。
したがって、レントゲン検査は五十肩の「診断を確定するため」というより、「似たような症状を起こす他の疾患を見逃さないため」に重要な役割を果たします。
MRI検査
MRI検査は必要に応じて行われる精密検査のひとつです。レントゲン検査では骨の状態しかわかりませんが、MRIは筋肉や腱、靱帯、関節包、滑液包といった軟部組織を詳しく映し出すことができるため、より詳しい診断に役立ちます。
五十肩そのものは、画像で明確に写るわけではありませんが、MRIを行うことで、腱板断裂や石灰沈着性腱炎、腫瘍、関節リウマチ、滑液包炎など、ほかの病気との区別ができるようになります。これらの疾患は症状が似ていても治療方針が大きく異なるため、正確な診断のためにはMRIが有効です。
また、五十肩が進行して関節包が厚くなっていたり、肩峰下滑液包の炎症や癒着が見られたりする場合には、MRIでその様子が確認できることがあります。とくに痛みが強い、症状が長引いている、リハビリで改善が見られないといったケースでは、MRI検査によって診断の確実性が高まります。
つまり、MRI検査は五十肩の診断を補助し、他の病気の可能性を除外したうえで、より適切な治療につなげるための重要な手段となります。必要かどうかは症状の経過や他の検査結果をふまえて、医師が判断します。
関節造影検査
五十肩(肩関節周囲炎)の診断や治療方針を決めるうえで、関節造影検査が行われることがあります。これは、関節の中に造影剤と少量の麻酔薬を注入して、関節包の広がりや状態を詳しく調べる検査です。
関節造影検査では、関節包の癒着や収縮の程度を確認できます。とくに五十肩が進行して関節の動きが大きく制限されている場合、関節包が硬くなっていたり、内部で癒着していることがあり、それが画像に映し出されることで診断の精度が上がります。レントゲンやMRIではわかりにくい細かい変化が、関節造影によってはっきりとわかることもあります。
また、関節造影は検査であると同時に、治療の一環としても使われることがあります。たとえば、「関節授動術」という治療では、造影剤と麻酔薬を注入しながら関節をゆっくり動かして、癒着を剥がすように可動域を広げていく方法が取られることもあります。これによって肩の動きが少しずつ改善することが期待されます。
ただし、関節造影検査はすべての五十肩に必要なわけではなく、症状が強い場合や、通常のリハビリでは改善が見られないケースなどに限られることが多いです。検査を行うかどうかは、医師と相談しながら決めていくことになります。
超音波検査
超音波検査(エコー検査)は非常に役立つ方法のひとつです。肩の内部の状態をリアルタイムで確認できるため、痛みの原因や炎症の程度を把握するうえで効果的です。
この検査では、肩の腱や筋肉、滑液包といった軟部組織の状態を詳しく見ることができます。特に腱板(けんばん)と呼ばれる肩のインナーマッスルや、その周辺の腱の断裂、炎症、石灰の沈着などが疑われる場合に有効です。また、検査中に腕を実際に動かしてみることで、動作時にどの部分が引っかかったり痛みを引き起こしているかも確認できます。
超音波検査は体への負担が少なく、放射線を使わないため安全性が高いのも特徴です。レントゲンでは映らない筋肉や腱の異常を把握でき、MRIよりも手軽に行えるため、外来診察でもよく使われます。
ただし、肩関節の奥深くにある構造まで詳しく見るにはMRIの方が適していることもあり、必要に応じて検査が使い分けられます。まず超音波で確認し、それでも原因がはっきりしない場合に他の検査を追加する、という流れが一般的です。
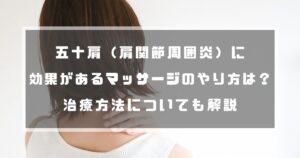
五十肩(肩関節周囲炎)の治療方法

五十肩(肩関節周囲炎)の治療方法は次のとおりです。
- 安静
- 薬物療法
- リハビリテーション
- 体外衝撃波治療
- 再生療法
- 手術療法
症状の進行具合によって適切な治療法は異なります。
それぞれの治療法を詳しく解説するので、自身の症状に合った方法をチェックしてみてください。
安静
五十肩の初期には、無理に肩を動かさず安静に保つことが重要です。特に痛みが強い時期には、日常生活の中でも肩に負担をかけないよう工夫しながら過ごします。ただし、安静にしすぎると関節の動きが悪くなる可能性もあるため、医師の指示に従いながらバランスの取れた過ごし方を心がけます。
薬物療法
痛みを和らげるために、消炎鎮痛剤(内服薬や湿布薬など)が使われます。痛みがひどい場合には、局所麻酔薬やステロイド剤の注射が行われることもあります。薬によって炎症を抑えることで、動かすときの不快感が軽減し、リハビリにも取り組みやすくなります。
内服
痛みの軽減を目的として内服薬が使われることがあります。主に使用されるのは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる薬で、炎症を抑えながら痛みを和らげる作用があります。これにより、日常生活の動作がしやすくなったり、夜間の痛みが軽減されて睡眠の質が向上したりすることが期待できます。内服薬は、比較的手軽に取り入れられる方法ですが、長期間の服用によって胃腸に負担がかかることもあるため、医師の指導のもとで適切に使うことが大切です。症状の強さや体質によっては、胃薬と一緒に処方されることもあります。
注射
痛みが強い場合や内服薬だけでは効果が不十分な場合に、注射による治療が行われることがあります。よく用いられるのは、ステロイド薬を関節内やその周辺に直接注射する方法です。炎症を速やかに抑える効果が期待でき、特に夜間の強い痛みや動作時の鋭い痛みがある場合に有効とされています。
また、ヒアルロン酸の注射が行われることもあり、こちらは関節の滑りを良くしたり、動きをなめらかにしたりする効果があります。注射は短期間で痛みを和らげる手段として用いられますが、何度も繰り返すと副作用のリスクもあるため、治療の頻度や回数については医師と相談しながら進める必要があります。
リハビリテーション
可動域を広げたり、肩の機能を回復させたりするためにリハビリが行われます。初期は痛みの出ない範囲で軽く肩を動かすところから始め、少しずつ可動域を広げていきます。理学療法士による指導のもとでストレッチや運動療法を継続することが、回復への近道になります。
体外衝撃波治療
比較的新しい治療法で、衝撃波を患部に当てて血流を促し、炎症の改善や痛みの緩和を目指します。主に慢性的な痛みが続く場合に用いられ、薬やリハビリで効果が乏しいときに選択されることがあります。侵襲が少なく外来でも受けられるのが特徴です。
再生療法
自己由来の血液や細胞を利用して修復を促す治療法で、PRP(多血小板血漿)注射などが含まれます。患部に直接注射することで組織の再生を促進し、痛みや炎症の改善を期待します。従来の治療で十分な効果が得られなかった場合に選ばれることがあります。
手術療法
保存的な治療で症状が改善しない場合や、拘縮が進んで関節の動きが著しく制限されている場合に手術が検討されます。関節鏡を用いた癒着の除去や、関節包の切開などが行われます。術後は再び可動域を取り戻すためのリハビリが必要です。
五十肩は多くの場合、時間の経過とともに自然に回復することもありますが、症状や生活の質に応じた適切な治療を受けることが大切です。
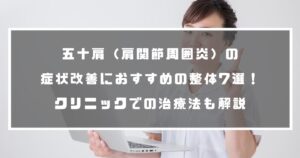
肩の治療ならシン・整形外科

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- パーソナライズされた治療ケア
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科の肩の治療は、以下の理由からおすすめです。
- 専門的な肩の治療
- 最新の医療技術
- 個別の治療プラン
- 安心の手術
- パーソナライズされたケア
専門的な肩の治療
シン整形外科は肩の痛みや問題に特化した専門的な治療を提供しています。経験豊富な専門医が、患者様の症状を正確に評価し、最適な治療法を選択します。肩に関する専門知識を持つ医師陣が、あなたの健康と快適な生活のために全力を尽くします。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
個別の治療プラン
患者様一人ひとりの状態やニーズに合わせて、カスタマイズされた治療プランを提供します。一般的な治療だけでなく、患者様のライフスタイルや目標に合わせて、最適なアドバイスや指導を行います。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていくパートナーとしております。
まとめ

五十肩は、原因がはっきりとしない肩の痛みや可動域の制限がある状態の俗語で、主に50代に多くみられます。
痛みのある炎症期、動かしにくくなる拘縮期、徐々に症状が改善される回復期の流れで症状が変わる点が特徴です。
自然に治癒するケースも少なくありませんが、なかには症状が長期間続き、生活に支障が出る方もいます。
早く改善するためには、クリニックを受診し正しい診断と治療を受けることが大切です。
肩の痛みが続いている方は、ぜひ早めにクリニックを受診してみてください。