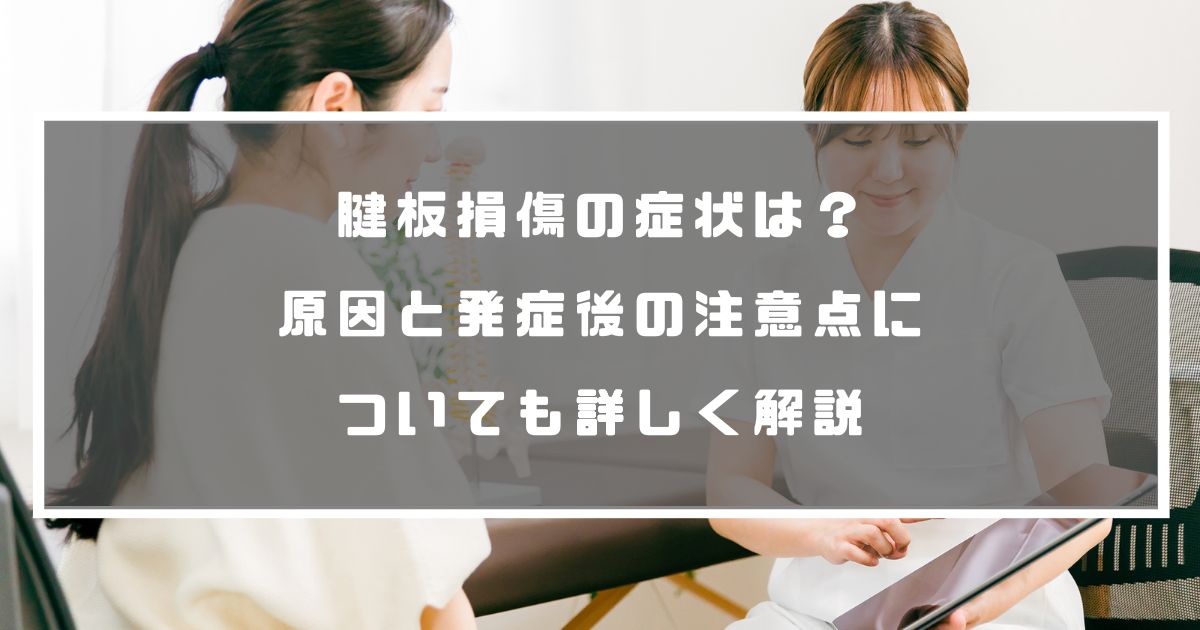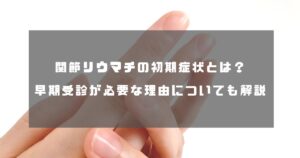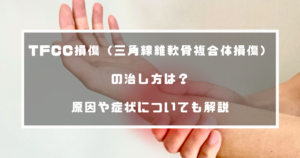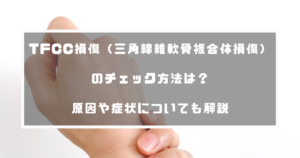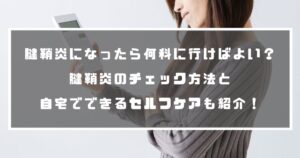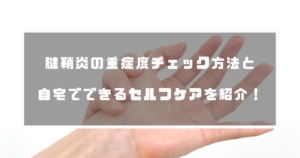「肩が痛くて眠れない」「腕を上げると肩に痛みが走る」など、肩の痛みで悩んでいる方はいませんか。
- 肩の奥が痛む
- 横になると症状が悪化する
- 背中や髪を触る姿勢を取ると痛みを感じる
- 運動すると疲れやすい
上記の症状に当てはまる場合、腱板損傷の疑いがあります。腱板損傷とは、肩のインナーマッスルである腱板筋群のスジを損傷して、痛みや炎症が起こる病気です。
四十肩や五十肩と混同されやすいですが、腱板損傷とは異なる肩の痛みです。
本記事では、腱板損傷(腱板断裂)の症状や原因、注意点などを解説します。肩の痛みで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
腱板損傷(腱板断裂)とは

腱板損傷(腱板断裂)とは、肩の関節を安定させたり動かしたりする役割を担っている「腱板(けんばん)」という筋肉と腱の集まりが傷ついたり、切れてしまったりする状態のことを指します。腱板は、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という4つの筋肉で構成されており、肩の複雑な動きを支えています。
この損傷は、大きく2つの原因によって起こります。1つ目は、加齢や長年の使用による変性です。これは40代以降の人に多く見られ、肩を酷使し続けることで腱の組織がもろくなり、あるとき突然断裂してしまうことがあります。もう1つは外傷によるもので、転倒して肩を強く打ったり、重いものを無理に持ち上げたときなどに、若い人でも損傷が起こる場合があります。
症状としては、肩の痛みが主なもので、特に腕を挙げたときや夜寝ているときに強く感じることがあります。また、腕が上がらない、力が入らない、物を持ちづらいといった運動制限が出ることもあります。損傷が長期間放置された場合、肩の筋肉がやせ細っていく筋萎縮が起こることもあります。
診断には問診や触診に加え、MRIや超音波検査などの画像検査が用いられます。これにより、腱の損傷の有無やその程度を詳しく調べることができます。
治療法には、保存療法と手術療法があります。保存療法では、痛み止めの薬の使用やリハビリテーション、注射(ヒアルロン酸やステロイドなど)によって、症状の緩和を図ります。一方、腱の断裂が大きかったり、保存療法で効果が見られない場合には、断裂した腱を縫合する手術が行われます。最近では、関節鏡という小さなカメラを使った低侵襲の手術が一般的になっています。
腱板損傷は放っておくと症状が進行しやすく、治療も難しくなることがあるため、早めに整形外科を受診して適切な対応をとることが大切です。
腱板損傷の原因や発症しやすい方の特徴

腱板損傷の原因は、加齢に伴う組織の劣化や、肩への過度な負担、外傷などが主に挙げられます。特に多いのは、長年にわたって肩を使い続けた結果として腱が徐々に弱くなり、ある日ふとした動作で断裂に至るというケースです。これを「変性断裂」と呼び、40歳以降に発症しやすいのが特徴です。年齢とともに腱の血流が減少し、弾力性が失われていくことで、わずかな負荷でも損傷しやすくなります。
一方で、転倒や肩を強くぶつけたことによって腱板が急に切れてしまう「外傷性断裂」もあります。これはスポーツや交通事故、重い物を無理に持ち上げたときなどに起こることが多く、比較的若い人でも見られることがあります。
腱板損傷を発症しやすい人にはいくつかの共通した特徴があります。まず、日常的に肩を酷使する仕事やスポーツをしている人、たとえば大工や塗装業、荷物の積み下ろし作業が多い職業の人、あるいは野球やテニス、水泳など腕を大きく動かすスポーツを行っている人はリスクが高くなります。また、過去に肩の痛みを我慢しながら使い続けていたような人も注意が必要です。
さらに、加齢以外にも喫煙習慣や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病を持っている人は腱の血流が悪化しやすいため、腱板の損傷リスクが高まるとされています。このように、腱板損傷は単なる肩の使いすぎだけでなく、年齢や生活習慣、職業などが複雑に絡み合って起こるため、予防のためには日頃から肩に過度な負担をかけないよう意識することが大切です。
腱板損傷の主な症状

腱板損傷による痛みには、軽度なものと重度なものがあります。多くの場合は症状が軽いため、気が付かないまま過ごしている方もいるほどです。
しかし、悪化すると手術が必要になるケースもあります。不自然な肩の痛みを感じた場合は、早めに医師の診察を受けましょう。
ここでは腱板損傷の主な症状をまとめました。自身の肩の痛みと照らし合わせて、腱板損傷の疑いがないかチェックしてみてください。
肩の奥の痛み
腱板が損傷すると、肩の深い部分に鈍く響くような痛みを感じることがあります。特に腕を動かしたときや、肩に力を入れたときに痛みが増す傾向があります。これは、断裂や炎症によって関節周囲の組織が刺激されているために起こるもので、「表面が痛い」というより「関節の奥が重だるく痛い」と感じる人が多いのが特徴です。
寝ている際の肩の痛み
腱板損傷では、夜間に肩の痛みが強くなることがあります。特に痛みのある側を下にして寝たときに圧迫がかかり、ズキズキとした痛みで目が覚めることもあります。寝返りを打つたびに痛みが走ったり、仰向けでも肩の内部がうずいて眠れないという人もいます。この「夜間痛」は腱板の炎症や血流の影響と関係していると考えられています。
背中や髪を触る姿勢で痛みを感じる
腕を後ろに回したり、上に伸ばして頭の後ろへ持っていくような動作のときに痛みが出やすいのも、腱板損傷の特徴です。たとえば背中に手を回してブラジャーのホックを外す動作や、髪を束ねるような動作で「痛くて腕が上がらない」「引っかかるような感じがする」といった訴えがよく見られます。これは、損傷した腱が関節の動きをスムーズに保てず、炎症や引っかかりを起こしているためです。
運動をすると疲れやすい
腱板が損傷していると、肩の安定性が低下し、少しの動作でも周囲の筋肉に余計な負担がかかります。そのため、長く腕を使った作業を続けると、普段よりも早く肩が疲れてしまったり、だるさを感じたりします。特に荷物を持ったり、高い位置で作業を続けるとすぐに肩が重くなる、腕が上がらなくなるというような状態になります。これは筋力の低下というより、肩を支えるバランスが崩れていることによる「機能的な疲労」です。
腱板損傷の症状のうち日常生活で不便なこと

腱板損傷になると、日常生活で不便なことが多くあります。たとえば、シャンプーや髪を乾かす際にも痛みを感じるなどです。
エプロンの紐を腰付近で結ぶ際にも、肩に痛みが走る可能性があります。無理をすると症状が悪化するケースもあるため、腱板損傷の方は日常生活の動作にも気を配ることが大切です。
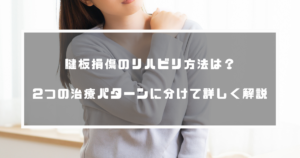
腱板損傷の症状が出たあとの注意点

腱板損傷と診断された場合、肩周囲を安静にした方がよいため、腕の動きそのものを最小限にするよう注意が必要です。
そこで、腱板損傷の症状が出たあとの注意点をまとめました。まだ医師の診断を受けていなくても、可能性があるのなら下記の注意点をチェックしましょう。
頭の上で重い物を持たない
腕を頭の高さ以上に上げた状態で重い物を持ち上げると、損傷した腱板に強いストレスがかかります。この動作では肩の深部にある腱が引っ張られたり、関節の中で擦れるような状態になりやすく、炎症が悪化する原因になります。洗濯物を高いところに干す、棚の上に物を収納するなどの日常の作業にも注意が必要です。
上半身の力で物を持たない
肩や腕に力を入れて物を持ち上げるとき、腱板がしっかり働いていないと肩関節が不安定になり、他の筋肉が無理に補おうとして負担が偏ります。とくに肩に負荷が集中しやすい中腰での持ち上げや、腕だけで支える持ち方は避けるようにしましょう。重い荷物はなるべく両手で体の近くに引き寄せて持ち、脚の力も使って全身で支えることが大切です。
首の後ろで腕を動かさない
髪を結ぶ、服のタグを取る、手を首の後ろに回すといった動作は、肩関節を大きくひねる必要があるため、腱板に強い圧力やねじれが加わります。このような姿勢では腱が骨に挟まりやすくなり、損傷が悪化する可能性があります。無理に腕を動かそうとせず、痛みを感じる動きはできるだけ控えるようにしましょう。
腱板損傷の治療法

腱板損傷の治療法には、大きく分けて保存療法と手術療法の2つがあります。基本的に腱板損傷は自然治癒しないため、早めに医師の診断を受けて適切な処置をおこなうことが大切です。
ここでは、腱板損傷の治療法についてまとめました。どのような治療法があるか気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
保存療法
保存療法とは、手術をせずに痛みの緩和や機能回復を目指す治療法です。腱の損傷が軽度であったり、高齢で手術のリスクが高い場合、また日常生活に大きな支障がない場合には、この方法が選ばれます。主な内容としては、痛みを和らげるための薬の内服、ステロイドやヒアルロン酸の関節内注射、そして肩の可動域を改善し筋力を保つためのリハビリテーションがあります。痛みを避けながら動かせる範囲で肩を動かすことで、拘縮(かたまって動かなくなる状態)を防ぎます。ただし、断裂した腱自体が自然に元通りにくっつくことはないため、あくまで「痛みと機能のコントロール」が目的となります。
手術療法
保存療法で十分な効果が得られなかった場合や、損傷が大きく日常生活に支障が出ている場合には、手術療法が検討されます。手術では断裂した腱を縫い合わせ、肩の機能を回復させることを目指します。最近では関節鏡という細いカメラと器具を使って行う「関節鏡視下手術」が主流で、傷口が小さく、回復も比較的早いとされています。完全断裂している場合でも、早期に手術を行うことで肩の筋力や可動域を取り戻せる可能性があります。手術後は一定期間の安静とリハビリが必要で、肩の回復には数か月かかるのが一般的です。
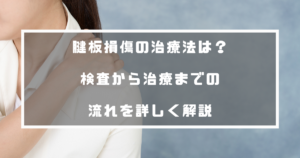
腱板損傷を予防するエクササイズ

腱板損傷を予防するためには、肩の柔軟性を保ちながら、腱板を支える筋肉を鍛えることが大切です。特に、肩の安定性を保つ役割を持つ「棘上筋」「棘下筋」「小円筋」「肩甲下筋」といった筋肉を日常的にケアしておくことで、加齢や使いすぎによる損傷を防ぎやすくなります。ここでは、腱板損傷の予防に効果的なエクササイズをいくつか紹介します。
まず取り入れたいのが「ペンデュラム運動(振り子運動)」です。これは肩関節周囲をやさしく動かして血流を促す運動で、リハビリ初期にもよく行われます。前かがみになり、片手で椅子やテーブルに体を支えながら、もう一方の腕を力を抜いて垂らし、前後左右や円を描くようにゆっくり揺らします。1回30秒から1分ほど行えば十分で、肩に負担をかけずに可動域を保つことができます。
次におすすめなのが、チューブ(セラバンド)を使った「外旋運動」です。この動きは棘下筋や小円筋を鍛えるのに有効で、腱板全体の安定性を保つために重要です。チューブを固定し、肘を90度に曲げた状態で体の横につけたまま、手を外側に引くようにゆっくり動かします。力を抜いて元の位置に戻すときもゆっくり行うことがポイントで、左右それぞれ10〜15回を1セットとし、無理のない範囲で数セット行うとよいでしょう。
また、外旋とバランスを取るために「内旋運動」も大切です。これは肩甲下筋を鍛える目的で、外旋と同様にチューブを使って行います。今度は腕を体の外側から内側に引き寄せるように動かし、同じく10〜15回を目安に行います。これにより、肩の内外の筋力バランスが保たれ、過度な負担が特定の筋肉に偏るのを防げます。
さらに、肩甲骨周囲のストレッチも取り入れることで、肩全体の動きが滑らかになり、腱板への負担を軽減できます。肩を大きく回したり、肩甲骨を寄せるような動作をこまめに行うと、血行が促進され、筋肉の柔軟性も高まります。特にデスクワークなどで肩周囲がこわばりやすい人は、合間に簡単なストレッチを取り入れることが予防につながります。
腱板損傷の症状についてよくある質問

腱板損傷の症状についてよくある質問をまとめました。腱板損傷は年配の男性に多い症状ですが、スポーツや肉体労働をする方なら若くても発症する可能性があります。
そのため肩に慢性的な痛みを感じる方は、腱板損傷である可能性も考えてみましょう。
腱板損傷の痛みを緩和する運動はある?
軽いエクササイズで腱板損傷の痛みが緩和する可能性はあります。本記事でも、腱板損傷に効果的なエクササイズを紹介しています。
腱板損傷の痛みを完全に取り除くことはできないものの、症状を緩和する効果が期待できます。ただし、痛みがつらく腕を動かすのも難しい方は、病院で保存療法の処置を受けるようにしましょう。
腱板損傷なのかセルフチェックできる?
腱板損傷なのか簡単にセルフチェックする方法はあります。
- 両腕を肩の高さに上げる
- 1分間腕を水平に保つ
腕が下がり水平に保てない方は、腱板損傷の疑いがあります。また肩に痛みが出る場合も腱板断裂の可能性があるため、医師の診断を受けるようにしましょう。
腱板損傷と五十肩の違いは?
腱板損傷と五十肩の違いは次のとおりです。
- 五十肩ははっきりした原因はわかっていないが、腱板損傷は外傷や肩を酷使した場合など原因がある
- 五十肩は肩が固くることがあるが、腱板断裂は力が入りにくくなる症状がある
しかし、腱板損傷でも原因が明確でないうちに症状がでるケースがあったり、腱板部分に損傷があると肩が固くなったりする場合もあります。
例外が多く、実際のところ症状のみで判断するのは難しい点が現状です。肩の不調の原因や症状を正確に知りたいのなら、医師の診断を受けるほうがよいでしょう。
腱板損傷の症状は自然治癒する?
腱板損傷は基本的に自然治癒しません。一部のみの小さな損傷だと可能性はゼロではないものの、基本的には悪化して自然に治ることはないでしょう。
そのため、痛みがひどい場合は医師の診察を受け、保存療法または手術療法をおこなう必要があります。
腱板損傷の症状を改善するならシン・整形外科の再生医療がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン・整形外科では、腱板損傷の治療としても注目されている再生医療を専門的に扱うクリニックです。
主に次のような特徴があります。
- 手術なしで治療できる再生医療
- オーダーメイドのリハビリテーション
- 治療効果や健康被害に配慮した保証制度
それぞれの特徴を詳しく解説するため、腱板損傷による痛みを改善したい方は、ぜひチェックしてみてください。
手術なしで治療できる再生医療
再生医療とは、人体の自己再生能力を活かし、損傷した組織を修復する治療法です。
シン・整形外科では、主に次のような幹細胞や血液を患者から採取し、加工して患部に注入する再生医療を採用しています。
- 幹細胞培養治療
- PRP-PRO治療
- PRP-FD治療
上記の再生医療は腱板損傷の治療にも用いられており、日帰りで受けられます。
損傷した腱板の修復や痛みの軽減が期待できるうえ、体への負担も少ないため、症状が進行しているものの手術には抵抗がある方にも適しています。
治療の提案は整形外科の専門医がおこなうため、再生医療に関する不安や疑問は気軽に相談してみてください。
オーダーメイドのリハビリテーション
シン・整形外科には、再生医療の効果を最大化させるオーダーメイドのリハビリテーションも提供しています。
患者一人一人の症状に合ったリハビリテーションメニューを、医学療法士が提案し、マンツーマンで指導します。
また、自宅でできる運動のアドバイスもおこない、再生医療による修復を促しつつ、痛みが再発しない体づくりが可能です。
腱板損傷を治療したい方は、ぜひ検討してみてください。
治療効果や健康被害に配慮した保証制度
シン・整形外科には、治療効果や健康被害に配慮した次の2つの保証制度を用意しています。
1つ目は、幹細胞培養治療を2回以上と、リハビリスタンダードコースを6か月以上継続しても治療効果が得られなかった場合に適用される再治療保証です。
上記に該当する場合、無料の追加治療(1回)が初回治療から1年間保証されます。
2つ目のリスク保証は、再生医療を受けて健康を害した場合に、再生医療サポート保険を利用できる保証です。
患者が安心して治療を受けられる制度が設けられているため、再生医療をはじめて受ける方も検討しやすいでしょう。
まとめ

腱板損傷(腱板断裂)とは、肩のインナーマッスルである4種類の腱板筋群のスジが損傷したり、切れたりした状態のことです。
加齢によって腱板を構成しているコラーゲンがもろくなり、古い輪ゴムのような状態になって起こるケースもあれば、外傷や肩を酷使した結果なる場合もあります。
横になるのみでも痛みを伴う場合があるため、症状が悪化すると日常生活に支障が出るでしょう。
腱板損傷は、一度なると自然治癒は期待できません。そのため、病院の薬で対処する保存療法、もしくは外科的処置をおこなう手術療法を受けることになります。
腱板損傷は命にかかわる症状ではないものの、症状が悪化するケースもあることから、痛みがひどい場合は早めに医師に相談しましょう。