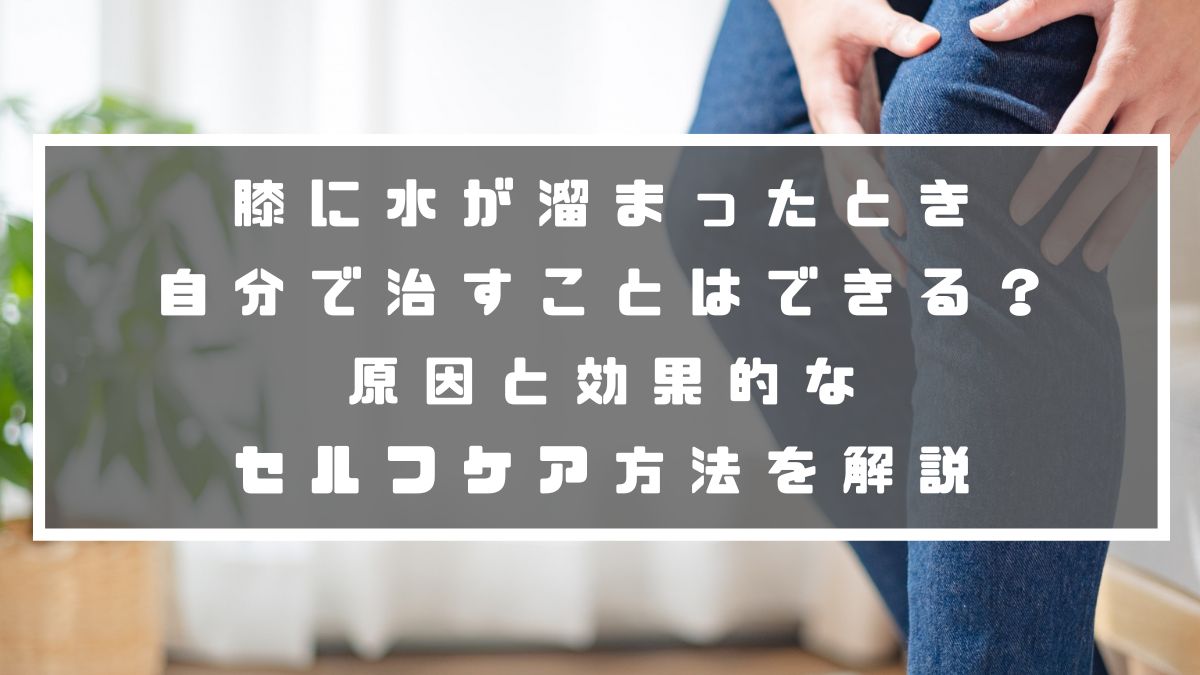膝に水が溜まることは変形性膝関節症や半月板損傷など膝の疾患が原因となり、膝関節内に炎症ができて水が過剰に分泌されるためです。
溜まった水は放置しても基本的には改善しませんが、安静にして冷やすことで炎症がおさまり水が吸収されるケースもあり、軽度であればセルフケアでの改善が可能です。
大量に水が溜まっている場合は、整形外科や膝関節専門のクリニックで一度抜いてもらうことで水が溜まる原因がわかります。
ここでは水が溜まる原因と自宅で簡単にできるセルフケアについて紹介します。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
【結論】膝に溜まった水を自分で治すことはできる?

膝に溜まった水を自分で完全に治すことは難しいですが、軽度の症状であれば自宅での対処によって改善する可能性があります。まず大切なのは膝を無理に動かさず、安静にすることです。歩行や運動を控え、膝に負担がかからないように心がけましょう。また、炎症を抑える目的でアイシングを行うのも効果的です。氷や保冷剤をタオルに包んで、1回15〜20分を目安に冷やします。さらに、膝を包帯やサポーターで軽く圧迫したり、心臓より高い位置に足を上げたりすることで腫れが引きやすくなります。
痛みが強い場合には、市販の消炎鎮痛薬を使用してもかまいません。ただし、症状が数日以上続く場合や、膝が熱を持っていたり歩くのが困難なほどの痛みがある場合には、医療機関を受診する必要があります。特に、膝をひねったりぶつけたりしたあとに水が溜まっているようなケースでは、骨や軟骨、半月板などの損傷が隠れている可能性もあります。
病院では、水を抜いて関節内の状態を調べたり、炎症を抑える注射を行ったりするほか、原因となる病気の治療が行われます。膝に水が溜まるというのはあくまでも結果であり、背景には変形性膝関節症や半月板損傷といった疾患があることが多いため、根本的な原因を突き止めて治療を行うことが重要です。
そもそも膝に水が溜まるとは?

膝関節を包み込む関節包のなかには、膝に溜まる関節液である滑液が滑膜で閉じられています。
滑液は膝関節の軟骨が擦れずスムーズに曲げ伸ばす潤滑油のような役割があり、この滑液が膝に溜まる水の正体です。
通常滑膜内には適切な量の滑液が生成されて排出されますが、膝に水が溜まっているのは変形性膝関節症や半月板損傷などの疾患が原因となり、関節液を過剰に分泌している状態だからです。
滑膜の炎症で関節液が増えた状態
膝関節の内側には「滑膜(かつまく)」という薄い膜が張り巡らされており、ここから関節液が分泌されています。関節液は関節の動きを滑らかにし、軟骨に栄養を届ける働きを持っています。
しかし、滑膜が炎症を起こすと、その防御反応として関節液を過剰に分泌するようになります。これは「膝を守ろうとする反応」ですが、分泌が過剰になると関節の中に液体が溜まりすぎてしまい、腫れや圧迫感、熱感、痛みなどの症状が出てきます。炎症の原因としては、変形性膝関節症や関節リウマチ、半月板損傷、打撲やねじれなどの外傷、感染などがあります。中でも変形性膝関節症は高齢者に多く、慢性的な滑膜炎が水の繰り返し発生につながることが多いです。
滑膜が鈍くなると水が溜まる
通常、滑膜には関節液を分泌するだけでなく、必要のなくなった関節液を体内に再吸収する機能も備わっています。ところが、この吸収機能が加齢や病気、慢性的な炎症によって弱まってしまうと、分泌された関節液が関節内に残ったままになり、やがて水が溜まってしまいます。
つまり、関節液が増えすぎるわけではなく、吸収されずに残ってしまうという仕組みです。特に、長年にわたって膝関節に負担がかかってきた場合や、変形性膝関節症が進行して滑膜が厚くなり機能が低下したときなどに、このタイプの水が溜まりやすくなります。痛みがそれほど強くない場合でも、膝の腫れや重さ、曲げ伸ばしの違和感が出ることがあります。
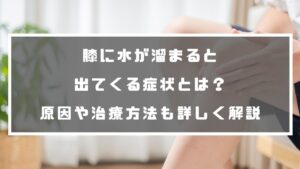
膝に水が溜まる原因

膝に水が溜まる原因は、主に膝にかかる疾患です。代表的なのは変形性膝関節症によるもので、多くの方が悩まされている疾患でもあります。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、加齢や長年の負担により膝関節の軟骨が徐々にすり減り、関節の構造が変化してしまう病気です。軟骨は本来、骨と骨の間でクッションの役割を果たし、関節の動きを滑らかにしていますが、年齢や過体重、過度な使用、外傷などの影響で摩耗してしまいます。軟骨がすり減ると、関節の隙間が狭くなり、骨同士が直接こすれ合うようになります。その刺激が滑膜に伝わり、炎症が起こって関節液が過剰に分泌されることで、水が溜まる状態になります。初期は膝のこわばりや立ち上がるときの痛みといった軽い症状から始まりますが、進行すると膝全体の腫れや変形、歩行困難、階段昇降の困難など、日常生活に大きな支障をきたすようになります。水が何度も溜まる場合は、病気が進行しているサインであることが多く、早期の診断と治療が重要です。

半月板損傷
半月板は、膝関節の中で太ももの骨とすねの骨の間にある軟骨組織で、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。この半月板が裂けたり傷ついたりすることを「半月板損傷」と言い、スポーツ中の急な方向転換やジャンプ着地時の衝撃、または加齢による摩耗などが原因で起こります。半月板が損傷すると、その周囲にある滑膜が刺激を受けて炎症を起こし、関節液が多く分泌されるようになります。その結果、膝に水が溜まって腫れや痛みが出てくるのです。特に損傷の初期には膝が引っかかるような感覚や、動かしにくさ、あるいは「ガクッ」と外れるような不安定感が生じることもあります。高齢者の場合は、特にきっかけがなくても、日常の動作で半月板が自然に傷つくことがあります。損傷の程度によっては保存療法で様子を見ることもありますが、大きく裂けている場合は手術が必要になることもあります。

関節リウマチ
関節リウマチは、自己免疫の異常により自分の体の免疫が誤って関節を攻撃してしまう病気です。特に滑膜が標的となって炎症が起こり、慢性的に関節液が過剰に分泌されるようになります。膝関節が腫れて水が溜まるのはその結果であり、リウマチの進行とともに症状が強くなります。通常、朝の関節のこわばりや、左右対称の関節の腫れといった症状が特徴的で、膝だけでなく指や手首、足の関節など複数の部位に痛みや腫れが出るのもこの病気の特徴です。膝に水が溜まっている場合、それは滑膜の炎症が活発である証拠であり、早めの対応が求められます。関節リウマチを放置すると、関節が変形し、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。最近では治療薬が進歩しており、早期発見・早期治療によって進行を抑えることが可能になっています。膝の水が繰り返し溜まる、かつ他の関節にも症状がある場合は、リウマチ専門医の受診を検討する必要があります。
靭帯損傷
膝関節には、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯といった複数の靭帯があり、これらは関節の安定性を保つために非常に重要な役割を果たしています。スポーツ中の急な方向転換、ジャンプの着地、交通事故、転倒などによってこれらの靭帯が部分的に伸びたり、断裂したりすると、関節内に炎症が起きて関節液が増加します。特に損傷直後は、関節液の中に出血が混ざって水が濁って見えることもあります。膝の強い腫れ、内出血、動かすときの痛み、不安定感が見られることが多く、靭帯損傷は比較的急激な症状として現れます。水が溜まっている場合には、単なる炎症に加えて、関節の中に損傷がある可能性が高いため、医師による診断と画像検査(MRIなど)が必要です。靭帯損傷は程度によって治療法が異なり、軽度であれば装具やリハビリによる保存療法が可能ですが、断裂している場合には手術が必要になるケースもあります。
膝に水が溜まりやすい方の特徴

膝に水が溜まりやすい方には次のような特徴があります。
持病がある方以外は膝に負担のかかる生活をしていることが共通の特徴であるため、水が溜まりやすい方はできることから一つずつ改善していきましょう。
体重の増加が激しい
急激な体重増加は膝関節に大きな負担をかけます。膝は歩くたびに体重の3〜5倍の負荷を受けており、体重が重くなるとその負担はさらに増加します。とくに太ももやふくらはぎの筋力が追いつかないまま体重だけが増えると、関節を保護する力が不足し、膝の軟骨や滑膜にダメージが蓄積されやすくなります。その結果、滑膜が炎症を起こして関節液が過剰に分泌され、水が溜まりやすくなります。肥満が進行すると、変形性膝関節症のリスクも高まります。
加齢
年齢を重ねるとともに、関節軟骨や靭帯、筋肉、滑膜の機能は徐々に低下していきます。特に50歳を過ぎた頃から、膝の軟骨は少しずつすり減り、衝撃吸収機能が弱くなってきます。その状態で長年使い続けると、滑膜が刺激を受けて炎症を起こしやすくなり、水が溜まる原因になります。高齢になると自然治癒力も低下するため、一度水が溜まると長引きやすく、再発もしやすい傾向にあります。年齢とともに膝の不調が気になる方は、日常的に関節をいたわる習慣が大切です。
膝に負担をかけるようなスポーツをしている
バスケットボール、サッカー、テニス、マラソンなど、膝を酷使する動きが多いスポーツでは、膝関節への負荷が繰り返しかかります。ジャンプや急な方向転換、膝のねじれ動作は、半月板や靭帯、軟骨にダメージを与える原因になります。軽い痛みや違和感を無視して運動を続けていると、やがて滑膜に炎症が起き、水が溜まりやすい状態になります。若い人でも、スポーツ中に膝を痛めた経験がある場合は注意が必要です。また、筋力バランスが崩れていると負担が一点に集中しやすく、水の再発を招くこともあります。
関節リウマチや痛風を患っている
関節リウマチは自己免疫の異常によって滑膜に慢性的な炎症が起こる疾患であり、その結果として関節液が過剰に分泌され、水が繰り返し溜まることがあります。痛風は尿酸が関節内に結晶として沈着し、急激な炎症と激痛を引き起こす病気で、膝に発作が起こると関節内が腫れ、水が溜まることがあります。これらの病気を持っている人は、通常よりも滑膜が炎症を起こしやすいため、ちょっとした刺激でも関節液が増えやすい体質になっていると言えます。病気のコントロールが不十分な場合、膝だけでなく他の関節にも水が溜まりやすくなる傾向があります。
膝に水が溜まったときの初期症状

膝に水が溜まると違和感や痛み、腫れが出ます。初期症状の状態では日常生活に支障がないものの、悪化させないためには検査と早期治療が必要です。
もし水が溜まっていると思ったら、違和感や腫れが何日前から起こっているかメモしつつ、早めの受診を心がけましょう。
膝全体が腫れぼったい
見た目にはっきりと膨らんでいるわけではなくても、触ったときにふくらみを感じたり、ズボンがきつくなったように感じたりすることがあります。膝のお皿の周りが柔らかくブヨブヨとした感触になることもあり、これは関節内に余分な水が溜まっているサインです。炎症によって関節液が少しずつ増えるため、急激な変化ではなく、じわじわと腫れぼったさが増していくのが特徴です。
曲げ伸ばししにくい
水が溜まると関節の中の圧力が高まり、膝の動きがスムーズにいかなくなります。膝を深く曲げたり、まっすぐに伸ばしたりする動作に制限が出てきて、正座や階段の昇り降りがしづらくなることもあります。膝が引っかかるような感覚や、突っ張る感じが出ることもあり、動かすのが億劫になることで症状が悪化しやすくなります。
歩いたときに膝に違和感がある
膝に水が溜まり始めると、関節の中に余分な液体が存在するため、歩行時に膝が重く感じられたり、不安定に感じたりします。わずかな段差や傾斜でも違和感を覚えるようになり、「普段と何か違う」と感じるようになります。痛みがまだ出ていない場合でも、この違和感が初期のサインであることが多く、気づかないまま運動を続けると、悪化して強い腫れや痛みにつながる可能性があります。
膝に水が溜まった際のセルフケア
 自身で水を抜くことはできませんが、炎症をおさえる方法には自宅でできるいくつかのセルフケアがあります。
自身で水を抜くことはできませんが、炎症をおさえる方法には自宅でできるいくつかのセルフケアがあります。
また初期症状の場合はセルフケアでの改善も期待できますが、膝の状態を検査して原因を知ることが適切な治療です。
受診するほどではないけれど違和感が気になる方は、まずはセルフケアとして手軽にできることから挑戦してみましょう。
患部を冷やす
膝が腫れて熱を持っていると感じるときは、まず冷却が大切です。氷や冷却パックをタオルに包んで、膝に当てて冷やしましょう。1回15~20分を目安に、1日数回行うと炎症や腫れを抑える効果が期待できます。冷やしすぎると逆効果になることもあるため、適度に行うよう注意が必要です。
ストレッチを実施する
膝関節まわりの筋肉を柔らかく保つことで、関節にかかる負担を軽減できます。特に太ももの裏(ハムストリングス)やふくらはぎのストレッチは、膝の動きをスムーズにするうえで有効です。痛みが出ない範囲でゆっくりと、反動をつけずに行うことがポイントです。
大腿四頭筋を鍛える
太ももの前面にある大腿四頭筋は、膝を支える重要な筋肉です。この筋肉を鍛えることで、膝関節への負担が減り、水が溜まりにくい状態を作ることができます。たとえば、椅子に座ったまま足を伸ばす「膝伸ばし運動」など、負担が少ない筋トレから始めるとよいでしょう。
サポーターを着ける
歩くときの衝撃や膝のぐらつきを抑えるために、サポーターの使用が効果的です。特に外出時や長時間の歩行の際にサポーターを着けると、膝の安定性が増し、痛みや違和感の軽減につながります。サイズが合っていないと逆に負担になることがあるため、適切なタイプを選ぶことが大切です。
膝の負担がかかる運動を避ける
ジャンプ・ランニング・しゃがみ込み動作など、膝に強い負担をかける運動は、炎症を悪化させるおそれがあります。症状がある間はできるだけ安静を保ち、日常生活でも階段の使用を減らす、長時間の歩行を控えるなどの工夫が必要です。安静にしながら、痛みが落ち着いたら徐々に軽い運動に切り替えましょう。
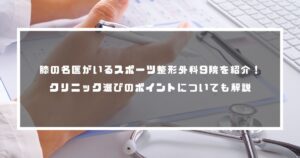
膝の水が悪化している症状

膝の水が大量に溜まると、最初は軽かった違和感や痛みが強くなり、思ったように膝の曲げ伸ばしができなくなります。
次のような症状が出ている方は、早めに整形外科や膝関節専門のクリニックへ受診しましょう。
膝を曲げられない
本来滑液は1mL~3mL程度が正常の量ですが、大量に溜まると30mL以上になることもあります。
水が溜まりすぎるて膝が曲げ伸ばしできない状況は、日常生活に支障が出るほど悪化している状態です。
腫れがおさまることを自然に待つよりも、一度病院で水を抜いて原因を特定しましょう。
正座ができない
初期症状でも膝が腫れて正座に違和感を感じることがあります。
しかし膝が完全に曲がらず正座ができない場合は悪化しているため、早急に治療を進める必要があります。
無理に正座しようとすると膝関節の負担となるため、深く膝を曲げる動作はなるべく避けましょう。
膝に継続的な痛みを感じる
違和感が痛みに変わり、膝を曲げていなくても痛む場合は炎症の悪化が予想されます。
痛み止めの内服薬や湿布を貼ることも効果的ですが、水が溜まってからおこなう薬物療法は一時的な処置です。
炎症をおさめる根本的な治療ではないことを念頭に置き服用しましょう。
膝が激しく痛む
水が大量に溜まりすぎると歩行すら難しい程度の痛みになることもあります。
膝の痛みが強い場合は変形性膝関節症や半月板損傷など原因となる膝の疾患が重症化していると予想されるため、早めの検査が必要です。
膝に水が悪化したら整形外科の受診が必要

膝の水が溜まりやすくなったり大量に溜まっていたりなど悪化している場合は、整形外科や膝専門のクリニックへに受診が大切です。
クリニックでは次のような検査や治療がおこなわれます。
関節炎の治療
滑膜の炎症をおさめるためには、膝の水を抜きヒアルロン酸を注射する治療やストレッチと筋トレで筋肉をほぐす運動療法などがあります。
原因となる膝の疾患が重症化している場合は手術の可能性もありますが、最初は運動療法や薬物療法で改善を試みます。
膝の水を抜く
膝の水を抜き水の色や浮遊物で原因を特定すると、適切な治療や日常生活で気をつけるべきことがわかります。
また滑液には炎症を引き起こす成分が含まれているため、まずは水を抜いて膝を軽くしましょう。
ヒアルロン酸の注射
水を抜いたあとはヒアルロン酸の注射による処置があります。
ヒアルロン酸は本来体内にあるもので副作用もなく、滑液と同じように関節の動きをサポートするはたらきがあります。
また炎症抑制の効果も期待できるため、処置後は痛みや腫れをおさえられる成分です。
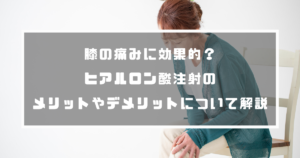
膝に水が溜まるのを防ぐためにできること5選!

膝に水が溜まることを防ぐには、日常生活において次の5つを気をつけましょう。
運動の習慣をつける
適度な運動は膝を支えるための筋肉も鍛えられ、体重増加も防げます。
膝を守るためには非常に重要なポイントであるため、毎日少しでもウォーキングやエアロバイクなど運動を習慣づけることをおすすめします。
太りすぎない
体重の増加は膝に大きなダメージとなります。
体重が重いと軽い運動でも膝に負担がかかりやすく炎症が起きやすいため、太りすぎない生活習慣を目指しましょう。
ストレッチ
膝に水を溜めないためには、膝の屈伸運動や膝の皿の血流改善を促すストレッチが運動療法としておすすめです。
膝を痛みの感じない範囲でゆっくりと曲げ伸ばし、筋肉をほぐすことがポイントです。
筋トレ
筋トレはストレッチのように筋肉をほぐすのみでなく、筋肉をしっかりと鍛えるトレーニングです。
膝が痛むと足を動かすことも億劫になりますが、膝を支える筋肉がついていないと関節に負担がかかるため水も溜まりやすくなります。
筋トレは水が少量溜まっている状態でもできますが、日頃から適度な運動や筋トレをおこなうことで予防効果も期待できます。
また、筋トレやストレッチをおこなう際は体を動かす準備運動をしましょう。
膝を冷やしすぎない
炎症が起きて患部が腫れている際の冷却は効果的ですが、常に冷やすことはおすすめしません。
膝を冷やすと血流も悪くなり周辺の筋肉も緊張するため、膝の冷却は痛みや腫れが気になる際におこないましょう。
膝に水が溜まった際によくある質問
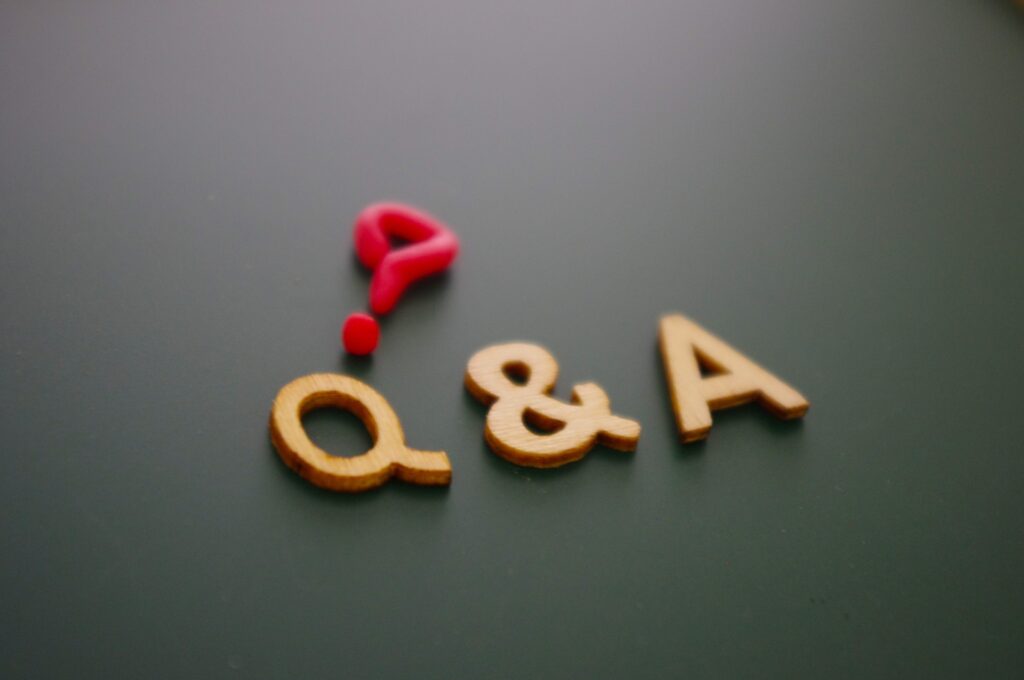
ここでは膝に水が溜まった際の質問についてまとめました。
膝の水に関して不安なことがある方は一度チェックして、これからの対策を考えてみましょう。
自然治癒の可能性は?
膝の水が自然に吸収されることは珍しくありません。
炎症が起きて一度水が溜まっても、安静にして冷やしていればおさまり正常に吸収されていくこともあります。
しかし一度抜いても炎症の原因が治療できなければ再び水が溜まります。
慢性的に水が溜まりやすくなっている方は、炎症の原因を特定するために一度水を抜くことをおすすめします。
膝に溜まった水を放置するとどうなる?
膝に水が溜まったまま放置すると、炎症がおさまらない限りは滑液が過剰に分泌されます。
炎症が一時的であれば放置しても滑液が吸収されて正常な膝になりますが、炎症がおさまらないと過剰分泌し続けて大量に水が溜まります。
また滑液には炎症や痛みを悪化させるサイトカインが含まれているため、最初は違和感が少なくても徐々に痛みを発することも考えられます。
膝の水を抜くと癖になる?
一度膝の水を抜くと癖になるという方は多いですが、実際に癖になることはありません。
ただ抜いても炎症の原因がおさまらないと再び水が溜まり続けるため、根本的な解決を目指しましょう。
膝の治療ができる専門クリニックはシン・整形外科

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン・整形外科は、再生医療による膝や肩などの関節痛の治療をおこなうクリニックで、次のような特徴があります。
- 膝を切らないリスクを抑えた治療
- 実績豊富な整形外科の専門医による診察
- 再生医療専門のリハビリで再発予防
それぞれ詳しく解説するため、膝に溜まった水と慢性的な痛みに悩んでいる方は、シン・整形外科の受診をぜひ検討してみてください。
膝を切らないリスクを抑えた治療
シン・整形外科が扱う再生医療は、膝を切らずにリスクを抑えたうえで痛みの根本解決ができる治療法です。
そもそも再生医療とは、人体が持つ自己再生能力を引き出し損傷を修復させるもので、保存療法では改善できない痛みの根本的な改善が期待できます。
また、自身から採取した血液や細胞を加工し患部に注入するため、手術に比べて拒絶反応のリスクも低く、体への負担も抑えられます。
とくに、高齢者のような体力が低下している方におすすめです。
治療は日帰りで受けられるため、生活への影響は少なく、仕事や家事も通常どおりおこなえます。
保存治療では改善できないけど手術には抵抗があるという方は、シン・整形外科の再生医療を検討してみるとよいでしょう。
実績豊富な整形外科の専門医による診察
シン・整形外科では、日本整形外科学会認定の専門医が診察をおこないます。
専門的な知識と再生医療の豊富な実績を有する医師が丁寧に診察をおこなうため、患者一人一人にあわせた治療の提案が可能です。
また、適切な検査の結果、再生医療が必要ないと判断した場合はほかの治療法を提案します。
もちろん強引に治療をすすめられることはないため、再生医療を受けた経験がない方も相談しやすいでしょう。
再生医療専門のリハビリで再発予防
シン・整形外科の特徴として、再生医療のみでなく治療効果を最大化するリハビに力を入れている点も挙げられます。
具体的には、経験豊富な理学療法士によるマンツーマン指導と、患者一人ひとりにあわせたオーダーメイドのリハビリメニューで治療後の患部の修復をサポートします。
また、上記のリハビリを月4回のスパンで継続しつつ、自宅での運動指導もおこなわれるため、永続的な痛みの再発予防も期待できます。
とくに、治療を受けているにもかかわらず膝の水や痛みを何度も繰り返している方は、再発しない体づくりで根本的な解消が期待できるでしょう。
発症前の生き生きとした暮らしを取り戻したい方は、ぜひシン・整形外科を受診してみてください。
まとめ
膝に溜まる水は関節内の炎症により過剰に分泌された滑液です。
放置することでおさまるケースもありますが、炎症の原因を探さないと水はたまり続け、痛みや腫れが強くなることもあります。
しかし痛みや腫れが軽いと病院に行く機会も少なく、つい溜まった水を放置しがちです。
筋トレや体重の減量で膝にかかる負担を減らすことも効果的ですが、変形や損傷など根本的な原因がある場合は水が溜まり続けます。
一度整形外科で水を抜き、根本的な原因を特定することが早期治療につながります。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。