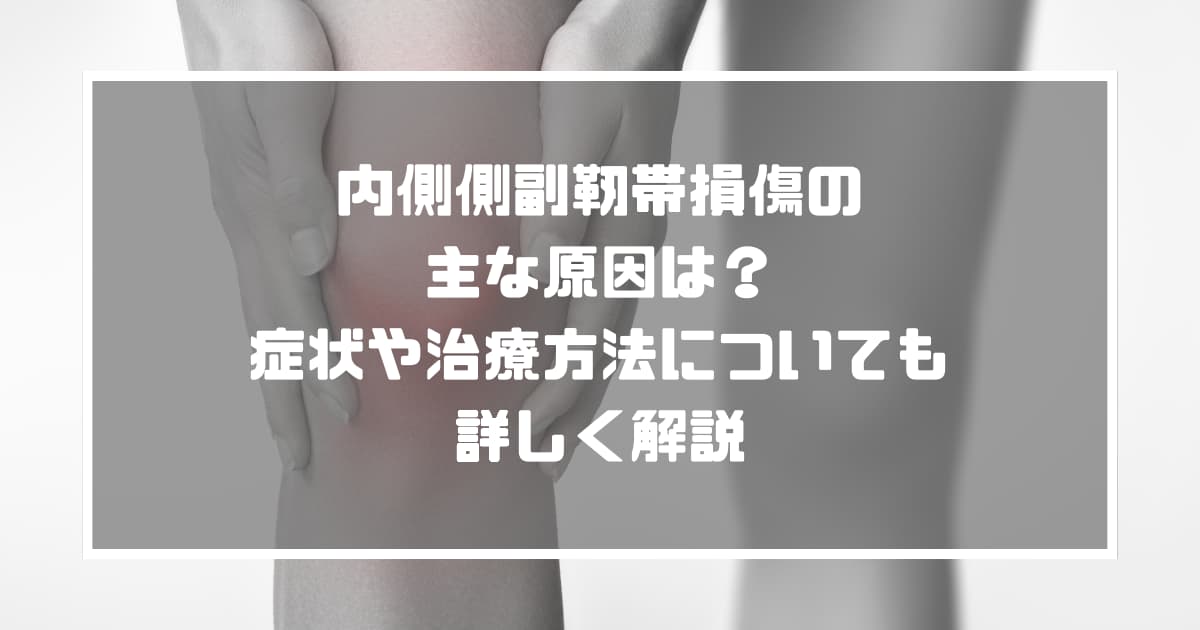内側側副靭帯損傷は、膝関節の内側にある靭帯に生じる外傷の1つです。
とくにスポーツをしている方に多くみられる靭帯損傷で、そのまま放置すると合併症を引き起こす可能性もあります。
そこで本記事では、内側側副靭帯損傷の主な原因や症状を詳しく解説します。
治療方法についても紹介しているため、膝に痛みがあり悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
内側側副靭帯損傷とは

膝関節の内側にある靭帯が何らかの外力によって伸ばされたり、部分的または完全に断裂したりするケガです。内側側副靭帯は、膝の内側を支える重要な靭帯で、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)をつないでいます。膝が内側に折れ曲がらないようにする役割を果たしており、日常生活やスポーツの動作において膝の安定性を保つために不可欠な組織です。
損傷の主な原因は、膝の外側から強い衝撃を受けたときです。たとえば、サッカーやラグビーなど接触の多いスポーツ中に相手選手とぶつかって膝が内側に押されるような状況で起こることがあります。また、スキーの転倒や階段での転落、交通事故などでも発症することがあります。
症状としては、膝の内側の痛みや腫れ、圧痛(押したときの痛み)、膝の不安定感などが挙げられます。靭帯が完全に切れてしまうと、膝がぐらつくような感覚が強くなり、日常の歩行にも支障をきたすことがあります。損傷の程度は軽度(靭帯が軽く伸びている)、中等度(部分断裂)、重度(完全断裂)の3段階に分類されます。
治療は、損傷の程度によって異なります。軽度から中等度の損傷であれば、保存療法が中心となります。具体的には、安静やアイシング、膝を固定する装具の使用、消炎鎮痛薬の内服などです。腫れや痛みが引いた段階で、徐々にリハビリを行い、膝の可動域や筋力を回復させていきます。重度の損傷や他の靭帯も同時に損傷している場合には、手術が必要になることもあります。
内側側副靭帯損傷は、適切な治療とリハビリによって多くの場合は回復が見込めますが、無理をして復帰を急ぐと再発するリスクもあるため、十分な安静と段階的な運動再開が重要です。
内側側副靭帯損傷の主な原因

内側側副靭帯損傷の主な原因は、接触型と非接触型にわけられます。
それぞれの原因について詳しく解説するため、どちらが自身に当てはまるかチェックしてみてください。
接触型
接触型とは、外部からの力が直接膝に加わることで発生するタイプの損傷です。特に膝の外側から強く押されるような力が加わると、膝が内側に押し込まれる形になり、内側側副靭帯が引き伸ばされて傷ついてしまいます。
たとえば、ラグビーやサッカー、柔道などのコンタクトスポーツでは、相手選手とぶつかったり、タックルを受けたりする場面が多く見られます。そうした瞬間に外側から膝に力が加わると、膝が横に崩れ、靭帯が耐えきれずに損傷してしまうのです。
また、交通事故などで膝の外側を打撲した場合にも、同じような力が働き、接触型の損傷が起こることがあります。このような損傷は、多くの場合、受傷した瞬間に「ぶつけた」「ひねった」などのはっきりした原因があるため、患者自身が自覚していることが多いのが特徴です。
非接触型
非接触型とは、相手との接触や衝突がなくても、自分自身の動きの中で膝に負荷がかかり、靭帯を痛めてしまうタイプの損傷です。スポーツ動作中、急に方向転換をしたり、ジャンプの着地でバランスを崩したり、急ブレーキをかけるような動きをしたときに、膝関節にねじれや過剰な外反(膝が内側に折れ込むような動き)が加わると、内側側副靭帯が引き伸ばされて損傷します。
このタイプは、筋力不足や柔軟性の低下、フォームの崩れ、疲労の蓄積など、身体的な準備不足が背景にあることが多く、慢性的に膝への負担がかかっていた結果として損傷が起こるケースもあります。特に、下半身の筋肉のバランスが悪かったり、体幹が不安定だったりすると、ジャンプや切り返しの動作で膝に不要なストレスがかかりやすくなります。
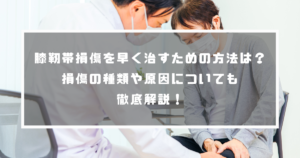
内側側副靭帯損傷の症状

内側側副靭帯損傷の主な症状は次のとおりです。
- 痛み
- 腫れ
- 可動域の低下
- 歩行困難
膝の内側に強い痛みを感じるケースが多いため、日常生活にも影響が出るでしょう。
それぞれの症状について詳しく解説するので、まだクリニックで診断を受けていない方は自身の症状と照らしあわせてみてください。
痛み
内側側副靭帯損傷では、膝の内側に鋭い痛みが出るのが最も代表的な症状です。損傷の直後からピリッと刺すような痛みが起こることが多く、特に膝の内側を押したときや、膝を内側に押し込むような力が加わると、痛みが一層強くなります。軽度の損傷であれば、日常生活での動作には耐えられる程度の痛みで済むこともありますが、中等度から重度になると、安静時でも痛みが持続し、夜間にうずくような痛みで眠れないこともあります。また、膝に負担のかかる運動や、急な方向転換、階段の昇り降りなどによって痛みが悪化する傾向があります。痛みの程度や発生するタイミングを正確に把握することは、損傷の深さを見極める手がかりにもなります。
腫れ
損傷によって靭帯周辺の血管が傷つき、内部で出血や炎症が起こることで、膝の内側に腫れが生じます。腫れは受傷してから数時間以内、早ければ30分ほどで目に見えて現れることがあり、特に靭帯の損傷範囲が広い場合は腫れの程度も大きくなります。関節の内側だけでなく、膝全体がふっくらと膨らんだように見えることもあります。触ると熱を帯びていたり、押すと少し痛みを伴うこともあります。強い腫れがあると、周囲の組織が圧迫されて関節の動きが制限されるだけでなく、神経や血管にも影響を与える可能性があり、重症例ではしびれを感じることもあります。腫れが引かないまま放置すると、関節内に水が溜まりやすくなることもあるため、冷却や圧迫による初期対応が重要です。
可動域の低下
靭帯の損傷による痛みや腫れが原因で、膝関節の動きが大きく制限されることがあります。特に膝を完全に伸ばしきったり、深く曲げようとしたときに強い痛みを感じ、それが恐怖感となって無意識に動きを控えるようになることで、さらに可動域が狭くなっていきます。また、腫れによって関節内部の圧力が高まると、関節を動かすだけで違和感が生じ、日常的な動作すら難しくなることもあります。数日間膝を動かさない状態が続くと、筋肉や腱、靭帯が硬くなってしまい、関節の可動範囲がさらに狭まります。特に高齢者や運動不足の方では、拘縮(こうしゅく)と呼ばれる関節の固まりが起きやすく、リハビリによる回復に時間がかかってしまうこともあるため、早期の改善を目指す対応が求められます。
歩行困難
内側側副靭帯は膝の安定性を保つ重要な役割を担っており、損傷すると膝がグラつくような感覚が出て、正常な歩行が難しくなります。軽度の損傷であっても、膝を支える筋肉に負荷がかかることで疲労しやすくなり、長時間の歩行が困難になる場合があります。中等度以上の損傷では、膝を曲げ伸ばしするたびに激痛が走ることもあり、足を引きずるような歩き方になってしまいます。また、膝が不安定な状態になることで、歩いている途中にガクッと崩れるような「膝折れ」現象が起こることもあります。これにより転倒のリスクが高まるため、日常生活の中でも不安を感じるようになります。痛みをかばう歩き方が続くと、反対側の足や腰にも余分な負担がかかり、他の部位に新たな障害を引き起こす可能性もあるため、歩行困難が続く場合には適切なサポートやリハビリが必要になります。
内側側副靭帯損傷の分類

内側側副靭帯損傷は、損傷の程度に応じて次のように分類されます。
内側側副靭帯損傷の分類方法は、Fetto&Marshallに基づくものとAmerican Medical Associationに基づくものの2種類があります。
それぞれの分類の内容について詳しく解説するため、あわせてチェックしてみてください。
Fetto&Marshallの分類
Fetto&Marshallでは、外反ストレステストをおこない、3つのグレードに分類します。
外反ストレステストとは、膝を内側に押し出した際の痛みや、内側側副靭帯の不安定性でグレードを測る検査方法です。
検査の具体的な流れは次のとおりです。
- 仰向けになり足をまっすぐ伸ばした状態で膝の外側に手をおく
- もう片方の手で足首にある足関節部をもつ
- 足関節部を外側に動かし(外反)内側側副靭帯の不安定性を確認する
- 膝を30°曲げた状態で同様に動かし内側側副靭帯の不安定性を確認する
上記の検査により、損傷の程度をGradeⅠ、GradeⅡ、GradeⅢの3つに分類します。
GradeⅠ
GradeⅠは、次のような場合に該当します。
・内側側副靭帯の疼痛のみ、外反ストレステスト0°、30°ともに陰性
つまり、外反ストレステストによる内側側副靭帯の不安定性は確認されず、軽い痛みのみがある場合にGradeⅠに分類されます。
GradeⅠであれば、保存療法で改善が期待できます。
GradeⅡ
GradeⅡは、次のような場合に該当します。
・外反ストレステスト0°陰性、外反ストレステスト30°陽性
膝を30°に曲げ外反ストレステストをおこなった場合のみに、内側側副靭帯の不安定性が確認されるとGradeⅡに該当します。
GradeⅡの場合も、保存療法での改善が期待できます。
GradeⅢ
GradeⅢは、次のような場合に該当します。
・外反ストレステスト0°、30°ともに陽性
外反ストレステストにおいて、膝を伸ばした状態と30°に曲げた状態の両方で内側側副靭帯の不安定性がある場合に分類されます。
American Medical Associationの分類
American Medical Associationに基づく分類は、内側側副靭帯の損傷の大きさや不安定性に応じておこないます。
グレードは、1度、2度、3度があり、外反ストレステストやレントゲン検査、MRI検査などの検査結果をもとに振り分けられます。
1度
1度は、次のような場合に該当します。
・小範囲の繊維の損傷で不安定性を認めないもの
つまり、内側側副靭帯がわずかに伸びたり、切れたりしているのみで不安定性が認められない場合に分類されます。
損傷の程度が軽いため、保存療法による改善が期待できます。
2度
2度は、次のような場合に該当します。
・軽、中等度の不安定性を認めるが完全断裂には至らないもの
内側側副靭帯の不安定性はありますが、完全な断裂はみられないため、一般的に保存療法が適応となります。
3度
3度は、内側側副靭帯が完全に断裂している場合に分類されます。
内側側副靭帯は治癒力が高いため、単独の断裂であれば保存療法が適応されます。
しかし、複数の靭帯損傷が合併し手術が必要になるケースも少なくありません。
そのため膝に違和感や痛みがある方は、早めにクリニックを受診しましょう。
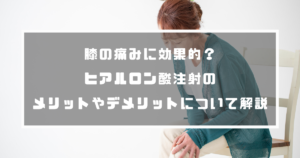
内側側副靭帯損傷の治療方法

内側側副靭帯損傷の治療方法は、保存療法と手術療法の2種類があります。
どちらの治療法が適応となるかは靭帯の損傷具合や状況で異なり、詳しい検査をしたうえで医師とよく相談する必要があります。
それぞれの治療方法の具体的な内容を解説するため、これから治療を受けたいと考えている方はぜひチェックしてみてください。
保存療法
保存療法では、組織を温存しながら炎症を抑え、可動域の制限を改善する治療がおこなわれます。
基本的には、リハビリテーションを中心としながら、損傷のグレードや状況に応じて治療法を組み合わせます。
たとえば、GradeⅠは、安静、アイシング、圧迫、挙上によるRICE療法、GradeⅡはテーピングやサポーターなどによる固定が一般的です。
また、痛みが強い場合は、消炎、鎮痛作用のある湿布や内服薬の使用や、超音波、低周波などの物理療法もおこないます。
手術療法
先述したように、内側側副靭帯以外の組織にも損傷がある場合は、手術療法が検討されます。
手術療法には縫合術や再建術などさまざまな方法があり、損傷の状態に応じて選択します。
手術方法のなかには体に対する侵襲を抑えられるものもあるため、慎重に検討しましょう。
また、術後は関節可動域訓練や、筋力訓練を目的としたリハビリテーションもおこないます。
クリニックでの内側側副靭帯損傷治療の流れ

クリニックでおこなわれる内側側副靭帯損傷治療は、次のような流れでおこなわれます。
- 予約
- 診察
- 検査
- 診断・治療方針
- 治療
細かい流れはクリニックごとに変動する場合があります。
それぞれの流れを詳しく解説するので、まだクリニックを受診していない方は事前に確認しておきましょう。
1:予約
まずは、整形外科があるクリニックで予約を取りましょう。
予約なしで診察可能なクリニックもありますが、待ち時間が長かったり、空き枠がなく当日に受けられなかったりする可能性もあります。
とくに、忙しい方やスムーズに診察を受けたい方は、事前の予約がおすすめです。
また、症状や予約の空き状況によっては、当日に物理療法や注入治療などができる可能性もあるため、長めに時間を確保しておくとよいでしょう。
2:診察
予約日時に来院したら、問診票を記入し医師による診察を受けます。
診察では、症状の程度やきっかけなど、詳しい内容をヒアリングする問診や、視診、触診などをおこないます。
とくに、ヒアリングは病気を見つけるうえで重要な工程であるため、症状に関する情報は覚えている範囲できちんと伝えましょう。
上記の診察で得た情報をもとに、診断に必要な検査を決定します。
3:検査
内側側副靭帯損傷が疑われる場合におこなう検査は次のとおりです。
- 外反ストレステスト
- MRI検査
- レントゲン検査
内側側副靭帯損傷であれば、外反ストレステストである程度の損傷具合を判断できます。
しかし、半月板や骨、複数の靭帯が損傷している可能性もあるため、MRI検査やレントゲン検査で膝関節内の状態を把握する必要があります。
とくに、MRI検査は、内側側副靭帯損傷と併発しやすい半月板損傷も確認が可能です。
4:診断・治療方針
診察と検査結果をもとに、最終的な診断をおこないます。
内側側副靭帯損傷であると判断された場合は、検査で把握した損傷の状態に合わせた治療方針を決めます。
治療方法ごとに効果や費用は異なるため、自身のライフスタイルに応じた治療ができるように医師とよく相談しましょう。
5:治療
決定した治療方針にあわせて治療を開始します。
先述したように、治療方法には保存療法と手術療法があり、症状に応じて選択することが大切です。
自己判断で治療を中止したり、過度なリハビリテーションをおこなったりすると症状を悪化させる可能性もあるため、医師の指示に従いましょう。
わからない点や不安な点があれば、通院の際に医師に相談してみてください。
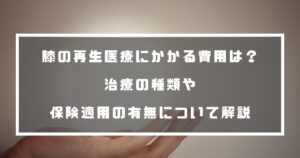
内側側副靭帯損傷を治療するならシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
内側側副靭帯損傷を治療するなら、関節痛治療専門のシン・整形外科がおすすめです。シン・整形外科のおすすめポイントは次のとおりです。
- 手術なしで痛みを除去できる再生医療に特化
- 整形外科の専門医による治療
- 安心の保証制度あり
それぞれ詳しく解説するため、内側側副靭帯損傷にお悩みの方はぜひチェックしてみてください。
手術なしで痛みを除去できる再生医療に特化
シン・整形外科では、手術なしで痛みを除去できる再生医療に特化したクリニックです。
再生医療とは、人体に備わる自己再生能力を活用し損傷した組織を修復する治療法で、患者自身の細胞や血液を加工し患部に注射します。
自身の細胞や血液を注射するため、拒絶反応や合併症などのリスクが低く、日帰りで受けられる点が魅力です。
とくに、保存療法では内側側副靭帯損傷が改善しなかった方や、手術に抵抗がある方にピッタリといえます。
再生医療は経験豊富な整形外科の専門医が丁寧な診察をおこない提案するため、初めて再生医療を受ける方も安心して相談できるでしょう。
3つの再生医療から選択
再生医療にはさまざまな種類がありますが、シン・整形外科では次のようなを治療法を扱っています。
| 種類 | 治療内容 |
|---|---|
| 幹細胞培養治療 | 患者の脂肪細胞から幹細胞を抽出、培養して損傷箇所に注入 |
| PRP-PRO治療 | 患者から採取した血液を厚生労働省認可の施設で加工し、損傷箇所に注入 |
| PRP-FD治療 | 患者の血液から精製したPRPをフリーズドライ加工し損傷箇所に注入 |
幹細胞培養治療は、多様な細胞に分化できる幹細胞を患部に注入することで、自然治癒が難しい組織損傷の修復が期待できます。
また、シン・整形外科のPRP療法は、組織の修復を促し、痛みのもととなる炎症を抑える成長因子やサイトカインが従来よりも多く含まれている点が特徴です。
そのため、痛みに対してより大きな効果が期待でき、効率的に内側側副靭帯損傷の治療が可能です。
もちろん、再生医療以外の治療法の提案も可能なため、広い選択肢から治療法を選びたい方はぜひ気軽に相談してみてください。
安心の保証制度あり
シン・整形外科では、再生医療の万が一に備えた次の保証制度を用意しています。
| 保証内容 | 保証対象 | |
|---|---|---|
| 再治療保証 | 無料で1回分の再生医療を追加で受けられる ※保証期間:初回施術から1年間 | 幹細胞培養治療を2回以上と、当リハビリスタンダードコースを6ヶ月以上受けたうえで効果が得られなかった方 |
| リスク保証 | 再生医療サポート保険のサービスを利用可能 | 再生医療の施術により健康被害を被った方 |
とくに、効果が得られない場合に無料で追加治療を受けられる点は、治療費用をできる限り抑えたい方に嬉しい保証です。
また、リスク保証があれば、万が一再生医療で健康被害を受けた場合でも、治療費用の負担を軽減できます。
再生医療は低リスクな治療法ですが、上記のような保証で万が一に備えられるのはシン・整形外科ならではの魅力です。
内側側副靭帯損傷の痛みを早く手軽に改善したい方は、ぜひシン・整形外科を検討してみてください。
まとめ

内側側副靭帯損傷の原因には、接触型と非接触型があり、どちらもスポーツで頻発します。
とくに、ジャンプや急な方向転換などで膝に衝撃が加わりやすいスポーツや、選手同士の接触が多いスポーツは注意が必要です。
内側側副靭帯は治癒力が高いため、単独の損傷であれば基本的に保存療法が選択されます。
症状が軽いうちに治療を開始できれば、スポーツの早期復帰も期待できます。
ただし、半月板や前十字靭帯などの周辺組織の損傷が併発するケースも多く、手術が必要になる場合もあります。
症状を悪化させないためにも、できる限り早めにクリニックを受診し、適切な治療を受けましょう。