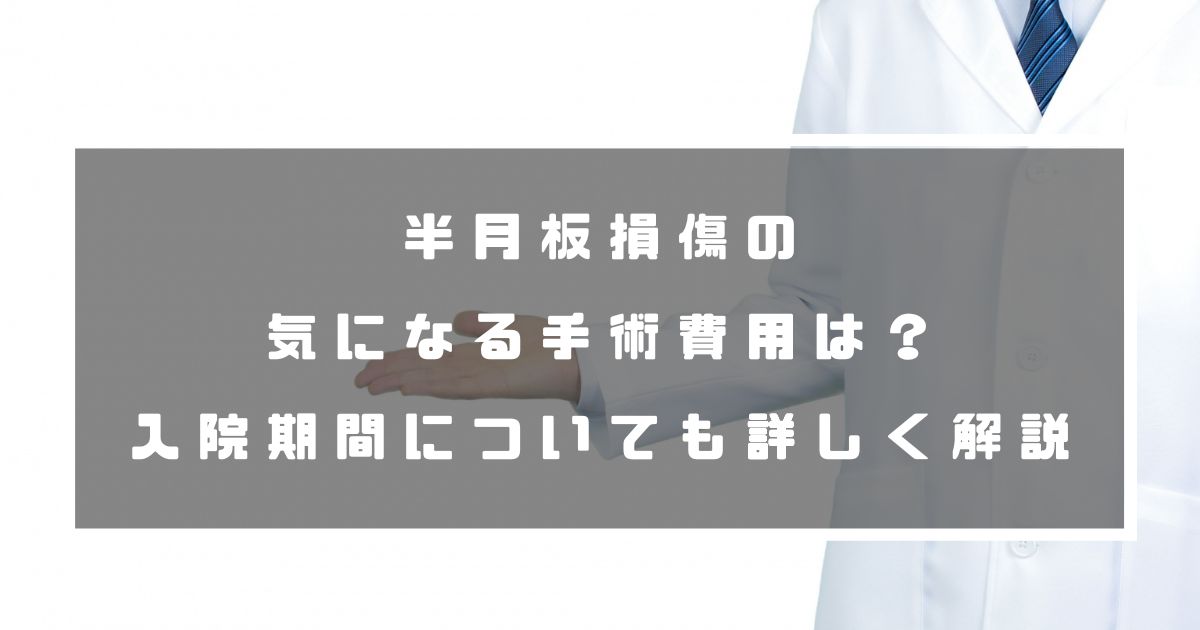半月板が損傷すると、日常の生活動作でも痛みを感じるようになり、歩くことが億劫になる方もいます。
温存治療で効果が感じられない場合、手術を検討する方もいるでしょう。事前に費用の目安や、利用できる助成制度を知っておくと、安心して治療に臨めます。
本記事では、半月板損傷手術の費用相場や入院期間、半月板損傷手術で受けられる医療助成制度などを解説します。
半月板損傷手術について知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
半月板損傷の症状とは

半月板損傷の症状は、膝にかかる負担や損傷の程度によって現れ方が異なりますが、多くの場合、膝の中で「引っかかる」「挟まる」といった感覚が出やすいのが特徴です。まず代表的なのは膝の痛みで、歩いたり走ったりする動作で強く出ることが多く、特に階段の上り下りやしゃがみ動作の際に悪化しやすいです。また、膝の中で異物感を覚えたり、急に膝が動かなくなるロッキングと呼ばれる状態になることもあります。このような症状が起こると、スムーズに歩行できなくなり、膝を曲げたり伸ばしたりする動作が妨げられます。
さらに、膝関節内で炎症が生じることで腫れや熱感が現れることもあります。水が溜まる関節水腫が起こるケースも多く、膝が重く動かしにくくなるのも典型的です。損傷の程度が強いと、膝の可動域が制限され、正座やしゃがみ込みといった日常の動作が困難になる場合があります。痛みや違和感はスポーツ活動だけでなく、日常生活の中でも繰り返し生じることが多く、症状が長引くと膝をかばって歩くようになり、周囲の筋力低下を招くことにもつながります。
このように、半月板損傷の症状は単なる膝の痛みにとどまらず、引っかかり感やロッキング、腫れや水の貯留、動作の制限といった複合的な不調として現れるため、放置すると悪化して長期的な機能障害につながる危険があります。

半月板損傷の治療方法
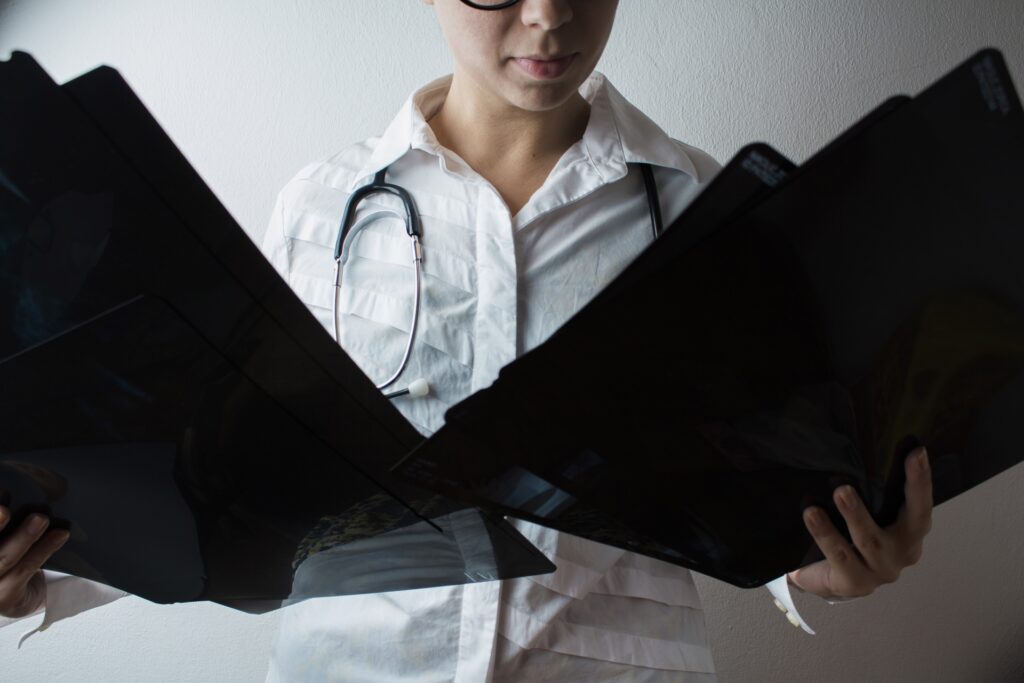
半月板損傷の治療方法で手術が選択されるのは、損傷部位が大きかったり、自然治癒が期待できなかったりする場合です。
半月板損傷の治療法について、詳しく解説します。
半月板損傷の手術
半月板損傷の治療は、まず損傷の程度や年齢、活動レベル、痛みの強さなどを考慮して方法を選びます。軽度であれば保存療法と呼ばれる手術をしない治療から始めることが多いです。安静にすることで膝の負担を減らし、炎症を抑える薬を使用したり、膝関節に負担をかけにくいストレッチや筋力トレーニングを行います。また、膝に水がたまって腫れる場合は注射で水を抜いたり、ヒアルロン酸注射で関節の動きを滑らかにすることもあります。保存療法で症状が改善しない場合や、半月板の損傷が大きい場合には手術療法が検討されます。
半月板切除術
保存療法で改善が見込めないケースや、半月板の損傷が広範囲に及んでいる場合には手術が必要になります。手術は主に関節鏡という細いカメラを使って行われ、膝に小さな切開を加えて内部を観察しながら処置を進めます。手術方法には半月板を部分的に切除する方法と、縫合して修復する方法があり、それぞれの適応は損傷の部位や形状によって異なります。スポーツ選手や活動量の多い若年者では、可能な限り半月板を温存することが望まれます。なぜなら半月板は膝の衝撃吸収や安定性の維持に重要な役割を果たしており、切除すると将来的に変形性膝関節症のリスクが高まるためです。
半月板縫合術
半月板切除術は、損傷した部分を切り取って症状を改善する方法です。切除によって引っかかりやロッキングがなくなり、比較的短期間で痛みが軽快することが多いのが特徴です。しかし半月板を一部でも切除すると、膝関節にかかる衝撃吸収能力が低下し、長期的には関節軟骨への負担が増す可能性があります。そのため現在では、できるだけ切除範囲を最小限にとどめる「部分切除術」が主流となっています。特にスポーツ復帰を目指す場合にはリハビリを徹底して行う必要があり、切除後の膝を守るために筋力強化や柔軟性改善を継続することが勧められます。
手術をしない新しい治療法
近年では、必ずしも外科的手術を行わなくてもよい新しい治療法が注目されています。その代表例が、再生医療やバイオ治療を応用した方法です。例えば自己血小板を濃縮したPRP療法は、損傷部位の修復を促す成長因子を利用して自然な治癒をサポートします。また衝撃波治療や特殊なリハビリプログラムも、組織の回復や炎症の軽減に役立つとされています。これらの治療法はまだ研究段階にある部分も多いですが、手術を避けたい患者や高齢者にとっては有望な選択肢となっています。
幹細胞治療
幹細胞治療は、半月板損傷に対する最先端の再生医療の一つで、患者自身の脂肪組織や骨髄から採取した幹細胞を膝関節に注入し、損傷した半月板の修復を促す方法です。幹細胞には組織を再生する能力があり、単に痛みを和らげるだけでなく、損傷した半月板そのものを修復できる可能性がある点が大きな魅力です。従来の切除術や縫合術と比べても膝関節の機能を長く保てると期待されており、将来の標準治療になる可能性もあります。ただし、まだ保険適用外で高額になることや、研究段階で長期的な効果が十分に確立されていないという課題もあります。それでも従来の治療で改善しにくい患者や、スポーツ選手など関節機能を重視する人々から注目を集めています。
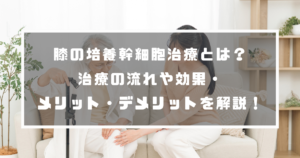
PRP治療
半月板損傷に対する治療方法のひとつとして、PRP療法があります。PRPとは「Platelet Rich Plasma(多血小板血漿)」の略で、自分自身の血液を採取し、遠心分離機にかけて血小板を多く含む部分を抽出し、それを患部に注射する再生医療の一種です。血小板には組織の修復や炎症を抑える成分が豊富に含まれており、半月板に注入することで自然治癒力を高め、損傷部位の修復を促す効果が期待できます。
半月板損傷の手術費用相場

半月板損傷の手術費用の相場を紹介します。
損傷の程度や治療内容で金額が大きく変わることがあるため、あくまでも目安として確認してみてください。
半月板切除術
半月板切除術は、損傷した半月板の傷んだ部分を取り除く手術です。比較的短時間で行えるため身体への負担も少なく、費用はおおよそ保険適用後で10万~20万円前後が一般的とされています。手術自体がシンプルであることから費用は縫合術に比べて抑えられる傾向があります。ただし、半月板を切除すると将来的に関節軟骨への負担が増え、変形性膝関節症などを発症しやすくなる可能性があるため、短期的な改善を重視するか長期的な膝の健康を重視するかで選択が分かれることがあります。
半月板切除術の入院期間
半月板切除術の入院期間は短い傾向にあり、平均すると数日から1週間程度で退院できるケースが多いです。場合によっては日帰り手術として行える医療機関もあります。術後は比較的早期から歩行が可能になり、数日で杖や松葉杖なしでの移動が可能になることも珍しくありません。ただし、早期に退院できても自宅での安静やリハビリを怠ると再発や関節への負担が強まるため、退院後もリハビリの通院が必要となります。
半月板縫合術
半月板縫合術は、損傷した半月板を取り除かずに縫い合わせて修復する手術方法です。半月板を温存できるため、将来的に膝関節への負担を減らし、関節の変性を予防する効果が期待できます。費用は切除術に比べて高額になり、保険適用後でもおおよそ20万~40万円程度が目安とされています。損傷部位の状態によっては縫合が適応できない場合もあるため、必ずしも全員が受けられるわけではありませんが、スポーツ選手や長く膝の機能を維持したい人に選ばれることが多い手術です。
半月板縫合術の入院期間
半月板縫合術は修復した半月板をしっかり固定して癒合を待つ必要があるため、入院期間は切除術に比べて長くなります。一般的には2週間から3週間程度の入院が必要とされ、さらに術後は膝の安静を守りながら徐々にリハビリを進めていきます。特に縫合術では、術後すぐに膝を大きく動かしたり体重をかけたりすると縫い合わせた部分が再び損傷するリスクがあるため、回復までの期間が長くなる傾向にあります。その分、長期的には関節の健康を保ちやすいという利点があります。
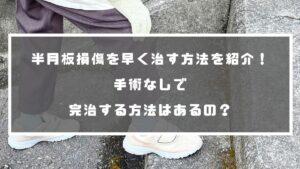
半月板損傷手術で受けられる医療制度や助成

半月板損傷の手術にかかる費用は安いものではありません。
ここでは半月板損傷の手術で受けられる医療制度や助成を紹介します。
高額医療制度
高額医療費制度とは、同じ月(1日から月末まで)に医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、超過分があとで払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得状況などで変わります。
69歳以下の方の自己負担限度額は次のように設定されています。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
| ア | 年収約1,160万円~ | 252,600+(医療費-842,000)×1% |
| イ | 年収約770~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% |
| ウ | 年収約370~約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% |
| エ | ~年収約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上の方の自己負担限度額は次のとおりです。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
| 外来(個人ごと) | |||
| 現役並み | Ⅲ年収約1,160万円~ | 252,600+(医療費-842,000)×1% | |
| Ⅱ年収約770万円~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% | ||
| Ⅰ年収約370万円~約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% | ||
| 一般 | 年収156~約370万円 | 18,000円 (年14万4千円) | 57,600円 |
| 住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下) | 15,000円 | ||
高額医療費制度は、払い戻しを受けるまで医療費を立て替えておく必要があります。
しかし事前に「限度額適用認定証」の交付を受けておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませられます。
更生医療
更生医療とは身体障がいを持つ方が障がいを除去したり、軽減したりする治療を受けるときに、自立支援医療費が支給されるものです。
しかしながら新鮮外傷による半月板損傷に対する手術は、更生医療の対象外であるため、半月板損傷の手術で更生医療の適用を受けることはできません。
障害年金
半月板損傷が重症化し、変形性膝関節症になった場合は障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
初診日要件とは、障がいの原因となった傷病の初診日時点で、国民年金または厚生年金のどちらかに加入していることです。
保険料納付要件は、一定以上の年金保険料を納めていなければならないことで、障害状態該当要件は、厚生労働省が定めた障害認定基準を満たしているかどうかです。
下肢についての障害認定基準は次のように定められています。
- 下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの(3級)
- 下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの(障害手当金)
(引用元:国民年金・厚生年金保険障害認定基準|日本年金機構)
3つの要件をすべて満たしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、その期間給与が支払われなかった場合に支給されるものです。
傷病手当金は、次の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
(引用元:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会)
傷病手当金が支給されるのは、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
傷病手当金は1日あたり次の金額が支給されます。
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3
介護保険
介護保険とは、65歳以上で要介護、要支援認定を受けた方が、1~3割の自己負担で介護保険サービスを受けられる公的制度です。
要介護認定は各市区町村がおこないますが、要介護と要支援を分ける基準の一つは認知能力であるとされています。
半月板損傷により自由に歩くことが難しい方は、認知能力に問題がなければ要支援段階であると考えられ、介護予防サービスを受けられる可能性があります。
介護保険サービスを希望する場合は、各市区町村の担当窓口に要介護認定を申請しましょう。
また40~64歳であっても、特定疾病で介護が必要な状態になったと認定された方は介護保険サービスを受けられます。
半月板損傷手術後のリハビリ方法

半月板損傷の手術後のリハビリは状態によって異なりますが、一般的に切除術であれば約2~3か月、縫合術であれば約3~6か月の通院リハビリが必要です。
どのようなリハビリを実施するのか解説します。
関節可動域訓練
膝関節の可動域(膝を曲げ伸ばしできる角度)を回復させる運動です。関節は筋肉や靱帯に支えられて動いているため、筋肉や人体の緊張を緩めることで膝を動かしやすくなります。
また関節が固まったり、変形したりしてしまわないためにも、可動域を大きくしていく訓練が必要です。
太もも前側を伸ばすストレッチ
太もも前側を伸ばすストレッチは次のようにおこないます。
- 片膝を曲げて床に座る
- 上半身を後ろに徐々に倒す
膝関節を支える最も大きな筋肉である大腿四頭筋を伸ばせるため、効果的です。
股関節のストレッチ
股関節のストレッチは次のようにおこないます。
- 床に座り、両足の足裏を合わせる
- かかとを体に近づける
- 手のひらで足の甲を押さえながら、肘で脚を押し広げる
膝関節以外に股関節のストレッチも実施すると、股関節が柔らかくなり、膝への負担を少なくできます。
筋力トレーニング
関節可動域訓練のあと、または同時並行で膝周辺の筋力トレーニングをおこないましょう。半月板には体重を支えて体を安定させる働きがありますが、損傷すると役割を果たせなくなります。
そのため、半月板以外の器官で体を安定させられるように、膝周辺の筋力を強化する方法があります。筋力トレーニングは、半月板損傷を再発させないためにも重要です。
筋力トレーニングの方法は、次のような「枕つぶし」が代表的です。
- 床に足を伸ばして座る
- 痛む方の膝の下に枕や丸めたバスタオルなどを置く
- 膝の裏で枕を押しつぶして5秒キープする
そのほかにもさまざまな筋力トレーニングがあります。医師の指示にしたがって、無理のないようにおこなってください。
半月板損傷の手術費用についてよくある質問

半月板損傷の手術費用について、よくある質問をまとめました。
手術後の高額医療費制度を申請する方法は?
手術後に高額医療費制度の申請を実施する方法は、加入している健康保険によって異なるため、自身が加入している健康保険組合のWebサイトで申請方法を確認しましょう。
会社員が加入する組合健保や協会けんぽなどの健康保険では、加入する健康保険組合に「高額療養費支給申請書」を提出します。
それぞれ申請様式や方法が異なり、添付書類が必要になるケースもあります。自身が加入している健康保険組合がわからない場合は、健康保険証を確認してみてください。
また申請してから払い戻しを受けるまでに3か月以上かかる場合が多く、さらに申請できる期限が決められているため、早めに手続きをした方がよいでしょう。
自営業者が加入する国民健康保険では、市区町村の担当窓口に「高額療養費支給申請書」を提出します。
市区町村によっては自己負担限度額を超えた月の3~4か月後に、申請書が自宅に郵送されてくる場合もあります。
申請書とともに本人確認書類や健康保険証、マイナンバーカード、医療機関の領収書などの添付書類が必要です。
必要な書類については、お住まいの市区町村のWebサイトで確認してみてください。
限度額適用認定はどのようにしたら手に入れられますか?
限度額適用認定証は、自身が加入する健康保険組合に「限度額適用認定申請書」を提出すると取得できます。
限度額適用認定申請書は、各健康保険組合のWebサイトでダウンロードし、記入して郵送する方法が一般的です。
郵送する際に、保険証のコピーを同封する必要があるケースが多いため、よく申請方法を確認しておきましょう。
国民健康保険に加入している場合は、お住まいの市区町村の担当窓口やWebサイトで限度額適用認定申請書を入手し、直接または郵送で提出します。
本人確認書類やマイナンバーカードなどが必要になるため、事前に市区町村のWebサイトで必要書類を確認しておくとスムーズに手続きできます。
半月板損傷の治療にはシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科の半月板損傷の治療は、以下の理由からおすすめです。
・専門知識と経験豊富な医師陣
・最新の医療技術
・安心の手術
・パーソナライズされたケア
専門知識と経験豊富な医師陣
シン整形外科は専門知識を持つ医師がいるため、患者の症状や状態について本質的な診断や治療プランを提供しています。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ

半月板が損傷すると、膝を曲げ伸ばしする際に痛みやひっかかりを感じ、ひどい場合は急に膝が動かなくなる場合もあります。
半月板損傷の治療方法は、切除術や縫合術の手術が一般的でしたが、幹細胞による再生医療で手術をせずに損傷部位を再生できるようになりました。
半月板切除術の費用相場は7~15万円、半月板縫合術の費用相場は9~20万円です。医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額医療費制度があります。
事前に限度額適用認定証を申請し交付を受ければ、窓口での支払いが限度額までで済みます。
手術を受けることが決まったら早めに申請しておきましょう。
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。