- 膝靭帯を損傷してしまったらクリニックへ行くべきか悩む
- 膝靭帯損傷を早く治すにはどうすればよいのか知りたい
- 膝靭帯を損傷するとどのような症状が起こるのか教えてほしい
当記事では上記の悩みについて解説していきます。
膝を負傷した痛みから靭帯損傷を疑っている方でも、具体的な症状まで理解している方は少ないでしょう。膝靭帯損傷にはいくつか種類があり、自身では判断しにくいです。
しかし、膝は歩いたり走ったりするのに重要な部位であるため、膝靭帯が損傷してしまったら日常生活に支障が出ます。
そこで、
- 膝靭帯損傷の原因や症状
- クリニックに行くべきタイミング
などを解説します。少しでも早く治るよう当記事の内容を、ぜひ参考にしてみてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
膝靭帯損傷の4つの種類
 膝靭帯損傷には4つの種類があります。4つそれぞれに起こりやすい原因や症状が異なり、しっかり理解して見極めることが大切です。
膝靭帯損傷には4つの種類があります。4つそれぞれに起こりやすい原因や症状が異なり、しっかり理解して見極めることが大切です。
なぜなら、膝靭帯損傷の種類によって治療法が異なる可能性があるからです。しっかり症状をみて、適切な治療法で早く治せるよう努めることが重要になるでしょう。
4つある膝靭帯損傷の種類は次のとおりです。
- 膝外側側副靱帯損傷
- 膝内側側副靭帯損傷
- 前十字靭帯損傷
- 後十字靭帯損傷
次は4つの種類の原因や症状をひとつずつみていきましょう。
膝外側側副靱帯損傷
膝外側側副靱帯損傷とは、膝の外側に位置する外側側副靱帯(LCL: lateral collateral ligament)が部分的あるいは完全に損傷する状態を指します。この靱帯は、大腿骨と腓骨の外側をつなぎ、膝が外側にぐらつくのを防ぐ重要な役割を担っています。主な原因は、膝の内側から外に向かって強い力が加わったときで、特にラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツで、タックルや転倒によって起こりやすいです。また、スキーやバイク事故など、膝に強いねじれや側方の衝撃が加わったときにも発生します。
症状としては、膝の外側に鋭い痛みや腫れ、押さえたときの圧痛、膝を動かした際の不安定感が挙げられます。歩行や階段の上り下りに違和感を感じることもあります。LCL損傷は単独で起こることは比較的少なく、前十字靱帯や後十字靱帯、後外側構造といった他の部位と同時に損傷するケースも多いため、診断と評価にはMRIなどの精密検査が必要になります。治療は、軽度の損傷であれば安静や装具固定、リハビリテーションによって回復が見込めますが、重度や合併損傷がある場合は手術が必要となることがあります。
膝内側側副靭帯損傷
膝内側側副靱帯損傷とは、膝の内側にある内側側副靱帯(MCL: medial collateral ligament)が損傷を受ける状態です。MCLは、大腿骨の内側と脛骨の内側をつなぎ、膝が内側に曲がりすぎたり、外側からの衝撃を受けたときに安定性を保つ役割を果たしています。この靱帯は、膝靱帯の中でも最も損傷しやすい部位であり、特に外側からの直接的な衝撃によって引き伸ばされることが主な原因です。スポーツではサッカーやラグビー、柔道など、相手との接触が頻繁にある競技でよく発生します。
症状としては、膝の内側に痛みが走り、腫れや皮下出血が現れることがあります。また、膝の内側を押すと強い痛みが出たり、膝を曲げ伸ばしした際に不安定さを感じることもあります。重症の場合には、歩くことが難しくなったり、膝がカクカクと崩れるような感覚が出てくることもあります。
診断は徒手検査やX線、MRIなどで行われ、損傷の程度によってグレード1(軽度)からグレード3(完全断裂)まで分類されます。軽度であれば保存的治療が中心で、装具を使いながら日常生活を送りつつ、リハビリによって筋力と可動域の回復を目指します。中等度以上の場合には長期的な装具療法や、まれに手術が必要となることもありますが、適切に治療すれば元の機能まで回復できることが多いです。
前十字靭帯損傷
前十字靱帯(ACL: anterior cruciate ligament)は、膝関節の内部にあり、大腿骨と脛骨の間を斜めに走っている靱帯で、膝が前方にずれるのを防ぎ、膝関節の回旋運動を安定させる重要な構造です。ACLが損傷するのは、特にジャンプの着地や急なストップ動作、急激な方向転換など、膝にねじれや前方向への力が加わるときに多く見られます。バスケットボール、バレーボール、スキー、サッカーなどのスポーツで頻発し、女性アスリートのほうが男性よりも発生率が高いとも言われています。
前十字靱帯損傷の特徴的な症状としては、「ブチッ」という断裂音を感じたり、膝が急に崩れ落ちるような感覚(膝くずれ)があります。直後から急激な腫れと痛みが生じ、数時間以内に膝が大きく腫れることも少なくありません。時間が経過すると痛みは落ち着くものの、膝の不安定感が続き、歩行やスポーツ復帰に支障をきたすようになります。
ACLは自然には再生されないため、特にスポーツを継続したい人や日常生活でも膝が不安定な人には、再建手術が推奨されます。手術後は半年から1年程度のリハビリが必要で、関節の可動域訓練、筋力トレーニング、バランス練習などを段階的に進める必要があります。一方で、日常的な活動に制限が少ない高齢者や運動量が少ない人の場合は、保存療法(装具や筋力強化)を選択することもあります。
後十字靭帯損傷
後十字靱帯(PCL: posterior cruciate ligament)は、前十字靱帯と交差するように膝関節の内部に存在しており、脛骨が後方にずれすぎるのを防いでいます。PCLは非常に強靭な靱帯で、損傷する頻度はACLよりも低いとされています。主な損傷原因としては、膝を強く打ちつける外傷が多く、特に交通事故で車のダッシュボードに膝をぶつけた際や、膝を地面に強くついたときに起こりやすいです。スポーツでは、アメリカンフットボールやレスリングなどの衝撃を受けやすい競技でも見られます。
PCL損傷の症状としては、膝の奥のほうに痛みを感じたり、膝の後ろ側に圧痛が出ることがあります。腫れはACL損傷ほど目立たないこともあり、症状が軽く見過ごされがちです。しかし、慢性的なPCL損傷は、膝の後方不安定性を引き起こし、関節軟骨や半月板に負担がかかることで変形性膝関節症に進行することもあります。
軽度のPCL損傷であれば、保存療法によって十分な回復が見込めます。リハビリでは大腿四頭筋の強化を中心に行い、関節の安定性を高めることが重要です。しかし、複数の靱帯が同時に損傷している場合や、膝のぐらつきが強く日常生活に支障がある場合には、再建手術が検討されます。PCLの再建術は技術的にやや難しいため、経験のある専門医の診断と治療が求められます。
膝靭帯損傷の原因
 ここからは、膝靭帯損傷が起こる原因や状況を確認していきましょう。
ここからは、膝靭帯損傷が起こる原因や状況を確認していきましょう。
しっかり原因を理解していれば、膝靭帯損傷が起こりやすい状況においても注意でき、ケガを回避しやすくなります。
膝靭帯損傷が起こりやすい場面は次のとおりです。
- 激しいスポーツ中に衝撃を受けたとき
- 交通事故を起こしたとき
どちらも膝に強い衝撃を受けることで受傷するリスクが上がります。次はそれぞれの状況を具体的に解説していきます。
スポーツによる損傷
スポーツ中は膝靭帯損傷がもっとも起こりやすい状況です。激しく走ったりぶつかったりして膝に強い負荷がかかりやすいからです。膝に負荷がかかることで膝靭帯が断裂する可能性があります。
基本的にはすべてのスポーツで気をつけるべきですが、とくに注意すべきスポーツの例をあげます。
- サッカー
- ラグビー
- 柔道やレスリング
- テニス
- バスケットボール
- バレーボール
- スキーやスノーボード
膝の靭帯損傷は回復にかかる時間やリハビリの時間を考えると、スポーツに復帰されるまで数か月ほどかかってしまいます。少しでも早く治すためにも、クリニックの早急な受診と正しい治療が重要となってくるでしょう。
交通事故による損傷
起こる頻度は稀ですが、交通事故でも膝靭帯損傷が起こることがあります。自転車やバイクでの転倒や歩行中に自動車にひかれた場合など、あらゆる事故に気をつけなければなりません。
また、交通事故で靭帯を損傷すると、適切な治療を受けても後遺症が残ってしまうこともあります。なぜなら、事故による衝撃は膝にとても強い力を与えるからです。
いつまでも続く膝の痛み、正常に膝が曲がらなくなる可動域制限などが後遺症としてあげられます。万が一、これ以上治療しても症状が治らない場合、後遺障害等級の認定申請をおこなうことで後遺障害と認められる可能性があります。
膝靭帯損傷の症状
 膝靭帯を損傷すると日常生活に支障をきたすさまざまな症状が起こります。自身の痛みの特徴に該当しているのか確認してみてください。
膝靭帯を損傷すると日常生活に支障をきたすさまざまな症状が起こります。自身の痛みの特徴に該当しているのか確認してみてください。
具体的な症状を4つあげます。
- 膝の痛み
- 膝の腫れ
- 関節の不安定感や動きの制限
- 歩行障がい
次はひとつずつ確認していきましょう。
膝の痛み
膝靭帯損傷でもっとも基本的で早期に現れる症状が膝の痛みです。損傷直後は鋭い痛みが走り、その後もじんじんとした痛みが続きます。痛みの部位は損傷した靭帯の位置によって異なります。たとえば内側側副靱帯が傷ついた場合は膝の内側、前十字靱帯損傷なら膝関節の中央や奥の方に痛みを感じることが多いです。痛みの程度も靱帯の損傷レベル(軽度の捻挫から完全断裂まで)によって大きく異なり、重度の場合には安静時でも痛みが続いたり、わずかな動きで激痛を感じることもあります。また、周囲の組織や半月板などの合併損傷がある場合は、痛みがより強く、広範囲に及ぶこともあります。
膝の腫れ
靱帯が損傷すると、関節内で出血や炎症が起こり、膝が腫れることがあります。特に前十字靱帯を損傷した場合は、受傷から数時間以内に膝全体が大きく腫れ上がるケースが多く見られます。これは関節内に血液(関節血腫)がたまることによるもので、急激な腫れと熱感を伴うのが特徴です。一方、後十字靱帯や側副靱帯などでは、腫れがそれほど目立たないこともありますが、膝の奥や特定の部位に限局した腫れが出ることもあります。腫れは痛みや関節の可動域の制限にもつながり、その後のリハビリにも影響を及ぼすため、初期段階での適切な対応(アイシングや圧迫など)が重要です。
関節の不安定感や動きの制限
靱帯は関節を安定させる役割を担っているため、損傷すると膝のぐらつきや、力が入らないような不安定感が現れます。例えば、前十字靱帯損傷では「膝が抜けるような感覚(膝くずれ)」が特徴的で、特に方向転換やジャンプの着地時に顕著になります。また、関節の腫れや痛みにより、膝の可動域が制限されることもあります。膝を十分に伸ばせなかったり、曲げようとしても途中で痛みが強くなって止まってしまうことがあります。これにより、スポーツはもちろん、階段の上り下りや立ち座りといった日常動作にも支障をきたすようになります。靱帯の損傷の程度によっては、症状が軽い場合もありますが、見た目以上に関節内部の損傷が進行しているケースもあるため、軽視せずに医療機関での評価が必要です。
歩行障がい
膝の痛みや腫れ、関節の不安定さが合わさることで、通常の歩行動作が困難になります。初期段階では膝に体重をかけることができず、引きずるような歩き方になったり、片足をかばって不自然な歩き方になることがあります。損傷が重度の場合は、膝が安定しないために何度もつまずいたり、急に膝が崩れるような感覚を繰り返すこともあります。また、関節がうまく動かせないことで、足を完全に伸ばしたり曲げたりできず、歩行がぎこちなくなります。痛みや腫れの軽減と並行して、適切なタイミングでのリハビリや筋力回復トレーニングを行わないと、長期的に歩行機能に悪影響が残る可能性もあるため注意が必要です。
膝靭帯損傷を早く治すならクリニックでの治療がおすすめ
 膝靭帯損傷の疑いがある場合、放置せずに速やかにクリニックで治療を受けることをおすすめします。
膝靭帯損傷の疑いがある場合、放置せずに速やかにクリニックで治療を受けることをおすすめします。
受診されるクリニックは整形外科がよいでしょう。早く治すためには整形外科でしっかり治療をおこなうことが重要です。整形外科の医師は膝靭帯損傷の専門医となるため、正しい治療を受けられるでしょう。
次は、クリニックで膝靭帯損傷を早く治す治療法について解説していきます。

膝靭帯損傷を早く治すための治療方法
 膝靭帯の損傷を早く治すためには、整形外科にて適切な治療をおこなう必要があります。
膝靭帯の損傷を早く治すためには、整形外科にて適切な治療をおこなう必要があります。
しかし、どのような治療をおこなうのか不安な方もいるでしょう。まずは、膝靭帯を損傷した場合の治療方法からお伝えします。
治療方法は大きく分けて次の2つがあります。
- 保存療法
- 手術療法
手術療法はイメージがわく方も多いでしょう。しかし、保存療法と聞いてもなかなかイメージできない方が多いのではないでしょうか。
そこで次は、2つの治療法について詳しく解説していきます。
保存療法
保存療法は手術をおこなわないで膝靭帯の損傷を治療していく方法です。損傷が軽度で日常生活に支障が少ないと判断された場合、保存療法で様子をみます。
保存療法の具体的な治療方法は次の2つです。
- サポーターの装着
- リハビリ
ただし、損傷した靭帯は自然に元に戻ることはないため、保存療法では完治しにくいといえます。あくまでも、リハビリで筋力をつけたりサポーターで膝を固定したりするサポートだと考えておくとよいでしょう。
サポーターの装着
膝靭帯損傷で保存療法が選ばれた場合、サポーターで膝を固定する方法があります。サポーターで膝を固定し不安定になった膝を支えます。
保存療法の目的は、膝を装具で固定しながら筋力をつけていくことです。損傷した膝の靭帯を筋力でサポートするためです。ある程度の筋力がつくまで装具で固定されるとよいでしょう。
サポーターにはいろいろな種類があり、膝靭帯損傷の状態によって適切なものを選ぶことが大切です。
リハビリ
保存療法のもうひとつにリハビリがあります。リハビリをおこなうことで筋力がつき、膝靭帯をサポートします。ただし、リハビリはケガをしてすぐにはおこないません。
なぜなら、早い段階で膝に負荷をかけると炎症が悪化する恐れがあるからです。そのため、リハビリはある程度の時間が経過してからおこないます。リハビリされるまでは膝の腫れの治療をしたり、痛みの経過をみたりして経過を観察します。
膝の腫れや痛みの状態がよくなったらリハビリを始めますが、膝の負担が軽減するようサポーターや固定具などを装着しておこなうとよいでしょう。
手術療法
膝靭帯の損傷が激しい場合、保存療法ではなく手術療法が選ばれることが多くなります。とくに前十字靭帯損傷の場合、保存療法での回復は難しいため、手術療法での治療が一般的です。なぜなら、膝靭帯損傷を繰り返さないためです。
スポーツしている方で前十字靭帯損傷と診断されたら、復帰は遅くなりますが、手術療法を選ぶ方がより早く治す近道となるでしょう。
膝靭帯損傷を早く治すためにクリニックで治療を受けた方がよいケース
 基本的に膝靭帯を損傷したら早急にクリニックの受診をおすすめしますが、とくに治療を受けた方がよいケースがあります。
基本的に膝靭帯を損傷したら早急にクリニックの受診をおすすめしますが、とくに治療を受けた方がよいケースがあります。
次のケースが該当します。
- 歩けない場合
- 屈伸ができない場合
- 膝を動かすと痛みがある場合
上記3つは膝靭帯損傷のなかでも重症の可能性があるため、早く治すためにもクリニックの受診が不可欠です。
歩けない場合
膝靭帯損傷でケガの直後から歩けない場合、早めのクリニックの受診が望ましいです。受傷後に歩けない場合、前十字靱帯損傷のような重症の可能性があります。
前述したとおり、前十字靱帯損傷の場合は保存療法での治療は期待できないため、医師による診断と正しい治療が大切です。早く治すためにも、歩けないほどの痛みを感じたらクリニックの受診をおすすめします。
屈伸ができない場合
屈伸ができない場合も注意が必要なため、ただちにクリニックを受診した方がよいでしょう。後十字靭帯損傷の疑いがあります。
後十字靭帯損傷は前述したとおり、スポーツで膝を強く打ったり膝が曲がった状態で転倒したりすると起こりやすいため、屈伸が困難になることがあります。
また、膝を強打した場合、半月板や膝のお皿も負傷している可能性があります。すぐにクリニックを受診し、同時に複数の箇所が負傷していないか診断してもらうことが早く治すためのポイントです。
膝を動かすと痛みがある場合
膝を動かした際に痛みを感じる場合、膝内側側副靭帯損傷の可能性があります。膝内側側副靭帯損傷はもっとも起こりやすい膝靭帯損傷であり、捻挫と勘違いしやすい特徴があります。
捻挫だと思って治療を怠ると重症化しやすいため、膝を動かすと痛みを感じる場合は早めにクリニックを受診されるとよいでしょう。
膝靭帯損傷を早く治すために効果的な食事方法
 膝靭帯損傷の回復には食事にも気をつける必要があります。食事によって膝靭帯が治ることはありませんが、靭帯の構成に必要不可欠な成分を食事によって摂取できるからです。
膝靭帯損傷の回復には食事にも気をつける必要があります。食事によって膝靭帯が治ることはありませんが、靭帯の構成に必要不可欠な成分を食事によって摂取できるからです。
代表例は次のとおりです。
- コラーゲン
- タンパク質
- ビタミン
上記の栄養素を積極的に摂るとよいでしょう。
次は上記の成分が必要な理由と多く含む食品を解説していきます。
コラーゲンが多い食品を摂取
靭帯損傷にコラーゲンがよい理由は、靭帯の主成分がコラーゲンでできているからです。ほかにはアキレス腱にも同じことがいえます。靭帯やアキレス腱のように筋肉と骨をつないでいる部分はコラーゲンが必要不可欠です。
コラーゲンを多く含む食材の例は次のとおりです。
- 豚足
- 鶏軟骨や鶏皮
- 牛すじ
- エビやカニ
上記の食材は日常的にも摂取しやすいため、積極的に食べることをおすすめします。
タンパク質やビタミンを摂取
靭帯をつくる主成分はコラーゲンであるとお伝えしましたが、コラーゲンの生成に必要な成分があります。具体的にはタンパク質やビタミンCがあげられます。コラーゲンと同時に摂取されると効率的でしょう。
では、タンパク質とビタミンCを多く含む食品はどのようなものがあるのでしょうか。
次の食品が代表例です。
【タンパク質】
- 肉
- 魚
- 牛乳やチーズ
- 卵
- 豆腐
- 納豆
【ビタミンC】
- アセロラ
- キウイフルーツ
- ゆず
- 赤ピーマン
- ブロッコリー
タンパク質もビタミンCも日常食品として馴染みのあるものばかりです。意識して食べるとよいでしょう。
膝靭帯損傷に関するよくある質問
 ここからは膝靭帯損傷に関するよくある質問に回答していきます。同じ疑問や不安がある方は、こちらの回答をぜひ参考にしてみてください。
ここからは膝靭帯損傷に関するよくある質問に回答していきます。同じ疑問や不安がある方は、こちらの回答をぜひ参考にしてみてください。
膝靭帯損傷しても歩けるのはどうして?
膝靭帯損傷した直後は痛みで歩けない場合が多いですが、時間が経過すると痛みや腫れが治まり歩けるようになります。
しかし、歩けるからといって治ったわけではないため注意が必要です。痛みがなくなっても、クリニックでしっかり診断してもらうとよいでしょう。
膝靭帯損傷は自然治癒できる?
膝靭帯損傷は自然に治ることはありません。通常、時間が経過すると痛みや腫れがひいて歩けるようになりますが、損傷した靭帯が治っているわけではありません。
治すには手術療法が必要になります。スポーツ復帰を望む方は手術をおすすめします。
靭帯損傷の治療ならシン・整形外科(旧東京ひざクリニック)がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
膝靭帯損傷を早く治すためには、クリニックで治療を受けることが大切です。
そこでおすすめするのは関節の痛み治療に特化したシン・整形外科(旧東京ひざクリニック)です。
シン・整形外科には、次のような特徴があります。
- 再生医療による痛み治療
- 整形外科の専門医が診察
- 安心の保証制度を用意
それぞれ詳しく解説するため、靭帯損傷がなかなか改善されない方はぜひチェックしてみてください。
再生医療による痛み治療
シン・整形外科は、膝や肘などの関節痛を再生医療で治療しています。
再生医療とは、自身の体から採集した細胞を培養して、損傷部位に注入する治療法で、人体に備わる再生能力を利用し損傷した組織の機能回復を図ります。
再生医療にもさまざまな種類があり、シン・整形外科では血液の血小板に含まれる成長因子を活用したPRP療法や、幹細胞を活用した幹細胞培養治療を採用しています。
どちらも日帰りで受けられほど体への負担は少く、痛みの根本的な改善が可能です。
症状が進行しているけど手術には抵抗がある方にもおすすめです。
整形外科の専門医が診察
シン・整形外科には、整形外科の専門医が在籍しており、丁寧に診察をおこないます。
再生医療における実績も豊富で、患者一人一人の症状にあわせた治療法を提案しています。
もちろん、再生医療が必要ない場合には再生医療以外の治療法も提案しているため、さまざまな選択肢から検討できるでしょう。
自身に適した治療法がわからない方は、ぜひ気軽に相談してみてください。
安心の保証制度を用意
シン・整形外科では、万が一に備えた2つの保証制度を設けています。
1つ目は、治療効果が得られなかった場合に、無料で1回分の治療を追加できる再治療保証です。
保証対象は幹細胞培養治療を2回以上受け、リハビリスタンダードコースを6か月以上継続した方で、治療開始から1年間適用となります。
とくに、ほかの治療で効果が得られず不安を感じている方には、上記の保証が安心できるポイントとなるでしょう。
2つ目は、再生医療による健康被害に備えて再生医療サポート保険に加入しているリスク保証です。
シン・整形外科が扱う再生医療は体の負担が少なく、高い効果が期待できますが、どのような治療でもトラブルがおこる可能性はゼロではありません。
その点、上記のような保証を用意し、不安を軽減しながら治療に取り組めます。
無料の電話相談を実施しているため、治療に関する不安や気になる点があればぜひ気軽に利用してみてください。
まとめ
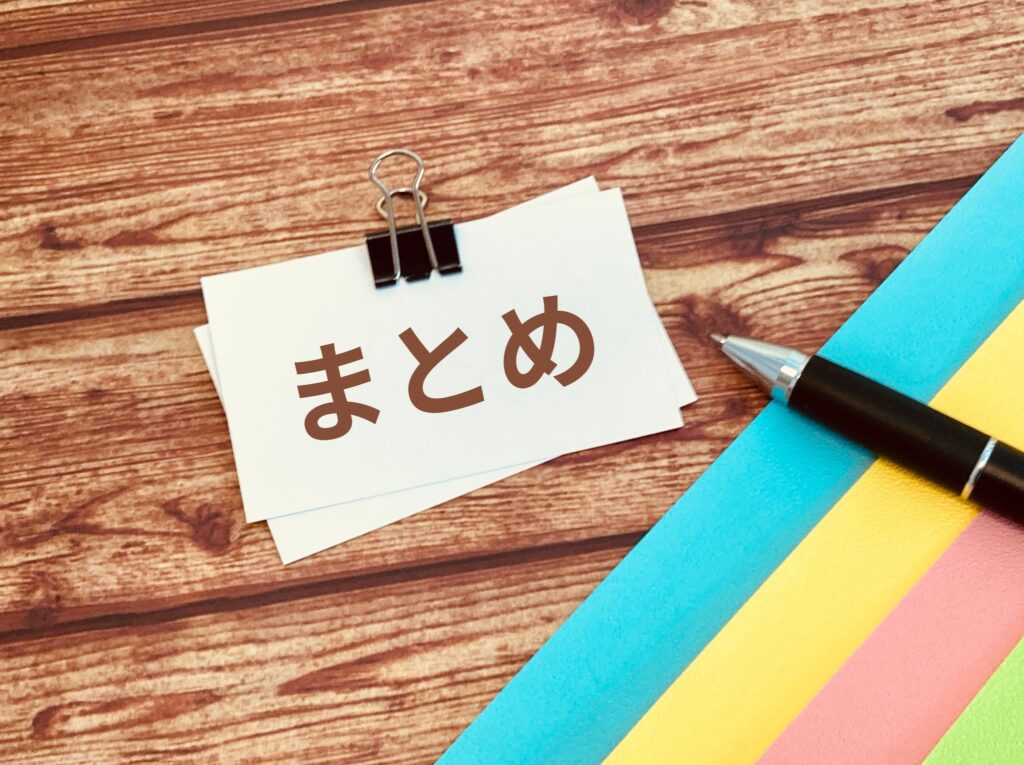 膝靭帯損傷は次の4つの種類があるとお伝えしました。
膝靭帯損傷は次の4つの種類があるとお伝えしました。
- 膝外側側副靱帯損傷
- 膝内側側副靭帯損傷
- 前十字靭帯損傷
- 後十字靭帯損傷
上記4つは損傷する原因や症状が異なるため、最適な治療法も異なります。
注意すべきは治療せずに放置することです。いずれも靭帯損傷は自然に治ることはないため、放置すると何度も膝靭帯損傷を繰り返したり後遺症が残ってしまったりするリスクが大きくなります。
軽度の症状であれば保存療法をおこなうことがありますが、症状が重い場合や前十字靭帯損傷の場合は手術療法をおすすめします。とくにスポーツ復帰したい方は、何度も繰り返さないためにもクリニックを受診して手術した方がよいでしょう。
膝靭帯損傷を早く治すためにも、医師の診断による正しい治療をぜひ検討してみてください。
※本記事の情報は2023年4月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。










