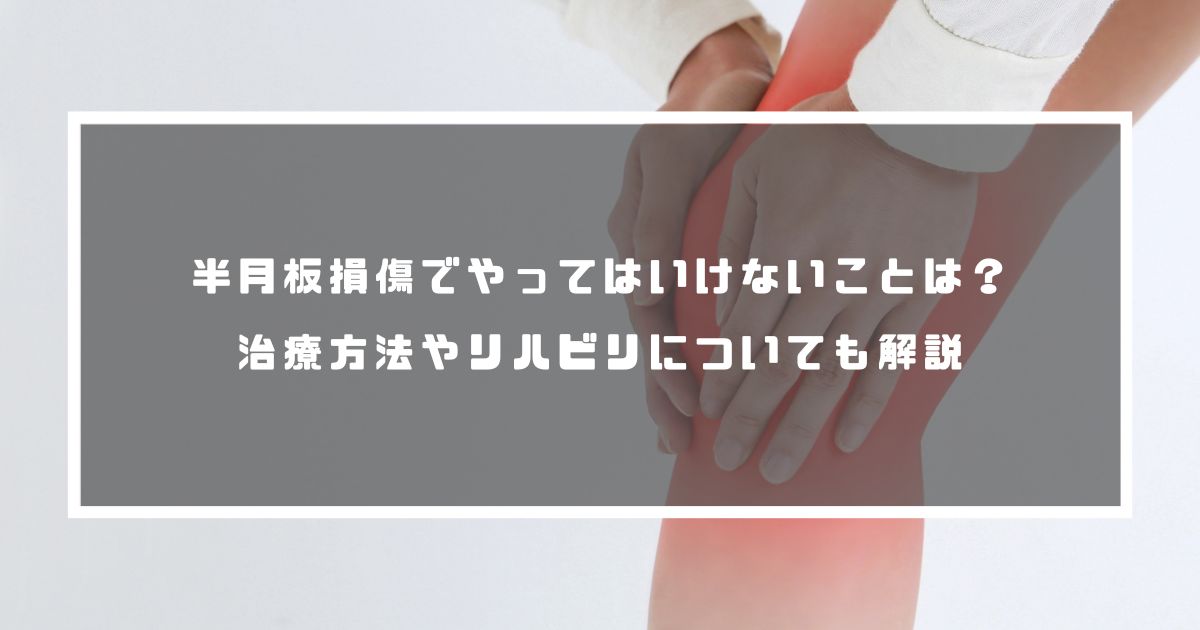半月板損傷でやってはいけないことや、どの程度の期間リハビリが必要なのかなどとお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
半月板損傷は、スポーツによる外傷や加齢が原因で生じる怪我です。放置しておくと痛みや違和感が悪化するのみでなく、変形性膝関節症に進行する恐れもあります。
本記事では、半月板損傷でやってはいけないことを解説するとともに、治療方法やリハビリについても詳しくまとめています。膝の痛みや違和感に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
半月板損傷とは?

半月板損傷とは、膝関節内にある半月板に亀裂が生じたり欠けたりする状態です。
半月板は膝関節の大腿骨と脛骨の間にある軟骨様の板で、内側と外側にそれぞれあり、膝関節を安定させる役割を果たしています。
半月板が損傷すると、膝を曲げ伸ばしする際に痛みや引っ掛かりを感じるようになり、症状が悪化すると膝に水が溜まってしまう場合もあります。
ここでは半月板の役割や症状、原因、検査と診断方法について解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
半月板の役割
半月板は、膝関節の中にある三日月型の軟骨組織で、内側と外側に1つずつ、合計2つあります。大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に位置し、膝のスムーズな動きを支える重要な役割を果たしています。
主な機能としては、まずが挙げられます。歩行や走行、ジャンプなどの動作によって膝にかかる衝撃をやわらげ、関節へのダメージを防ぎます。また、骨同士のかみ合わせを補正することでを高め、動作時のぐらつきを防ぐ役割も担っています。
さらに、半月板は膝関節内の圧力を分散させることで、関節軟骨の摩耗を防ぎ、変形性膝関節症などの進行を抑える効果もあります。加えて、関節内の潤滑液(滑液)を全体に行き渡らせる働きにより、関節の滑らかな動きを助けています。
このように、半月板は膝の機能を保つうえで非常に重要な組織であり、損傷すると痛みや可動域の制限、関節の不安定感などが生じることがあります。
半月板損傷の症状
半月板損傷の症状は、損傷の程度や部位によって異なりますが、いくつかの特徴的な症状があります。まず、膝の内側または外側に痛みを感じることが多く、損傷直後には強い痛みが出る場合もあります。慢性的な損傷では、鈍く重い痛みが続くこともあります。
膝の腫れもよく見られる症状の一つで、これは関節内に関節液がたまることで起こります。また、膝の動きに引っかかりを感じることがあり、症状が進行すると膝が途中で動かなくなる「ロッキング」と呼ばれる状態になることもあります。
さらに、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなったり、膝に不安定さを感じたりすることもあります。例えば、「ガクッ」と力が抜けるような感覚がある場合も半月板損傷が関係している可能性があります。特に階段の昇り降りやしゃがむ動作など、膝に負担がかかる動作で痛みが強くなる傾向があります。
半月板損傷の原因
半月板損傷の原因の多くは、スポーツでの外傷や加齢によるものです。
スポーツ外傷の例をあげると、バスケットボールやサッカーなどで体重がかかった状態で膝をひねり強い衝撃が加わることで半月板が損傷する場合があります。
スポーツに限らず交通事故や高所からの着地などで膝に強い衝撃が加わった際も、半月板が損傷する恐れがあります。半月板は加齢により劣化して傷つきやすくなります。
そのため半月板が劣化している高齢者の場合は、階段を昇り降りする日常動作でも損傷することがあります。
半月板の形に先天性の特徴がある場合、小児期でも半月板損傷が起こる可能性があります。
小児期から老年期に至るまでさまざまなライフステージの方に起こりうる疾患のため、膝の痛みや違和感があるときにはすぐに受診しましょう。
半月板損傷の検査と診断
半月板損傷の診断は、問診や身体診察を基に、必要に応じて画像検査を組み合わせて行われます。
まず医師は、痛みの部位や発症のきっかけ、症状の経過、どのような動作で痛みや違和感が生じるかなどを詳しく問診します。視診では、膝の腫れや歩き方の異常、関節の変形の有無などを確認します。
その後、徒手検査(理学的検査)と呼ばれる、膝を実際に動かしながら行う診察が行われます。代表的なものに「マクマレーテスト」や「アプレー圧迫テスト」があり、膝を曲げたり回したりして痛みや異音の有無を調べ、半月板損傷の可能性を評価します。
半月板はレントゲンには写らないため、詳細な診断にはMRI検査が有効です。MRIでは軟骨や靭帯などの軟部組織まで詳しく映し出すことができ、損傷の有無やその程度、部位を正確に把握できます。これにより、保存療法が可能か、手術が必要かなど、治療方針の決定に役立ちます。
また、レントゲン検査(X線)も併せて行われることがあります。これは半月板自体を見るためではなく、骨折や関節の変形の有無など、膝関節全体の状態を確認する目的で使用されます。
診断が難しい場合や手術を検討する際には、関節鏡検査が行われることもあります。これは、細いカメラを膝関節内に挿入し、実際に関節内部を直接観察する方法で、必要に応じてそのまま治療(半月板の縫合や切除)を行うこともできます。
半月板損傷したときにやってはいけないこと

半月板を損傷したときに、やってはいけないことが3つあります。
- 放置
- 膝に負荷のかかる行為やトレーニング
- 無理なストレッチ
上記の3つの行為は症状を悪化させるのはもちろんのこと、他の疾患を引き起こす恐れもあります。
ここではそれぞれの詳しい理由を解説するため、ぜひチェックしておいてください。
放置
半月板損傷を長期間放置しておくと、痛みや水腫が慢性化し、接触している大腿骨と脛骨の関節軟骨に傷がつきます。
さらに症状が悪化すると、膝関節の軟骨のすり減りや関節の変形が起こる変形性膝関節症へと進行するため注意が必要です。
症状の進行や変形性膝関節症の発症を防ぐためには、放置せずに治療をおこなう必要があります。
半月板損傷は構造的な怪我のため、放置していても自然治癒はありません。
膝に痛みや違和感が生じた際は、放置せずに整形外科や接骨院を受診しましょう。
膝に負荷のかかる行為、トレーニング
半月板損傷をした場合、膝に強い負荷がかかる動作やトレーニングは避けることが非常に重要です。無理に運動を続けることで、損傷が広がったり、炎症や痛みが悪化したりする危険性があります。特に注意すべきなのは、スクワットやジャンプなどの膝を深く曲げる動作、ランニングや階段の昇り降りといった繰り返しの衝撃が加わる運動、そして方向転換やひねりを伴う動きです。これらの動作は、半月板に圧力やねじれの力を加えるため、損傷部分にさらなるダメージを与えるおそれがあります。
また、痛みが軽減したからといって自己判断でトレーニングを再開するのは危険です。症状が一時的に落ち着いても、内部で損傷が進行している場合もあり、気づかないうちに慢性化することがあります。最悪の場合、関節軟骨にも影響が及び、将来的に変形性膝関節症へと進行するリスクもあります。
無理なストレッチ
半月板損傷をしているときに、自己判断で無理なストレッチを行うことは非常に危険です。ストレッチは本来、筋肉や関節の柔軟性を高めるのに有効ですが、損傷した半月板に対しては、誤った方法で行うと逆効果になることがあります。特に、膝を深く曲げたり、ひねったりしながら伸ばすような動作は、半月板に強い圧力やねじれの力を加え、損傷をさらに悪化させる原因となります。
たとえば、「痛気持ちいい」と感じる程度で伸ばしているつもりでも、実際には半月板の裂け目が広がっていたり、内部で炎症が強まっていたりすることがあります。その結果、痛みの増加や腫れ、ロッキング(膝が引っかかって動かなくなる)といった症状がひどくなることも少なくありません。
また、インターネットや動画サイトなどで紹介されている一般的なストレッチ方法をそのまま取り入れてしまう人も多いですが、これらは健康な膝を前提としていることがほとんどです。半月板を損傷している場合には適さない動きも多いため、注意が必要です。
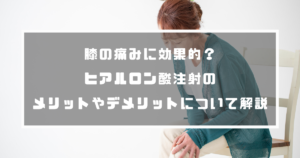
半月板損傷の治療方法

半月板損傷の治療方法は主に2種類、保存療法と手術があります。
ここでは、それぞれの治療方法について詳しく解説します。
保存療法
半月板損傷の治療方法の一つである保存療法は、比較的軽度の損傷や自然治癒が期待できる場合に選ばれる治療法です。この方法では、まず膝にかかる負担を減らすために安静を保ち、運動や膝を曲げ伸ばしする動作を制限します。痛みや炎症を抑えるために、アイシング(冷却)や消炎鎮痛剤の使用も行われます。これにより、膝の腫れや痛みを和らげることができます。
また、症状が落ち着いてきた段階では、理学療法士の指導のもとでリハビリテーションを開始し、膝を支える筋肉の強化や関節の可動域の改善を目指します。特に太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝関節への負担を軽減し、安定性を高める効果があります。場合によっては、膝の動きをサポートする装具やサポーターを使用して、日常生活での再損傷を防ぐこともあります。
保存療法は、痛みが軽くて日常生活に大きな支障がない場合や、損傷が血流の多い部分にあるため自然治癒が期待できるケースに適しています。しかし、治療を続けても症状が改善しない場合や、膝の痛みや機能障害が悪化する場合は、手術療法を検討する必要があります。そのため、保存療法中も定期的に医師の診察を受け、状態をしっかりと観察しながら治療を進めることが大切です。
手術
半月板損傷に対する手術療法は、保存療法では症状が改善しない場合や、損傷の程度が重く日常生活に支障をきたすケースにおいて選択される治療法です。特に、膝に強い痛みや引っかかり(ロッキング)などの症状がある場合、または損傷が自然治癒しにくい血流の乏しい「白色帯」に及んでいる場合には、手術が有効と判断されることが多くなります。
主な手術方法には、「半月板部分切除術」と「半月板縫合術」があります。部分切除術では、損傷した部分を切り取り、半月板の形状を整えることで痛みや症状を改善します。比較的短時間で済み、術後の回復も早いのが特徴ですが、切除範囲が広いと膝の関節軟骨にかかる負担が増え、将来的に変形性膝関節症を引き起こすリスクがあります。一方、縫合術は裂けた半月板を縫い合わせて自然な構造を保つ方法で、膝の機能維持に優れています。ただし、回復には時間がかかり、術後のリハビリも慎重に進める必要があります。
このほか、非常に限られたケースでは「半月板移植術」が行われることもあります。これは広範囲に損傷した半月板の代わりに他人の半月板を移植する手術で、国内ではあまり一般的ではありません。
どの手術を選択するかは、損傷の場所や大きさ、年齢、生活スタイル、活動レベルなどを総合的に判断して決定されます。手術後は医師の指導のもとでリハビリを行い、関節の機能回復を目指します。手術療法は、痛みの軽減と機能の改善を図る有効な手段であり、将来的な膝の健康を守るためにも、専門医との十分な相談のうえで治療方針を決めることが重要です。
半月板損傷のリハビリ

半月板損傷のリハビリにはいくつかの方法があります。
- 関節可動域訓練
- 筋力トレーニング
- バランストレーニング
- ウォーキング
- アスレチックリハビリテーション
ここでは上記5つのリハビリ方法について、それぞれ詳しく解説します。
関節可動域訓練
関節可動域訓練(ROM訓練)は非常に重要です。これは、膝関節の動きを回復させ、拘縮を予防し、日常生活や運動機能を取り戻すために行われます。訓練内容は回復の段階に応じて段階的に進める必要があります。
受傷直後の急性期(1週間程度)は、痛みや腫れの管理が最優先となり、膝を無理に動かすことは避けます。ただし、軽度の他動的な屈伸運動や、足首の運動などを行い、関節の固まりや血流の低下を防ぎます。
回復期(1~6週目)には、徐々に自分の力で膝を動かす自動運動へ移行します。壁を使ったヒールスライドやタオルを用いた膝の屈伸運動、自転車こぎなどを行い、膝の可動域を少しずつ広げていきます。痛みが強い場合は運動を中止し、無理をしないことが大切です。
その後の筋力強化期(6週以降)には、関節可動域を完全に回復させるとともに、筋力トレーニングや機能的な動作の習得を目指します。この段階では、ストレッチや全可動域での膝運動、スクワットやランジなども取り入れられます。ただし、再負傷やロック感などが見られる場合には、専門家の判断を仰ぐ必要があります。
筋力トレーニング
筋力トレーニングは関節の安定性を高め、再発防止や日常生活への復帰、さらにはスポーツ復帰を目指す上で欠かせない要素です。ただし、損傷の程度や治療内容(保存療法か手術か)、回復段階によってトレーニングの内容や強度を適切に調整する必要があります。
リハビリ初期(おおよそ2~4週目)では、まだ膝に大きな負荷をかけることは避け、主に自重を使った軽度の運動が中心になります。具体的には、大腿四頭筋の等尺性収縮(膝を動かさず力を入れる)、ヒールスライド(膝の曲げ伸ばし運動)、ストレートレッグレイズ(膝を伸ばしたまま脚を持ち上げる運動)、およびブリッジ運動(仰向けで腰を持ち上げる)が代表的です。
中期(4〜8週目)になると、膝の可動域が広がり、痛みが軽減してきたタイミングで、少しずつ負荷を増やすことが可能になります。軽負荷のレッグプレスや、深くしゃがみすぎないミニスクワット(30〜45度)、カーフレイズ(かかと上げ運動)、そしてゴムチューブを使った膝の伸展運動などが推奨されます。
後期(8週以降)には、より本格的な筋力強化と動作トレーニングに移行します。深めのスクワットやランジ、片脚でのスクワット、さらにはバランスディスク上でのトレーニングを取り入れることで、膝周囲の筋力だけでなくバランス感覚や協調性も養われます。最終段階ではジャンプやステップ動作など、実践的な動きも取り入れられるようになります。
なお、運動中や運動後に痛みや腫れが出た場合はすぐに中止し、適切な処置(アイシングや休息)を行うことが大切です。また、運動フォームが崩れると膝に過度な負荷がかかるため、トレーニングは常に正しい姿勢で行うことが重要です。
特に半月板縫合術後など、術後の回復過程にある場合は、膝に強い負担をかける運動は主治医や理学療法士の許可が出るまで控える必要があります。段階的かつ無理のない計画でトレーニングを進めることが、安全で効果的なリハビリの鍵となります。
バランストレーニング
関節の可動域回復や筋力強化に加えて、バランストレーニングが非常に重要です。膝関節は体重を支えるだけでなく、姿勢の制御や動作の安定にも関与しているため、バランス能力の低下は再受傷のリスクを高めます。特にスポーツ復帰を目指す場合や不安定感が残るケースでは、バランス訓練を段階的に取り入れることが勧められます。
リハビリの初期段階では、まず両脚での立位保持や、片脚立ち(支持脚を患側に)といったシンプルな動作から始めます。慣れてきたら、目を閉じて行ったり、不安定な床(タオルやエアクッション)で行ったりすることで、感覚入力を高めていきます。これにより、膝周囲の筋肉や関節をコントロールする固有感覚(位置感覚)が鍛えられます。
回復が進んだ中期以降は、バランスディスクやバランスボード、BOSUボールなどを使用したトレーニングも取り入れることが可能です。また、片脚でスクワットを行う、左右に重心移動する、体幹をひねりながら立位を保つなど、動的な要素を加えることで、より実践的なバランス能力を養うことができます。
さらに、スポーツ復帰を視野に入れた後期では、ジャンプ着地、ステップ動作、切り返し動作にバランスを組み合わせた複合トレーニングが必要になります。これにより、急な動きにも対応できる膝の安定性が身につき、ケガの再発防止につながります。
バランストレーニングは一見地味に見えますが、関節を守るうえで非常に重要な役割を果たします。実施にあたっては、無理のない範囲で、左右差やふらつきに注意しながら行うことがポイントです。必要に応じて理学療法士の指導を受けながら、正しい姿勢と安全な方法で進めることが望ましいでしょう。
ウォーキング
関節の動きを自然に促し、筋力やバランス感覚の向上、血流の改善、日常生活動作への復帰を助ける役割があります。ただし、損傷の程度や治療法(保存療法・切除術・縫合術など)、術後の経過に応じて、歩行のタイミングや方法を慎重に進める必要があります。
初期の段階では、膝への荷重を制限しながら、杖や松葉杖を使用しての部分荷重歩行から始めることが一般的です。特に縫合術後などでは、医師の指示により数週間は全荷重を避けることがあります。炎症や痛みが落ち着き、可動域や筋力がある程度回復してから、全荷重でのウォーキング練習が段階的に許可されます。
歩行時は、姿勢や歩き方のクセに注意することが重要です。膝をかばうことで生じる不自然な歩行(跛行)は、別の部位に負担をかけたり、再発のリスクを高めたりします。正しい姿勢を意識し、足をまっすぐ前に出し、かかとから着地してつま先で蹴り出すという基本的な歩行パターンをゆっくり確認しながら行います。
回復期に入ったら、徐々に歩行距離や速度を増やすことが可能になります。平坦な道を短距離から始め、体力や膝の状態に応じて長時間の歩行や階段昇降、坂道などに挑戦していきます。また、必要に応じてトレッドミル(ウォーキングマシン)を使用することもありますが、速度や傾斜の設定には注意が必要です。
ウォーキング中に痛み、腫れ、膝の引っかかり感(ロッキング)などの症状が出た場合は、すぐに中止し、医師や理学療法士に相談することが大切です。運動後にはアイシングやストレッチを取り入れ、膝の状態を整えることも忘れてはいけません。
アスレチックリハビリテーション
半月板損傷に対するアスレチックリハビリテーションでは、損傷の程度や手術方法(縫合術か切除術か)、競技特性に応じて段階的にリハビリを進めることが重要です。リハビリは一般的に4つのフェーズに分かれます。
最初の急性期(術後〜2週間程度)では、炎症や痛みを抑えることを優先し、RICE処置や筋の軽い収縮運動、関節の可動域訓練が中心です。縫合術後は荷重や膝の屈曲に制限が設けられることがあります。
回復期(2〜6週)では、日常生活への復帰を目指し、筋力回復や可動域の拡大を図ります。エルゴメーターやチューブトレーニング、プールでの運動などが用いられ、徐々に荷重をかけた歩行訓練も始まります。
次の強化期(6〜12週)では、筋力やバランス能力を高め、基本的な動作の習得に取り組みます。スクワットや片脚でのトレーニング、段階的なジャンプ練習、軽いランニングなどが含まれます。
競技復帰期(3〜6か月)には、競技特有の動作(方向転換やアジリティドリル)を取り入れ、実戦形式のトレーニングを行います。パフォーマンステストや動作分析を通じて、再発リスクの評価と最終的な復帰判断が行われます。
また、定期的に関節の可動域、筋力、バランス能力、主観的な膝の状態を評価することが、安全な競技復帰のために不可欠です。
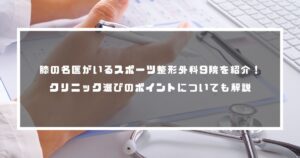
半月板損傷に関するよくある質問

半月板損傷に関するよくある質問をまとめました。半月板損傷について疑問を抱く方はぜひ参考にしてみてください。
半月板損傷は自然に治る?
損傷の場所や程度によって大きく異なります。半月板には血流が豊富な「レッドゾーン(外側1/3)」と、血流が乏しい「ホワイトゾーン(内側2/3)」があります。自然治癒が期待できるのは、主に血流のあるレッドゾーンに起きた軽度の損傷です。特に縦方向の小さな裂け目であれば、若年者やスポーツ選手でも保存療法(安静・運動制限・リハビリ)によって回復することがあります。
一方で、ホワイトゾーンの損傷や、複雑な断裂、フラップ状の損傷、水平方向の断裂などは、血流が届きにくく自己修復が困難です。こうした場合、自然に治る可能性は低く、放置すると膝の引っかかり感やロッキング、さらには変形性膝関節症へと進行するリスクがあります。そのため、症状が強い場合や損傷が大きい場合は、早期に手術や専門的なリハビリを検討する必要があります。
したがって、半月板損傷が自然に治るかどうかは一概には言えず、MRIなどの画像診断による正確な評価が不可欠です。適切な治療法を選ぶためには、損傷の部位、程度、年齢、活動レベルなどを総合的に判断することが重要です。
術後スポーツに復帰するまでにどのくらいかかる?
半月板損傷の手術後にスポーツへ復帰するまでの期間は、手術の方法や損傷の状態によって異なります。一般的に、損傷部分を部分的に切除する「部分切除術」の場合は、回復が比較的早く、術後6〜8週間ほどでスポーツ復帰が可能です。軽度であれば、4週間程度で軽い運動を再開できるケースもあります。
一方、損傷部分を縫って修復する「縫合術」の場合は、半月板の自然治癒を促す必要があるため、回復にはより長い時間がかかります。この場合、スポーツ復帰までには通常3〜6か月ほどを要し、場合によってはそれ以上かかることもあります。特に縫合術では、術後に膝への荷重や可動域に制限がかかるため、リハビリを慎重に段階的に進める必要があります。
また、復帰までの期間は損傷の程度や年齢、競技種目、リハビリの進行具合などにも影響されます。例えば、コンタクトスポーツや瞬発的な動作を伴う競技では、より慎重な復帰判断が求められます。スポーツ復帰にあたっては、筋力やバランス、ジャンプ動作などのパフォーマンステストを通じて、再発リスクを評価することが重要です。
半月板損傷の治療にはシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科の半月板損傷の治療は、以下の理由からおすすめです。
・専門知識と経験豊富な医師陣
・最新の医療技術
・安心の手術
・パーソナライズされたケア
専門知識と経験豊富な医師陣
シン整形外科は専門知識を持つ医師がいるため、患者の症状や状態について本質的な診断や治療プランを提供しています。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ

半月板損傷の治療方法やリハビリ方法について解説しました。半月板損傷でやってはいけないことは、放置したり膝に負荷のかかる行為やトレーニング、無理なストレッチです。
膝に痛みや違和感が生じたら、放置せず可能な限り早めに受診し、治療を開始しましょう。
※本記事の情報は2023年5月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。