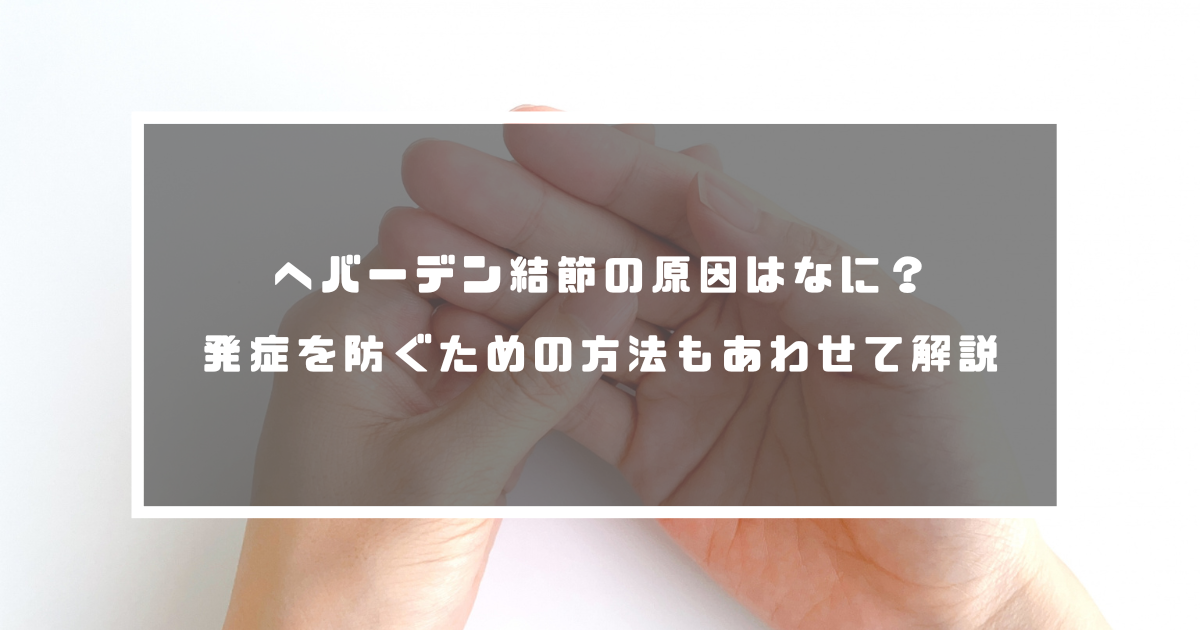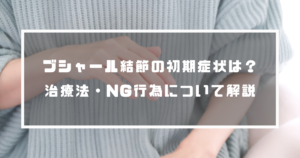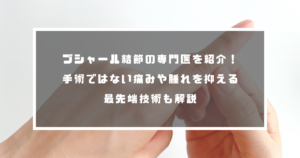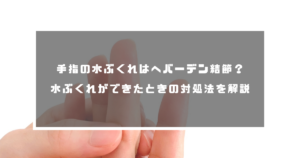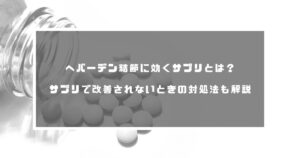指の第一関節に腫れや痛みを感じた場合、ヘバーデン結節を疑う女性も多いかもしれません。
へバーデン結節は手指の第一関節に腫れや痛みが生じ、次第に変形していく疾患ですが、原因は明らかにされていません。
ただし、中高齢の女性に多くみられるため、性別や年齢が発症に関係していると考えられています。
この記事では、へバーデン結節の発症に関係するとみられている要素や、へバーデン結節患者の共通点を紹介します。
あわせて、へバーデン結節の予防法も解説するため、へバーデン結節が疑われる症状がある方はぜひ参考にしてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない指へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
へバーデン結節の原因は明らかにされていない

指の第一関節に腫れや変形、屈曲を起こすヘバーデン結節(けっせつ)は、原因不明の疾患です。
ヘバーデン結節は、第一関節の手の甲側に関節を挟んで2つのコブができる点が特徴で、そのコブを結節(けっせつ)といいます。
親指から小指まですべての指に起こる可能性があり、複数の指に同時に起こる方も多くいます。
病気の発見者であるイギリスのヘバーデン(Heberden)医師にちなんで、ヘバーデン結節と呼ばれています。
ヘバーデン結節は、年齢に伴う変形性関節症の一つであることが分かっています。
変形性関節症とは、関節の表面を覆う軟膏が老化したり摩耗したりすることで、骨に直接負荷がかかり、骨が徐々に変形していく疾患です。
変形性関節症による骨の変形の程度は個人差があるため、すべての方に強い変形が起こるわけではありません。
指の第一関節に症状が起こる場合がヘバーデン結節であり、親指の付け根に起こると母指CM関節症、人差し指から小指までの第2関節に起こるとブシャール結節と呼ばれます。
ヘバーデン結節のはっきりとした原因は不明ですが、発症に関係しているのではないかと考えられている要素が次の3つです。
- 女性ホルモンの乱れ
- 遺伝性
- 外傷
それぞれ詳しく解説します。
女性ホルモンの乱れ
へバーデン結節は特に中高年以降の女性に多く見られる疾患であり、その背景には女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌量の変化が深く関わっていると考えられています。エストロゲンは、女性の身体のさまざまな機能を調整する重要なホルモンであり、骨や関節の健康を保つ役割も担っています。エストロゲンには、骨の代謝を調節する作用があるだけでなく、関節周囲の組織の炎症を抑える働きもあるとされています。しかし、閉経を迎える頃になると、このエストロゲンの分泌が急激に低下し、その影響で関節軟骨の変性が進みやすくなり、へバーデン結節のような関節の変形や痛みが起こりやすくなるのです。さらに、ホルモンバランスの乱れは血流や自律神経の働きにも影響を及ぼし、それが関節の回復力の低下や痛みの慢性化につながる可能性もあります。そのため、更年期以降の女性がへバーデン結節を発症しやすいのは、単に加齢の影響だけではなく、ホルモンの分泌変化という内分泌的な要因も大きく関係していると考えられています。
遺伝性
へバーデン結節は、遺伝的な要素も強く影響するとされています。実際に、親や祖父母にへバーデン結節を発症した人がいる場合、その子や孫の世代でも同じように発症するケースが多く見られます。この遺伝性は、関節自体の構造や軟骨の強度、炎症に対する反応のしやすさなど、生まれつきの体質に由来すると考えられます。また、関節を構成するコラーゲンの質や再生能力、細胞の老化速度にも個人差があり、それらも遺伝的な影響を受けるとされています。加えて、ホルモンの感受性にも遺伝要因が関わっており、同じように女性ホルモンが減少しても、ある人は発症しやすく、ある人は発症しにくいといった個人差が出る理由にもなっています。つまり、遺伝的に関節が弱かったり、炎症が起こりやすい体質の人は、環境や生活習慣による影響が加わることで、より高い確率でへバーデン結節を発症する傾向があります。家族に似たような指の変形が見られる場合は、自分にも同様のリスクがあると認識し、予防や早期の対応を心がけることが重要です。
外傷によるもの
へバーデン結節の発症には、日常生活や仕事などで指先の関節に長年かかり続ける負荷や、繰り返される微細な外傷も大きく関係していると考えられています。例えば、パソコン作業やピアノ演奏、細かい手作業を長時間行う人、あるいは重い荷物を持つことが多い職業の人などは、知らず知らずのうちに指の第一関節に負担をかけ続けています。このような継続的なストレスや圧力は、関節の軟骨や滑膜に微細な損傷をもたらし、それが積み重なることで関節の変形を引き起こし、へバーデン結節へとつながっていきます。また、過去に指を強く打ったり、突き指や骨折などの外傷を経験したことがある人も、関節にダメージが蓄積している可能性があり、発症リスクが高まるとされています。特に年齢を重ねて関節の修復力が落ちてくると、こうした損傷からの回復が遅れ、変形が進行しやすくなるため注意が必要です。関節の使いすぎや過度な負荷は自覚しづらいため、予防としては、休息をしっかりとることや、関節に負担をかけすぎない作業の工夫が重要になります。
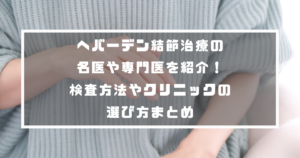
へバーデン結節患者の共通点

ヘバーデン結節の原因は特定されていませんが、患者に次のような共通点があると報告されています。
- 40代以降の女性に多い
- 日常的に手指を使用している
- 甘いものを好んで食べる
- 加工食品やレトルト食品をよく食べる
一つずつ詳しく紹介します。
40代以降の女性に多い
へバーデン結節は、特に40代から60代の中高年の女性に多く見られる疾患です。この年代になると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が徐々に減少し始めます。エストロゲンには関節の健康を保つ働きがあるとされており、その減少により関節の老化や変形が進みやすくなると考えられています。特に閉経前後はホルモンバランスが大きく変化し、それに伴って指の関節にも負担がかかるようになります。そのため、同年代の女性の間でへバーデン結節を発症するケースが多く報告されています。
日常的に手指を使用している
手指を頻繁に使う職業や家事を長年続けている人ほど、へバーデン結節を発症するリスクが高いとされています。たとえばパソコンのキーボードを使ったデスクワークや、手作業を伴う仕事、家事において繰り返しの動作を続けることが、指の関節に慢性的な負荷をかけてしまう原因になります。特に親指や人差し指、中指など、よく使う指に症状が出やすい傾向があります。過度な使用によって指関節の軟骨がすり減り、変形が進行していくのです。
甘いものを好んで食べる
甘いお菓子や砂糖を多く含む飲料を日常的に摂取している人は、へバーデン結節を悪化させる可能性があります。糖分の過剰摂取は血糖値の上昇を招き、体内で炎症反応を起こしやすくなることが分かっています。慢性的な炎症状態が続くと、関節の痛みや腫れが悪化することがあります。さらに、糖分を多く摂ると体内のコラーゲンが糖化しやすくなり、関節の柔軟性が失われるとも言われています。そのため、甘いものが好きな人は関節への影響にも注意が必要です。
加工食品やレトルト食品をよく食べる
へバーデン結節の患者によく見られる共通点の一つとして、加工食品やレトルト食品を頻繁に摂取しているという点が挙げられます。これらの食品には、保存料や化学調味料、着色料、安定剤などの添加物が多く含まれており、これらの物質が体内での炎症反応を助長し、関節の健康に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。さらに、加工食品は栄養バランスが偏っていることが多く、ビタミンやミネラル、特に関節の修復や炎症の抑制に関わる栄養素が不足しがちです。その結果、手指の関節に負担がかかり、変形や痛みを引き起こしやすくなると考えられています。また、これらの食品に含まれるトランス脂肪酸や過剰な塩分、糖分も、慢性的な炎症を引き起こす一因となるため、食生活の見直しはへバーデン結節の予防や症状の軽減にとって重要なポイントといえるでしょう。
へバーデン結節の症状

ヘバーデン結節で起こる一般的な症状は、次のとおりです。
- 第一関節の痛み
- 腫れや皮膚の赤み
- 粘液嚢腫(ミューカスシスト)
- 第一関節の変形
- 強く握れない
- 指の動きが悪くなる
一つずつ解説します。
第一関節の痛み
ヘバーデン結節の代表的な症状は、ピリピリやチクチクと表現される第一関節の痛みです。
ヘバーデン結節を発症すると、軟骨がすり減り、関節の隙間が狭くなります。
同時に関節を支える靱帯も緩み、関節が不安定になるため、結果として関節周囲の骨に負担がかかり、骨棘(骨のトゲ)が発生して痛みが生じます。
ヘバーデン結節による第一関節の痛みは、指を使うときに限りません。
じっとしているときでも起こる場合があります。
また、手をぶつけたときに激痛が走るように、痛みに過敏になる傾向があります。
腫れや皮膚の赤み
ヘバーデン結節では、指の第一関節の腫れや赤みも症状のひとつです。
ヘバーデン結節は、第一関節を挟んで2つのコブができる点が特徴ですが、このコブを結節といいます。
腫れや熱感があるときは患部の冷却や関節の安静が効果的です。
粘液嚢腫(ミューカスシスト)
粘液嚢腫とは、第一関節の手の甲側にできる水ぶくれで、ミューカスシストとも呼ばれます。
粘液嚢腫は第一関節の変形により、関節液が外に膨らんでいるもので、変形性膝関節症で膝に水が溜まる症状と同じ仕組みです。
粘液嚢腫は関節の袋とつながっているため、針を刺して水を抜くと細菌が入り感染するおそれがあります。
粘液嚢腫を自身で潰すことは避けてください。
第一関節の変形
ヘバーデン結節は、症状が出たり治まったりを繰り返す疾患です。
放置していると関節の炎症により関節を包んでいる袋が緩み、屈曲方向に曲がり始めます。
変形の程度には個人差がありますが、最終的に10年ほどかけて関節が変形します。
第一関節の変形は、複数の指に生じる傾向にあります。
またヘバーデン結節では関節のなめらかさも徐々に失わるため、関節の可動域が狭まり指が伸びきらない状態になります。
強く握れない
指のこわばりや第一関節の痛みにより、手を強く握れないこともヘバーデン結節の症状のひとつです。
包丁で堅いものが切れなかったり、ビンの蓋が開けられなかったりなど、日常生活で不便を感じるかもしれません。
ヘバーデン結節は関節を支える靱帯も緩むとされているため、指でものをつまむときに関節が不安定になり、指先の力が入りにくくなる場合もあります。
指の動きが悪くなる
ヘバーデン結節では腫れたコブの部分が第一関節を圧迫するため、指を曲げたり伸ばしたりする動きが難しくなる方もいます。
とくに指をまっすぐに伸ばしにくくなる方が多いようです。
箸を使った食事や食器洗い、キーボードのタイピングなどで不便を感じる場合もあるでしょう。

へバーデン結節にならないための予防法

ヘバーデン結節と遺伝との因果関係は明確にされていませんが、母や祖母がヘバーデン結節を発症している方は、予防することをおすすめします。
ヘバーデン結節の予防法には、次の3つが挙げられます。
- 栄養バランスの取れた食事を摂る
- 加工食品や甘いものを避ける
- 女性ホルモンのバランスを整える
上記のポイントはヘバーデン結節の症状軽減にもつながるため、すでに症状が出ている方にもおすすめです。
自身の生活に取り入れやすいことから、ぜひ実践してみてください。
栄養バランスの摂れた食事を摂る
ヘバーデン結節は肥満により悪化するといわれているため、栄養バランスの取れた食事で体重増加に気をつけましょう。
サバやイワシなどの青魚に含まれるDHAやEPAは、炎症を抑えるはたらきをサポートするといわれています。
また、アルコールは過剰摂取により血管を拡張させるため、ヘバーデン結節のズキズキとした痛みを増幅させるおそれがあります。
お酒の飲みすぎには注意が必要です。
加工食品や甘いものを避ける
加工食品や甘いものに多く含まれるトランス脂肪酸や糖分は、関節の周りに炎症を起こすことが分かっています。
トランス脂肪酸の摂取を控えるためには、油脂をオリーブオイルやココナッツオイルなど植物由来のものへの変更がおすすめです。
また糖分や糖質は甘いものばかりでなく、ご飯やパンなどの炭水化物にも含まれています。
毎食の主食の量を少し減らすと、糖質の摂りすぎを避けられるでしょう。
女性ホルモンのバランスを整える
ヘバーデン結節は女性ホルモンの乱れが関係していると考えられるため、女性ホルモンバランスを整えることは予防につながります。
女性ホルモンのエストロゲンに成分が似ていると注目されているのが、豆腐や味噌、納豆などの大豆製品に含まれる大豆イソフラボンです。
大豆イソフラボンを日常的に摂取すると、ヘバーデン結節の予防や症状改善につながる可能性があるといわれています。
また、エストロゲンの代謝を促進する効果のあるビタミンEやビタミンB6の摂取も、女性ホルモンバランスの正常化に効果的です。
エストロゲンに構造が似ている成分には、大豆イソフラボンの他にエクオールもあります。
大豆イソフラボンやエクオールに特化したサプリメントも販売されているため、サプリメントの摂取もひとつの方法です。
へバーデン結節の治療法

ヘバーデン結節は治療せずに放置していると骨の変形が進み、元に戻せなくなります。
第一関節で曲がってしまうため、できる限り早く治療を始めましょう。
ヘバーデン結節の治療法として挙げられるのは、次の4つです。
- 手術療法
- 薬物療法
- 保存的療法
- 再生医療
一つずつ解説します。
手術療法
ヘバーデン結節では、保存的療法で痛みが改善しない場合や変形が進み日常生活に支障をきたす場合に手術が検討されます。
ヘバーデン結節の手術は、関節形成術や関節固定術が一般的です。
関節形成術は、でっぱった骨や水ぶくれ(粘液嚢腫)を切除する手術法で、見た目の改善が期待できます。
関節固定術は、第一関節にスクリューネジを挿入し、前後の骨を固定してぐらつきを改善させる手術法です。
関節固定術は最も使いやすい位置で関節を固定するため、指を自由に曲げられなくなりますが、痛みはなくなります。
薬物療法
ヘバーデン結節の痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤の内服薬や、湿布や塗り薬などの外用薬を使います。
発症直後の急性期には、関節内へのステロイド注射も有効です。
ヘバーデン結節の進行を予防するためには、炎症を早期に沈静化させることが重要です。
大豆イソフラボンやエクオールなどの女性ホルモンのバランスを整えるサプリメントや、体調改善のための漢方の服用も検討されます。
保存的治療
ヘバーデン結節の保存的療法とは、局所のテーピングやサポーター、固定リング、アイシングなどです。
変形した関節では関節を支える靱帯が緩むため、不安定な状態になり軟骨がすり減りやすくなります。
テーピングやサポーターで関節を動かさないようにすると、痛みや腫れを軽減させられます。
再生医療
再生医療とは、血液や脂肪など自身の細胞を活用し体が本来持つ自己治癒力を高め、痛みを緩和したり損傷した部位を修復したりできる治療法です。
再生医療の中でも自身の血液を使うPRP療法は、膝や股関節、手指、肩、肘など人体のあらゆる関節が対象です。
PRP療法は血液を少量採取し、組織を修復する能力のある血小板を抽出してPRP(Platelet-rich plasma、多血小板血漿)を作り、患部に注射します。
PRP療法は、血小板の成長因子による痛んだ組織の修復や、関節の炎症軽減効果が期待できます。

へバーデン結節の治療はシン・整形外科の再生医療がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
へバーデン結節の治療に、保存的療法でも手術でもない第三の治療法、再生医療を検討してみませんか。
再生医療は入院の必要がなく、組織の修復も期待できる根本的な治療法です。
シン・整形外科は、PRP療法や肝細胞治療などの再生医療を専門的におこなうクリニックです。
日々痛みに悩まされている方のため、負担の少ない治療法で関節の痛みを取り除き、健康な毎日を送れるようサポートします。
再生医療に特化したクリニック
シン・整形外科は痛み除去と再生医療に特化しており、再生医療の実績が豊富です。
また、日本整形外科学会認定の専門医が正確な治療をおこないます。
丁寧な診察で、再生医療を含めたさまざまな治療法から、一人一人に合わせた最適な治療法を提案します。
手術を避けたい方も受けられる根本的な治療
再生医療は手術と異なり、メスを使わない体への負担の少ない治療法です。
手術は入院の必要があったり、体への負担が大きかったりするため、なかなか踏み切れない方も多いかもしれません。
PRP療法の場合、体への負担は採血とPRPを患部に注射するときの針を刺す痛みのみです。
また、へバーデン結節の保存的療法は内服薬や外用薬で痛みを緩和させるものであり、根本的な治療とはいえません。
一方、再生医療は痛みの緩和のみならず、損傷した部位の細胞の修復も期待できる治療法です。
注射のみの日帰り治療も可能
再生医療は、採血と注射のみの日帰りで受けられる治療です。
たとえば、PRP治療は初回の診察やリハビリを除けば、2回の通院で治療が受けられます。
PRP治療では、まず約100mlの血液を採取し、細胞加工施設へ送り、約3週間かけてPRPを調製します。
患者は採血から約3週間後に来院し、患部にPRPの注射を受けるのみであるため、入院の必要はありません。
安心できる保証制度
シン・整形外科では、患者が安心して治療を受けられる保証制度を設けています。
当院指定の治療メニューを契約された方で、治療効果が出なかった場合、追加で1回分を無償で提供します。
保証対象は次の2つの条件に当てはまる方です。
- 幹細胞培養治療を2回以上ご契約の方
- 当院のリハビリスタンダードコースを6か月以上継続した方
再生医療は自身の血液や脂肪を使用するためリスクの低い治療法とされます。
しかし、万が一再生医療で健康被害を受けた場合に備え、当院は再生医療サポート保険に加入しています。
まとめ
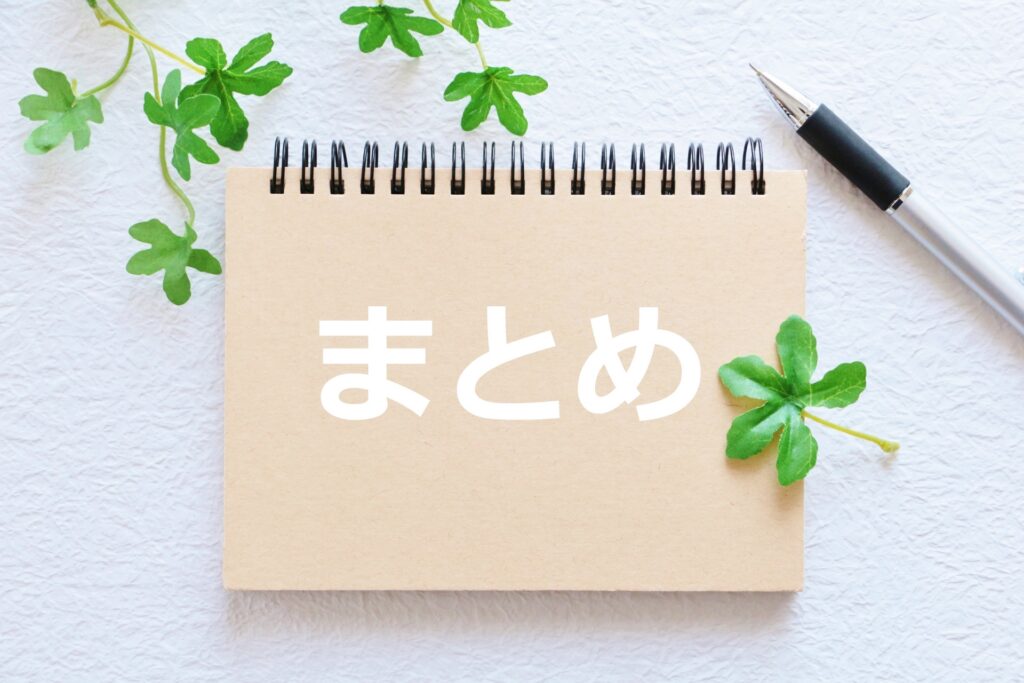
へバーデン結節は指の第一関節にコブができ、痛みや変形が起こる原因不明の疾患です。
はっきりした原因は分かっていませんが、更年期以降の女性に多くみられることから女性ホルモンの乱れが関係しているとみられています。
また、手指の使いすぎや肥満も発症に関係している可能性があることから、安静にしたり栄養バランスのとれた食事をとったりすることが予防になるでしょう。
へバーデン結節は変形性関節症の一種であり、再生医療で痛みの軽減や損傷部位の修復が期待できます。
再生医療なら実績豊富な専門クリニックであるシン・整形外科をぜひご検討ください。
<参考>
シン・整形外科