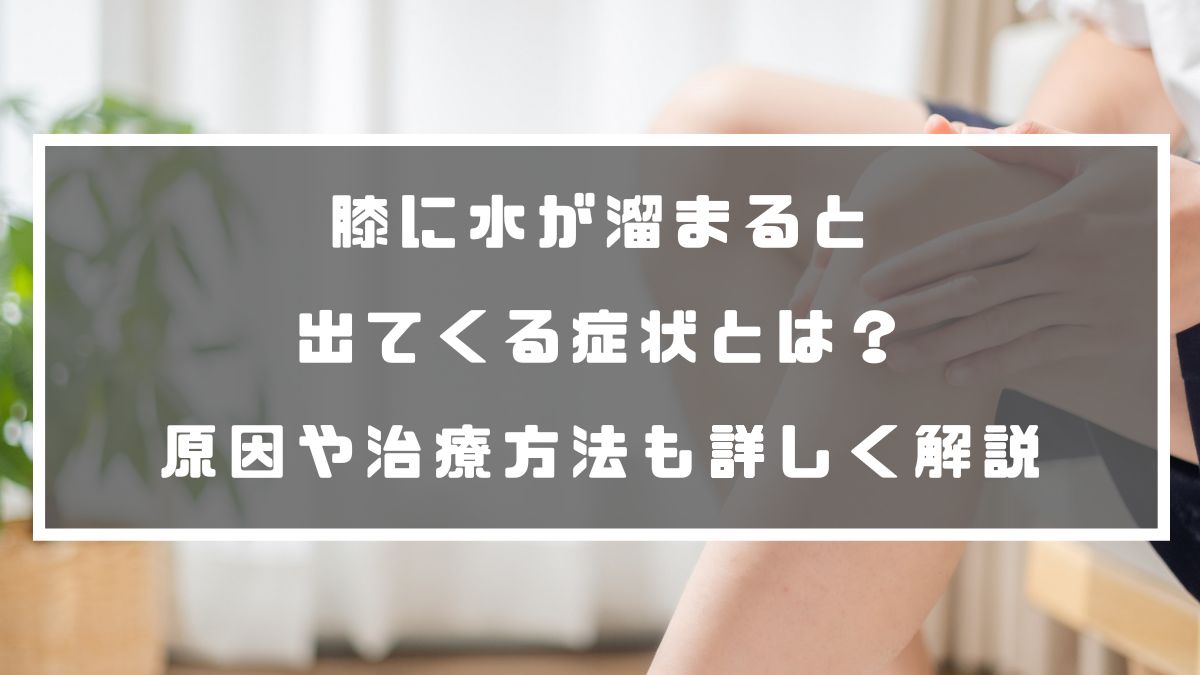膝が痛い、動かしにくいと違和感を覚えたときは、膝に水が溜まっている可能性があります。
膝に水が溜まる症状について耳にしたことはあっても、水が溜まる原因や放置するとどのようになるのか、知らない方も多いでしょう。
病院で膝に水が溜まっていると診断された場合は、水を抜く処置をしなければなりません。
この記事では、膝に水が溜まったときの症状や、治療法を紹介します。
また、膝に水が溜まった場合に自宅でできる改善策もあわせて紹介するため、膝に違和感がある方はぜひ参考にしてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
膝に水が溜まると出てくる症状

膝に水が溜まると、膝が痛い、腫れるなどの症状が見られます。自身に当てはまる症状がある場合、膝に水が溜まっている可能性が高いです。
早めに治療を開始するために、膝に水が溜まると出てくる主な症状から確認しておきましょう。
歩きはじめに膝が痛む
膝に水が溜まっていると、関節の内部で炎症が起きており、特に動き始めに痛みを感じやすくなります。安静にしていた後、歩き出す瞬間に膝がこわばったように感じたり、ズキッと痛みが走ることがあります。炎症によって関節周囲の組織が敏感になっているため、最初の動作に負担がかかりやすくなっています。

膝が腫れる
関節内に余分な関節液がたまると、膝が腫れて見えるようになります。左右の膝を見比べると、片方だけ明らかに膨らんでいることがあります。また、触るとぷよぷよと柔らかい感触があるのが特徴です。膝のお皿(膝蓋骨)の周囲が特に腫れやすくなります。
関節の曲げ伸ばしがしにくい
膝の中に水がたまると、関節内の圧力が高くなり、曲げたり伸ばしたりする動きがスムーズにできなくなります。しゃがむ、正座する、階段の上り下りといった動作が難しくなったり、動かすたびに引っかかるような違和感を覚えることがあります。
重だるく感じる
膝に水が溜まることで関節内の状態が不安定になり、膝そのものに重みを感じたり、だるさが続くことがあります。鋭い痛みとは異なり、じわじわとした不快感が長時間続くため、集中力や活動意欲にも影響を与えることがあります。

膝の関節を覆っている組織は、内側に滑膜があります。滑膜内部には関節液(滑液)と呼ばれる潤滑液で満たされた状態です。
関節の動きをサポートする液体
膝関節の中には本来、滑液(かつえき)と呼ばれる潤滑液が少量存在しています。この液体は関節の動きを滑らかにし、軟骨に栄養を届ける役割を果たしています。しかし、関節に炎症が起きるとこの滑液が過剰に分泌され、水が溜まった状態になります。本来は体にとって必要な液体ですが、過剰になると痛みや腫れの原因になります。
これらの症状がみられる場合には、膝に負担をかけすぎず、早めに医療機関で診察を受けることが大切です。
膝に水が溜まる原因

膝に水が溜まる原因は、軟骨の損傷や炎症、内出血が挙げられます。なぜ膝に水が溜まるのか、主な原因を3つ見ていきましょう。
軟骨に傷がついている
膝関節の軟骨は、骨と骨の間で衝撃を和らげるクッションのような役割を担っています。加齢や過度な運動、外傷などによってこの軟骨がすり減ったり、傷ついたりすると、関節内で摩擦が強くなり、関節液が多く分泌されるようになります。これは変形性膝関節症などでもよく見られる状態で、関節を守ろうとする反応として水が溜まります。
内出血が生じている
膝をぶつけたり、捻ったりすることで関節内に出血が起こると、その血液が刺激となって関節液の分泌が増えることがあります。とくに靭帯損傷や半月板損傷など、外傷に伴う内出血がある場合は、比較的短期間で膝が大きく腫れて水が溜まることがあります。外傷後に急に膝が腫れたときには、この内出血の可能性を考える必要があります。
炎症が起きている
関節の中で何らかの原因により炎症が起こると、それに反応して関節液が増え、水が溜まる状態になります。炎症の原因はさまざまで、変形性関節症や関節リウマチ、感染症などが含まれます。炎症が慢性的に続くと、何度も水が溜まりやすくなるため、根本的な病気の治療が必要になります。
膝に水が溜まる背景にはこのような身体の異常が隠れていることが多く、単に水を抜くだけでは再発する可能性があります。そのため、原因を正確に見極めたうえで、適切な治療を行うことが重要です。

膝に水が溜まる原因になりやすい怪我や病気
膝に水が溜まるのは、膝関節の内部に存在している滑膜に炎症を起こすためです。
滑膜に炎症を起こして、膝に水が溜まる原因になる怪我や病気の種類を紹介します。
変形性膝関節症
加齢や過度な負荷によって膝関節の軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれ合うようになることで、関節内に慢性的な炎症が起こります。この炎症によって関節液が増加し、水が溜まりやすくなります。初期の段階では軽い痛みやこわばり程度ですが、進行すると膝の腫れや変形、可動域の制限が顕著になり、水が頻繁に溜まるようになります。

半月板損傷
半月板は膝関節内にある軟骨組織で、衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。しかし、急なひねり動作や外傷によって損傷すると、関節内に出血や炎症が生じ、それが刺激となって水が溜まる原因になります。特にスポーツ中のケガや中高年の運動中のひねり動作で発生しやすく、損傷の程度によっては関節の引っかかり感や痛みを伴いながら、水が繰り返し溜まるようになります。

関節リウマチ
自己免疫の異常によって関節の内側にある滑膜が炎症を起こし、関節液が過剰に分泌されて水が溜まる病気です。関節リウマチは手指の小さな関節に始まることが多いものの、膝関節にも進行しやすく、関節の腫れ、熱感、こわばり、そして痛みが慢性的に続くのが特徴です。放置すると関節の破壊が進み、強い変形や機能障害を引き起こす可能性があります。
これらの怪我や病気は、いずれも関節内に物理的または免疫的な刺激を与えることで水が溜まる状態を引き起こします。膝に水が溜まるのは一時的な症状のように思われがちですが、その背後にはこのような深刻な問題が潜んでいることもあるため、早期の診断と治療が重要です。
膝に水が溜まる症状でクリニックを受診する目安

膝に水が溜まっても、いつクリニックで処置を受けるべきかの判断は難しいです。
どのタイミングでクリニックを受診すればよいのか、目安となる症状を紹介します。
痛みや腫れがある
膝に違和感がある程度であれば様子を見てもよい場合もありますが、明らかに腫れていたり、動かすと痛みが強くなるような場合は、関節内で炎症や損傷が進行している可能性があります。特に、押すとぶよぶよとした感触がある、熱を持っている、赤みがあるなどの症状があれば、診察を受けた方が安全です。
歩行がつらい
膝の痛みや不安定さによって日常生活に支障が出ている場合は、単なる一時的な不調ではない可能性が高くなります。歩くときに力が入らない、膝が抜けそうになる、階段の上り下りが困難になるといった症状は、関節内の異常を示しているサインです。
膝の痛みを繰り返している
一度良くなってもまた痛みがぶり返す、何度も腫れたり引いたりを繰り返しているといった場合は、関節の中に慢性的な問題があるかもしれません。変形性膝関節症や関節リウマチなどの慢性疾患が隠れている可能性もあるため、繰り返す症状には注意が必要です。
スポーツや事故のあとに痛む
運動中の捻挫や転倒、衝突などのあとに膝が腫れたり痛くなった場合は、半月板損傷や靭帯の損傷、内出血などが関係して水が溜まっていることがあります。スポーツ後に急に膝が動かしにくくなったり、腫れが引かない場合は、なるべく早く検査を受けることが重要です。
これらの状態は、早めに適切な処置を行えば悪化を防ぐことができます。水を抜くだけではなく、原因を突き止めて治療を行うためにも、症状が見られた時点で医療機関に相談するのが望ましい対応です。

膝に水が溜まる場合の治療方法

膝に水が溜まっているときは、病院で治療を受ける必要があります。具体的にどのような治療がおこなわれるのか、主な方法を紹介します。
早めに膝の水を抜く
膝にたまった関節液が多くなると、関節内の圧力が高まり、痛みや動かしづらさが増してきます。そのため、まずは膝の水を抜いて症状を緩和させることが治療の第一歩になります。注射器で関節液を抜き取る処置は「関節穿刺(かんせつせんし)」と呼ばれ、短時間で終わる比較的簡単な処置です。水を抜くことで痛みや腫れが軽減されるだけでなく、関節内の状態を検査するために関節液を分析することもできます。
膝内部の炎症を抑える
膝に水が溜まる原因は、ほとんどの場合、関節内の炎症によるものです。炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤の内服薬や、ステロイド剤やヒアルロン酸の注射が使われることがあります。これらの薬は関節内の炎症反応を抑えることで、痛みを軽減し、水が再びたまるのを防ぐ効果が期待できます。炎症の原因が関節リウマチや感染症などの場合は、それに応じた専門的な治療が必要になります。
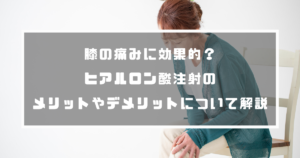
膝の水を抜くメリット

頻繁に膝の水を抜くのは良くないのではと、不安を覚える方もいるでしょう。
しかし、膝の水を抜くことにはいくつかのメリットがあります。主なメリットを3つ紹介します。
原因が判明する
膝から抜き取った関節液は、その性質を調べることで原因の特定に役立ちます。たとえば、関節液が透明でサラサラしていれば変形性膝関節症の可能性が高く、血が混ざっていれば半月板や靭帯の損傷を疑います。また、濁っていたり膿のような状態であれば細菌感染が原因と考えられ、さらに詳しい検査が必要になります。このように、見た目や成分を分析することで、水が溜まった背景にある病気やけがを明らかにすることができます。
早期発見ができる
関節液を検査することで、膝の中で起こっている異常を早い段階で発見できることがあります。たとえば、初期の関節リウマチや感染性関節炎などは、画像検査だけでは判断が難しいことがありますが、関節液の性状を確認することで早期の診断につながる場合があります。膝の水を抜くことは、目に見えない異常を見つけるための重要な手がかりとなります。
症状が改善しやすい
膝の水が多くたまっていると、関節内の圧力が高まり、動かしにくさや痛みが強くなります。そのため、水を抜くことで圧迫が解消され、痛みが和らいだり、膝の動きが改善したりします。また、同時に薬剤(ヒアルロン酸やステロイドなど)を関節内に注入することで、炎症を抑える治療効果も得られやすくなります。水を抜くだけで症状が大きく改善するケースも少なくありません。
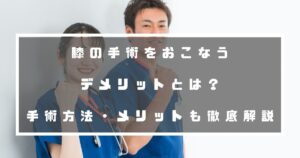
膝に水が溜まる症状を防ぐ方法

普段の生活で、膝に水が溜まらないように予防できます。膝にかかる負荷を減らしたり、ストレッチで関節の可動域を広げたりなど簡単に予防が可能です。
そこで、膝に水が溜まるのを防げる3つの方法を紹介します。
適正体重を保つ
体重が重いと、その分だけ膝にかかる負担が増え、関節軟骨がすり減りやすくなります。特に階段の上り下りやしゃがみ動作などでは、自分の体重の数倍の力が膝に加わることもあります。そのため、適正な体重を維持することは、膝の関節構造を守るうえで非常に重要です。バランスの良い食事や定期的な運動で体重をコントロールすることが、膝の水が溜まりにくい状態を保つ基本となります。
膝の負担を軽減する
膝に負担が集中しないように、生活動作や運動時の姿勢に注意することが大切です。たとえば、長時間の立ち仕事や急な方向転換を避ける、急激な階段の昇降や正座を長く続けないといった工夫が挙げられます。また、膝への衝撃をやわらげるために、クッション性の高い靴やサポーターの利用も有効です。膝の使い過ぎを防ぎながら、無理のない範囲で動かす習慣が重要になります。
膝のストレッチ
膝まわりの筋肉や関節の柔軟性を保つことも、水が溜まるのを予防するために効果的です。太もも前面の大腿四頭筋や、裏側のハムストリングス、ふくらはぎなどを日常的にストレッチすることで、膝関節にかかる力をうまく分散できるようになります。また、膝だけでなく股関節や足首の柔軟性も保つことで、体全体のバランスが整い、膝への負担を軽減する効果が期待できます。
これらの方法を継続的に取り入れることで、膝に余計な負担がかからず、関節内で炎症が起こるリスクを下げることができます。膝の健康を守るためには、日頃の小さな習慣の積み重ねがとても大切です。
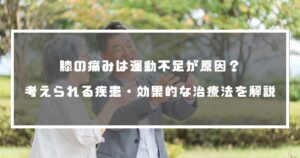
日常生活で可能な膝に水が溜まる症状の改善策

膝に水が溜まる症状は、病院で処置を受けた後に自宅で予防できます。また、軽度であれば改善できる可能性もあるでしょう。
そこで、日常生活でできるセルフケア方法を紹介します。
足上げストレッチ
膝周囲の筋力が低下すると、関節にかかる負担が増えて水が溜まりやすくなります。足上げストレッチは、太ももの前側にある大腿四頭筋を鍛える簡単な運動であり、膝を安定させる効果があります。椅子に座って片脚をまっすぐ伸ばし、そのまま数秒キープするだけでも効果があり、痛みが強くない範囲でゆっくり行うことがポイントです。筋肉を動かすことで血流もよくなり、関節内の炎症が改善しやすくなります。
靴に中敷きを使用する
歩行時の衝撃や膝への負担をやわらげるためには、靴の中にクッション性のある中敷きを入れるのが効果的です。特に土踏まずをしっかり支えるタイプや、かかとの安定感を高める中敷きは、膝関節にかかる圧力を分散してくれます。足のアライメント(骨の配列)が崩れていると膝に過剰な負荷がかかりやすくなるため、足元から整えることは膝の症状改善につながります。
有酸素運動
膝に強い負荷をかけずに全身の血流を促す運動として、有酸素運動は非常に有効です。たとえばウォーキングや水中歩行、自転車こぎなどは、膝をやさしく動かしながら筋力の維持と炎症の軽減を促します。運動によって体重を適正に保つこともでき、膝の圧迫を防ぐ効果も期待できます。ただし、痛みが強いときは無理をせず、医師や理学療法士に相談しながら行うことが大切です。
このように、日常生活の中で取り入れやすい工夫を継続することで、膝に水が溜まりにくい状態を保ち、症状の改善や再発防止に役立てることが可能です。
膝の水が溜まる症状に関するよくある質問

膝の水が溜まる症状がある場合、何度も水を抜いて癖にならないのか、自然に治るのかなど疑問や不安を抱く方もいるでしょう。
最後に、膝の水が溜まる症状についてよくある質問を紹介します。
膝の水を抜くと痛みや症状が癖になりますか?
膝の水を抜いても、痛みや症状が癖になることありません。ただし、膝の水を抜いた後も、症状が繰り返される可能性はあります。
膝関節に炎症が起こっている場合、炎症を抑えなければ、再度膝の水が溜まります。そのため、「癖になっている」と勘違いをする方も多いです。
炎症が起こっていることが原因であり、癖になっているわけではありません。
治療を受けた後に再度膝の水が溜まらないようにするためには、水が溜まる原因を明確にして、関節液が過剰分泌されないように対処しましょう。
膝の痛みに温湿布は効果的ですか?
温湿布を膝に貼る方法は、慢性的な炎症や変形性膝関節症が原因の痛みに効果的です。
一方、膝の痛みの種類によっては、冷湿布も効果が期待できます。冷湿布は患部を冷やすため、捻挫や打撲が原因で炎症を起こしているときに有効です。
温泉は膝の痛みや水が溜まる場合でも効果的ですか?
お湯の浮力や温度によって膝の痛みを緩和する効果が期待できます。温泉で身体を温めて血行を促進すると、痛みの軽減や、新陳代謝も活性化されます。
また、温泉に入ると浮力により、膝関節や膝周辺の筋肉への負担も軽くなることが特徴です。
さらに、水圧により膝の皮膚が締め付けられ、加えて血流が良くなると、むくみの解消にも効果が期待できます。
なお、温泉ではなく自宅の湯船でも同様の効果があります。
膝関節の痛みは治療しなくても自然に治りますか?
膝関節の痛みが、自然に治る可能性は低いです。膝に溜まった水は、関節内部の炎症が治ると少しずつ減ります。
膝関節で起こっていた炎症が治まると、関節液が吸収と分泌のバランスを保てるようになるためです。
しかし、炎症を抑えるためには治療しなければならないケースが多く、膝関節の痛みを放置すると炎症が悪化したり長引いたりします。
そのため、膝関節の痛みを放置せず、早めに治療が大切です。
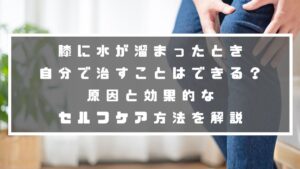
膝に水が溜まる症状は何科のクリニックを受診すればよいでしょうか?
膝に水が溜まる症状は、整形外科を受診します。
とくに、膝が腫れるほど水が溜まっている場合や、長期間痛みがある、感染症を起こしている可能性がある方は、早めに整形外科のあるクリニックを受診しましょう。

膝の治療にはシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科の膝の治療は、以下の理由からおすすめです。
・専門知識と経験豊富な医師陣
・最新の医療技術
・安心の手術
・パーソナライズされたケア
専門知識と経験豊富な医師陣
シン整形外科は専門知識を持つ医師がいるため、患者の症状や状態について本質的な診断や治療プランを提供しています。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ
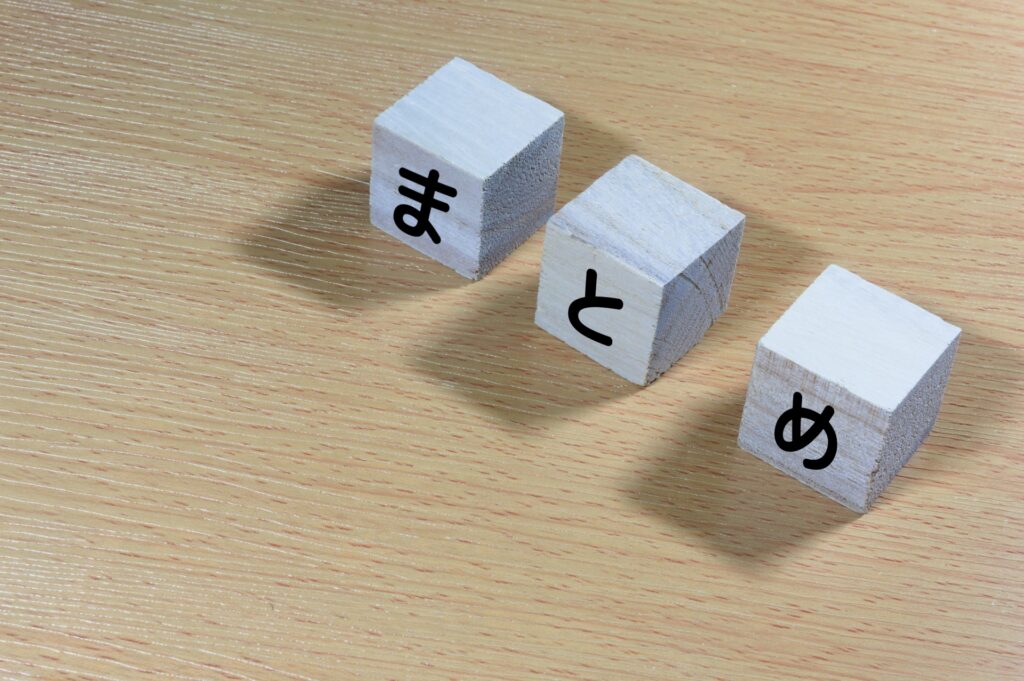
膝に水が溜まる症状が出ているにもかかわらず、放置を続けていると、将来的に外科的手術が必要になる可能性があります。
膝に水が溜まっている可能性がある方や、痛みや腫れ、動かしにくいなど違和感がある方は、病院で膝の状態を確認してもらいましょう。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。