半月板損傷はスポーツをする方にとってリスクの高い症例の一つです。半月板を損傷すると膝の痛みや違和感が症状として挙げられます。
半月板は自然治癒を見込めないため、半月板損傷の症状が疑われる場合は、速やかに治療を開始する必要があります。
この記事では、半月板損傷の症状や原因、効果的な治療方法について解説します。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
半月板損傷とは?

半月板損傷とは、膝関節の中にある半月板という軟骨組織が傷ついたり、裂けたりする状態を指します。半月板は膝の内側と外側にそれぞれ存在しており、膝の動きを安定させるクッションのような役割を果たしています。体重がかかったときの衝撃を吸収したり、膝の関節にかかる負担を分散させる重要な組織です。
スポーツ活動や日常生活で膝をひねる動作、ジャンプの着地、急な方向転換などがきっかけで損傷することが多く、特にサッカーやバスケットボール、ラグビーなどの激しい運動に多く見られます。また、加齢によって半月板の柔軟性が失われ、わずかな動作でも傷つきやすくなることがあります。
症状としては膝の痛みや腫れ、関節の引っかかり感、動かしたときの不安定さ、膝がスムーズに動かないロッキング現象などが挙げられます。軽度の場合は保存療法で改善することもありますが、損傷の程度によっては手術が必要になることもあります。膝関節の機能を維持するためには、早期に適切な診断と治療を受けることが大切です。
半月板の働き
膝関節の中には内側半月板と外側半月板という二つの軟骨組織が存在し、C字状の形をして大腿骨と脛骨の間に挟まるように配置されています。これらは骨と骨が直接ぶつかるのを防ぎ、関節の動きをスムーズにするために重要な役割を果たしています。
まず大きな働きとして、膝にかかる衝撃を吸収するクッションの役割があります。歩行やランニング、ジャンプの着地といった動作では膝に強い衝撃が加わりますが、半月板があることでその負担が和らぎ、軟骨や骨へのダメージが減ります。また、体重が膝に加わるときにその圧力を分散する働きも持っています。もし半月板がなければ、膝の関節面に一点集中で負担がかかり、早い段階で軟骨のすり減りや関節症が起きやすくなります。
さらに、膝の動きを安定させる機能も大切です。半月板は大腿骨と脛骨の間にぴったりとはまることで関節のガタつきを防ぎ、スムーズな曲げ伸ばしを可能にしています。特に方向転換や急なストップ動作のときに膝が不安定にならないよう支える役割を担っています。
半月板損傷の症状
半月板損傷の症状として最も代表的なのは膝の痛みです。特に膝を深く曲げたときや階段の上り下り、しゃがむ動作をした際に強く痛みが出ることが多く、膝関節に強い負担を感じます。また、損傷の程度や部位によっては動作のたびに膝の中で「引っかかるような感覚」や「何かが挟まっているような違和感」が生じることがあります。
さらに、膝を動かした際にゴリゴリとした音や感触を伴うこともあり、これは損傷した半月板の一部が関節内で不安定に動くことで起こります。症状が悪化すると、膝が突然動かなくなり、まるでロックがかかったように曲げ伸ばしができなくなる「ロッキング」と呼ばれる状態に陥ることもあります。これは半月板の断片が関節に引っかかってしまうために起こる現象で、強い痛みと共に日常生活に大きな支障をきたします。
また、膝に水が溜まる「関節水腫」が繰り返し出現するのも特徴です。炎症によって関節内に余分な液体が溜まることで膝が腫れぼったくなり、動かしにくさや重だるさを感じます。損傷が長期間にわたり放置されると、膝関節にかかる衝撃を吸収する機能が低下するため、軟骨がすり減りやすくなり、将来的に変形性膝関節症へとつながる危険性もあります。
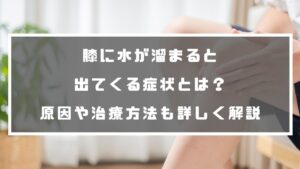
半月板損傷の原因
半月板損傷の原因には、スポーツや事故などによる急な外傷と、加齢による変性の二つの大きなタイプがあります。まず、スポーツや交通事故などの外傷性の損傷では、膝を強くひねったり、急に方向転換したり、ジャンプの着地で強い力が加わることで半月板が裂けたり断裂したりします。特にサッカーやバスケットボール、ラグビー、スキーなど、膝に負担がかかりやすい競技で多く見られます。前十字靭帯損傷と同時に起こることも少なくなく、膝全体の安定性が失われる大きなケガにつながることもあります。
一方で、年齢を重ねるにつれて半月板の組織が弱くなり、弾力性や柔軟性が低下することで、わずかな動作でも損傷が起きやすくなります。これを変性損傷と呼び、特に中高年層に多くみられます。しゃがむ、立ち上がるといった日常的な動きでも半月板に亀裂が入り、膝の痛みや動かしづらさの原因になります。さらに、体重増加や長年の膝への負担の蓄積も要因となり、徐々に進行していくことがあります。
つまり半月板損傷の原因は、若い世代ではスポーツや事故による強い外力、中高年以降では加齢や負担の蓄積による変性が中心となっており、それぞれで治療や予防の考え方が異なってきます。
半月板損傷の治療方法

半月板損傷は、痛みや症状の進行の程度により、保存療法、もしくは手術療法で治療をおこないます。
半月板損傷は自然治癒が見込めず、長期間放置すると変形性膝関節症など、別の症状に繋がるリスクがあります。
膝に痛みや違和感がある場合は、自己診断せずに医師の診断を受け、適切な治療をおこなうようにしましょう。
保存療法
半月板損傷に対して行われる保存療法とは、手術をせずに症状の改善や進行の抑制を目指す治療法のことを指します。比較的軽度の損傷や、損傷していても膝の安定性が保たれている場合に選択されることが多く、日常生活に支障をきたす強い症状がないときには有効です。主な方法としては、まず安静にして膝に過度な負担をかけないことが重要で、急性期には炎症や腫れを抑えるためにアイシングや圧迫、膝の挙上が行われます。また、鎮痛薬や消炎薬を用いて痛みや炎症を和らげることもあります。
さらに、膝周囲の筋力を強化するリハビリテーションが保存療法の中心的役割を担います。特に太ももの大腿四頭筋やハムストリングを鍛えることで膝関節の安定性が向上し、損傷した半月板への負担を軽減できます。リハビリは段階的に行われ、初期は可動域を取り戻す軽い運動から始め、徐々に筋力やバランスを養う運動へと移行していきます。場合によっては、膝の動きをサポートする装具やテーピングを使用し、関節への負荷を減らすこともあります。
また、体重の管理も保存療法の一環です。膝は体重を支える関節であるため、体重が増えると半月板への圧力が高まり損傷部の悪化につながります。そのため、適正体重の維持は症状の軽減と再発予防のために大切です。これらの保存療法は根本的に損傷した半月板を修復するものではありませんが、症状を緩和しながら膝の機能を保つことが可能です。特に高齢者や活動量の少ない方、あるいは小さな損傷で痛みが強くない場合には、保存療法だけで日常生活に支障がない状態を維持できるケースも少なくありません。
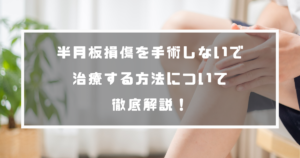
手術療法
月板損傷の手術療法は、保存療法を行っても症状が改善しない場合や、損傷の程度が大きく日常生活やスポーツ活動に支障をきたしている場合に検討されます。手術にはいくつかの方法があり、損傷部位や患者の年齢、生活スタイルなどによって最適な術式が選択されます。
代表的なのは関節鏡を用いた手術で、皮膚を大きく切らずに小さな切開口からカメラと器具を挿入して行うため、身体への負担が少なく、比較的短期間で退院やリハビリに移れるという利点があります。
手術の内容としては、まず「半月板部分切除術」があります。これは損傷して修復不可能な部分を取り除き、残りの健康な半月板をできるだけ温存する方法です。ただし、半月板を削る量が多くなると、将来的に変形性膝関節症を引き起こすリスクが高まるため、必要最小限にとどめることが重要です。
次に「半月板縫合術」があり、これは比較的血流が保たれている部分で損傷が起こった場合に、断裂した部分を縫い合わせて修復する方法です。半月板を温存できるため、関節機能を長く維持できるメリットがありますが、縫合部がしっかり癒合するまで時間がかかるため、リハビリ期間はやや長くなります。
また、若年者や広範囲に半月板を失った場合には、「半月板移植術」が選択されることもあります。これはドナーから提供された半月板を移植する方法で、膝のクッション機能を取り戻し、関節の変性を予防する目的で行われます。ただし、手術自体が複雑であり、適応となる患者は限られます。
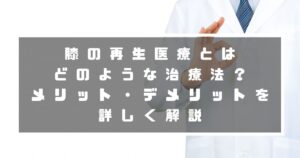
半月板損傷の検査や診断方法

半月板はレントゲンに映らないため、検査・診断は主に次のような方法でおこなわれます。
- 問診
- MRI検査
- 超音波検査
ここでは、それぞれの検査・診断方法の内容について紹介します。
問診
問診では、次のような内容が質問されます。
- 痛みや違和感の現れた時期
- どのようなときに痛みや違和感があるか
- 痛みの程度
- これまでの怪我の経験
問診と併せて触診がおこなわれ、痛みや違和感のある部分や患部の腫れや熱感などを確認します。また、スポーツの経験の有無についても質問されます。
- サッカー
- 野球
- バスケットボール
- バレーボール
- 体操
- テニス
- スキー
上記のような半月板損傷の好発種目の場合、プレー時に膝に負荷がかかった状況がないのかも確認されます。
MRI検査
問診、触診により、半月板損傷を疑われる場合、半月板にはMRI検査による診断がおこなわれます。
半月板損傷の診断におけるMRI検査の診断率は80〜90%と高い精度を誇ります。また、MRI検査では前十字靭帯損傷などの合併症も併せて診断可能です。
MRI検査により半月板損傷の診断となった場合、患者の希望や症状の程度、ライフスタイルに合わせて、保存療法か手術療法かの治療方針を決定します。
ただし、医院によっては事前にレントゲンにより関節の状態を確認し、MRI検査の結果と総合的に判断する場合もあります。
超音波検査
検査をおこなう医院によって、または、MRI検査で確定診断に至らなかった場合、超音波検査(エコー)による診断をおこなうケースがあります。
超音波検査では、半月板の損傷の有無と併せて、腰や股関節、足などの膝に負担のかかる要因の有無を検査できます。
超音波検査は、主に整骨院や整形外科のクリニックなどで採用されています。
半月板損傷後のリハビリ方法

半月板損傷の手術後、約2週間程度経過すると、軽度な運動から動的なリハビリが開始されます。
ここでは、半月板損傷の手術後に効果的なリハビリ方法を紹介します。
可動域を広げるストレッチ
収縮した膝関節周辺の筋肉や靭帯の可動域を広げ、柔軟性を向上させるストレッチは効果的なリハビリ方法です。
ストレッチは、膝関節のみならず大腿や股関節なども対象です。
膝を伸ばすストレッチの手順は次のとおりです。
- 床に座り両腕で上半身を支える
- 片方の足を曲げ、逆側の足に乗せる
- 2で乗せた足の重さで膝を伸ばす
- 片側20秒ずつ、両側で複数回繰り返す
半月板の損傷の箇所や、手術の範囲によっても効果的なストレッチ方法は異なります。適切なストレッチ方法については、担当医師に相談してみましょう。
筋力トレーニング
膝周辺の筋力を鍛えて、半月板への負担を軽減するのも効果的です。痛みを感じない範囲で次のような筋力トレーニングをリハビリに取り入れます。
- 枕つぶし
- 胴上げ
- お尻上げ
- 片足ブリッジ
- サイドブリッジ
- スクワット
最も膝への負荷が少ない筋力トレーニングは枕つぶしです。
- あおむけに寝転び、膝下に丸めたタオルを入れる
- 膝下に入れたタオルを押しつぶすイメージで太腿を床に押しつける
リハビリでの筋力トレーニングでは、大腿筋や内側広筋を対象にトレーニングをおこないます。
バランス感覚を鍛えるトレーニング
半月板は大腿骨と脛骨のクッションの役割を果たし、荷重を分散してバランスを保っています。
そのため、半月板損傷により不安定になった膝のバランス感覚をリハビリで鍛える必要があります。
バランス感覚を鍛えるトレーニングは、バランスボードやバランスディスクなどの器具を使用します。
ただし、転倒の危険も伴うため、理学療法士などの付き添いの元、安全を確保してリハビリをおこなうようにしましょう。
スポーツ動作
スポーツ選手の場合、リハビリの最終的なゴールはスポーツ競技への復帰です。
半月板損傷の手術から、スポーツ動作のリハビリに至るまでのステップは次のとおりです。
- 術後2週間~4週間:ウォーキングや軽いジョギング
- 術後1か月~3か月:スポーツ動作
まずは、負荷の少ないウォーキングや軽いジョギングからスタートし、ジャンプやステップなど、取り組むスポーツに必要な動作のチェック、トレーニングをおこないます。
その際、痛みや違和感がある場合、無理は禁物です。
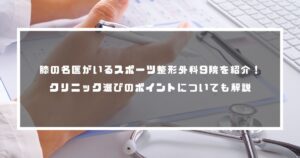
半月板損傷の治療ならシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
半月板損傷の治療を検討している方には、再生医療による関節の痛み治療専門のシン・整形外科がおすすめです。
シン・整形外科には次のような特徴があります。
- 手術不要の再生医療に特化
- 保証制度あり
- 無料電話相談に対応
それぞれの特徴について詳しく解説するため、半月板損傷による痛みが長期間続いている方や、保存療法では改善がみられない方はぜひチェックしてみてください。
手術不要の再生医療に特化
シン・整形外科は、手術不要で痛みの改善が期待できる再生医療に特化しています。
再生医療とは、人体の自己再生能力を引き出し損傷を修復させる治療方法です。
治療は自身から採取した血液や細胞を加工し損傷箇所に注入するのみで、日帰りで手軽に受けられます。
体への負担も少なく生活に影響しにくいため、仕事や家事など通常通りに過ごせるのも魅力です。
採用している再生医療は、幹細胞培養治療、PRP-PRO治療、PRP-FD治療と豊富で、自身の症状にあった方法を選べます。
もちろん、どの治療が適しているかは整形外科の専門家が詳しい検査をしたうえで提案します。再生医療に詳しくない方も相談しやすいでしょう。
保証制度あり
シン・整形外科では、安心して治療を受けられるように次のような保証制度も用意しています。
- 再治療保証
- リスク保証
再治療保証は、再生医療を受けても十分な効果が得られなかった際に、無料で1回分の再治療が受けられる保証です。
幹細胞培養治療を2回以上とリハビリスタンダードコースを6か月以上継続して受けた方が対象となり、初回の施術から1年間保証されます。
保存療法では改善がみられなかった方も、上記のような保証があれば再生医療に挑戦しやすいでしょう。
また、リスク保証は万が一再生医療により健康を害した場合に、再生医療サポート保険を利用できます。
シン・整形外科が扱う再生医療は拒絶反応や副作用などのリスクが低い治療法ですが、万が一のために備えられるのは安心できるポイントでしょう。
無料電話相談に対応
シン・整形外科では診察以外にも電話無料相談に対応しています。
再生医療に関する不明点や不安など気になることを気軽に相談でき、初回の診察を受ける前にある程度の情報を集められます。
再生医療がどのような治療なのか詳しく知りたい方や、再生医療が自身にあっているのか悩んでいる方に嬉しいサービスです。
フリーダイアルで通話料もかからないため、再生医療を検討している方はぜひ利用してみてください。
まとめ
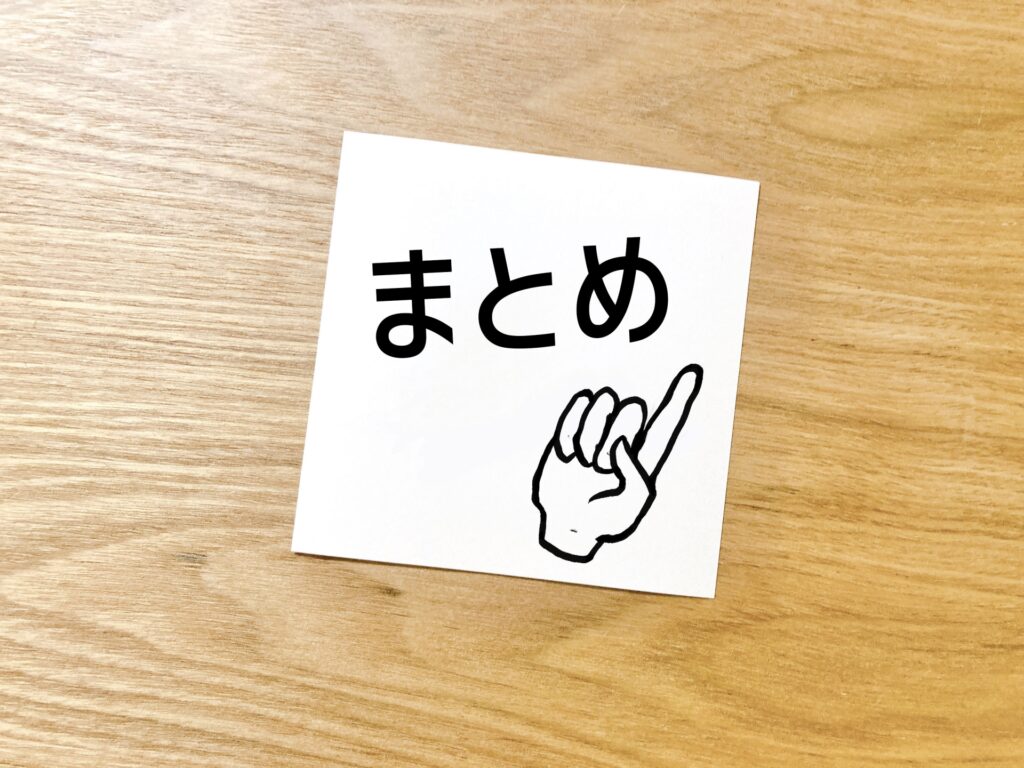
半月板損傷には、大きく分けて外傷性と非外傷性の2種類の原因があります。
とくに、スポーツ選手の場合は外傷性の半月板損傷のリスクが高く、代表的なスポーツ外傷の一つでもあります。
半月板損傷の治療からスポーツ競技への復帰には3か月~半年程度の期間が必要ですが、適切なリハビリをおこない、治療期間を短縮できる可能性もあります。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。










