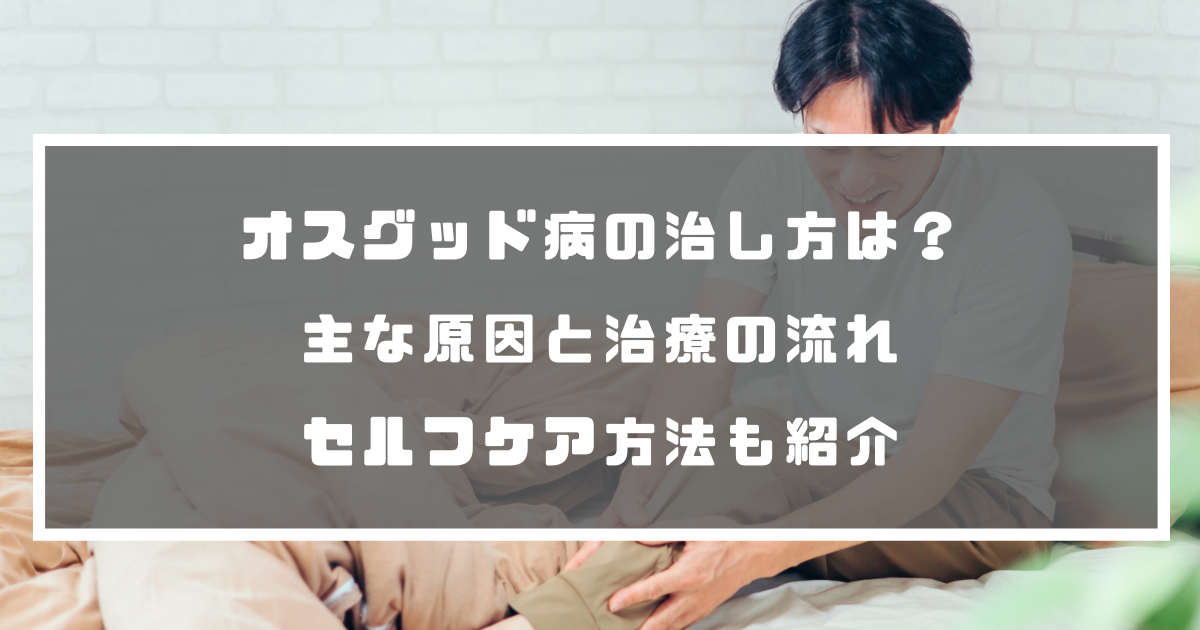10代の成長期に患うことが多いオスグッド病は、成長痛と混同されやすいほか、痛みに耐えたまま部活や授業に参加する子どもが多いため、発見が遅れがちです。
そのため、オスグッド病には親や教師、インストラクターになど大人が理解していなければなりません。
本記事では、オスグッド病の症状や成長痛との違いを明確にし、治し方や自宅でできるセルフケア方法を解説します。
予防や痛みを緩和させる具体的な方法や、治療にかかる期間なども認識できるため、ぜひ参考にしてみてください。
- WEB来院予約OK!
- 手術・入院不要のひざ特化治療!
- 専門リハビリで痛みが再発しない膝へ!
| 事前相談 | 無料 |
| 初診料 | 3,300円〜 |
| 注入治療 | 198,000円〜 30%割引モニター制度あり |
オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)とは?

オスグッド病は、主に成長期の子どもに起こりやすい、膝や膝下に痛みが生じる病気とされており、成長期スポーツ障害の代表疾患ともいわれています。
膝のお皿となる膝蓋骨と脛骨をつなぐ膝蓋靭帯が引っ張られることで、脛骨粗面から剥がれてしまい、痛みが生じる疾患です。
まずは、オスグッド病の症状や成長痛との違いなど、オスグッド病への理解を深めることで早期発見にもつながるため、ここでオスグッド病について詳しく解説します。
オスグッド病の症状
オスグッド病は、成長期の子ども、とくにスポーツをしている中学生に多く見られる膝の障害で、膝のすぐ下にある骨(脛骨粗面)が痛くなるのが特徴です。膝の下の部分が押すと痛んだり、走る・ジャンプする・しゃがむなどの動作で痛みが強くなることがあります。しばらく休んでいると症状は軽くなるものの、運動を再開すると再び痛みが出ることが多く、繰り返しやすいのがこの病気の特徴です。膝下の骨が徐々に出っ張ってくることもあり、触ると硬いこぶのように感じる場合もあります。
脛骨が突出する
膝の下にある脛骨の上端(脛骨粗面)に強い負担がかかることで、その部分が徐々に突出してくることがあります。成長期の子どもは骨がまだ柔らかく、太ももの筋肉(大腿四頭筋)が膝を通じて脛骨を強く引っ張るため、繰り返しの運動によって骨が引きはがされるような状態になり、脛骨の一部が盛り上がってきます。これが目立つようになると、触っても分かるほど硬く膨らんだ状態となり、運動時や圧迫時に痛みを感じる原因になります。運動を続けると突出が悪化することもあるため、早めの対応が重要です。
成長痛との違い
オスグッド病と成長痛はどちらも成長期の子どもに見られる膝の痛みですが、原因や症状、対処法にいくつかの違いがあります。
オスグッド病は、特定の部位――膝の下の脛骨粗面に痛みや腫れが出るのが特徴です。主にスポーツなどで膝に負担がかかることで起こり、運動中や運動後に痛みが強くなります。触ると痛みがあり、膝下の骨が出っ張ってくる場合もあります。動作に関連して症状が出るため、安静にすると比較的楽になるものの、再度運動をすると再発しやすい傾向があります。
一方で成長痛は、夕方から夜間にかけて両足の膝やすね、太ももなどが漠然と痛むのが特徴で、特定の部位ではなく、場所が日によって変わることもあります。日中に痛みを訴えることは少なく、運動量とはあまり関係がありません。睡眠中に痛みで目が覚めることがあっても、朝になると痛みがなくなっていることが多いです。
つまり、オスグッド病は運動による負荷が原因で膝下に明確な炎症や骨の変化を伴うのに対し、成長痛は一時的で原因がはっきりしない非炎症性の痛みで、運動とは無関係なことが多いのが大きな違いです。
成長期の子どもに多い病気
オスグッド病は、成長期の子ども、特にスポーツをしている男子に多くみられる膝の障害のひとつです。小学校高学年から中学生くらいの時期は、骨の成長が急速に進む一方で、筋肉や腱の柔軟性が追いつかず、体のあちこちに負担がかかりやすくなります。オスグッド病では、太ももの前側にある大腿四頭筋が膝のお皿の下にある脛骨粗面という部位を強く引っ張ることで、骨が炎症を起こしたり、徐々に突出したりするのが特徴です。
ジャンプやダッシュなどを繰り返すスポーツ、たとえばサッカーやバスケットボールなどを日常的に行っている子どもに発症しやすく、膝の下に痛みや腫れが出る、骨が出っ張る、運動中に痛みが強くなるといった症状が現れます。成長が落ち着くと自然に症状が軽くなることも多いですが、無理をすると悪化したり、長引いたりするため、早めの対応が大切です。成長期特有の病気として、保護者や指導者がその存在を知っておくことも重要です。
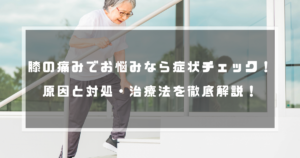
オスグッド病の原因

オスグッド病の原因は、前述してきた刺激によること以外に、さまざまな原因があると考えられています。
姿勢の悪さや偏平足のような、普段の癖からオスグッド病につながる場合もあるため、正しい姿勢やバランスを整えることで予防できる病気です。
原因が明確になれば、オスグッド病にならないための予防策も考えられるため、オスグッド病の原因を認識しておきましょう。
太ももの柔軟性がなくなる
オスグッド病の原因のひとつに、太ももの筋肉(特に大腿四頭筋)の柔軟性の低下があります。成長期の子どもは骨の成長が先に進み、筋肉や腱の柔軟性が追いつかないことがよくあります。その結果、太ももの筋肉が硬くなり、膝の下の骨(脛骨粗面)を引っ張る力が強くなってしまいます。
この状態でジャンプやダッシュなどの動作を繰り返すと、脛骨粗面に大きな負担がかかり、炎症が起きたり、骨が突出したりする原因になります。特に運動量が多い子どもや、ストレッチをあまり行っていない子どもほど発症リスクが高くなります。つまり、太ももの筋肉の柔軟性がなくなることは、オスグッド病を引き起こす大きな要因のひとつであり、予防のためには日頃からのストレッチや適度な休息が大切です。
ジャンプ動作による炎症
ジャンプや着地といった動作の繰り返しによって膝にかかる負担があります。特にジャンプでは、太ももの筋肉が強く収縮して、膝を伸ばす力が働きます。このとき、筋肉の力が膝下の骨(脛骨粗面)に伝わり、繰り返されることでその部分に炎症が起きやすくなります。
ジャンプ動作を頻繁に行うスポーツ、たとえばバスケットボールやバレーボールなどをしている子どもでは、脛骨粗面が引っ張られ続けることによって炎症が慢性化し、骨が盛り上がって硬くなったり、痛みが強くなったりします。成長期の骨はまだ未完成で柔らかいため、こうした衝撃に弱く、オスグッド病を引き起こしやすくなります。つまり、ジャンプの衝撃が脛骨に繰り返し加わることで炎症が起き、それがオスグッド病の発症につながるのです。
姿勢が悪い
猫背や骨盤が後ろに傾いている状態が続くと、太ももの前側の筋肉である大腿四頭筋に過剰な緊張が生じます。この筋肉が硬くなることで、膝の下にある脛骨粗面という部分が強く引っ張られ、炎症や骨の突出が起こりやすくなります。
また、姿勢の悪さは運動時の体の使い方にも影響を与えます。ジャンプやダッシュなどの動作でフォームが乱れると、膝への負担がさらに大きくなり、オスグッド病のリスクが高まります。特に成長期の子どもは骨が未発達なため、こうした負担が直接的な原因となることがあります。普段から正しい姿勢を心がけることは、オスグッド病の予防や悪化防止につながります。
重心が傾いている
体の重心が前後や左右に偏っていると、下半身の筋肉にかかる負担が均等でなくなります。特に重心が前に傾いている場合、太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)が過剰に使われやすくなり、その結果として膝下の脛骨粗面に強い牽引力が加わります。これが繰り返されることで、炎症や骨の突出が起こりやすくなり、オスグッド病を引き起こす要因になります。
また、重心が崩れていると運動時の姿勢も不安定になり、ジャンプや着地、方向転換といった動作で膝に不自然な力がかかりやすくなります。特に成長期の子どもは関節や骨がまだ発達途中のため、こうした小さな負担の積み重ねが大きな障害につながることがあります。重心の安定を意識した姿勢づくりや体幹の強化は、オスグッド病の予防に効果的です。
扁平足
扁平足とは、足の土踏まずのアーチが低下している状態で、足裏全体が地面に接しているような形になります。この状態だと、歩行や運動時に足首や膝への衝撃がうまく分散されず、膝に直接的な負担がかかりやすくなります。
特に、扁平足の人は歩いたり走ったりするときに足の内側に重心が偏りやすくなります。これによって膝の位置がずれやすくなり、太ももの筋肉が正しく働かなくなります。その結果、膝下の脛骨粗面に過度な牽引力が加わり、炎症や突出が起こることでオスグッド病を発症することがあります。
扁平足は見落とされがちですが、足元のバランスが崩れると体全体の動きにも影響を与えるため、オスグッド病の予防や改善には足のアーチを支えるインソールや筋力トレーニングなどが有効です。
大腿四頭筋の発達
大腿四頭筋は太ももの前面にある大きな筋肉で、膝を伸ばす動作やジャンプ、ダッシュなどの動きに大きく関与しています。この筋肉が強く発達すると、運動時に膝下の脛骨粗面にかかる引っ張る力も強くなります。
特に成長期の子どもは、骨の成長に対して筋肉の成長や柔軟性が追いつかないことが多く、大腿四頭筋が硬くなりやすい傾向があります。筋肉が硬いまま強く働くと、脛骨粗面が繰り返し引っ張られて炎症を起こしやすくなり、オスグッド病を発症するリスクが高まります。
スポーツを熱心に行っている子どもほど大腿四頭筋が発達しやすく、その分膝への負担も大きくなるため注意が必要です。予防のためには、筋力トレーニングだけでなく、ストレッチや柔軟性を高める運動も取り入れることが重要です。
オスグッド病の治し方!痛みの改善方法

オスグッド病の治し方は、安静にしてスポーツを控えることが最も多くありますが、部活やスポーツに励む子どもの可能性を潰すことになりかねません。
そのため、運動しつつ改善を図る治し方として装具療法が用いられます。オスグッド病専用のサポーターを着けたまま部活やスポーツに参加できるため、子どものことを考慮すると最善策といえるでしょう。
また、重症の場合は手術も検討する必要があるため、それぞれ詳しく解説します。
装具療法
装具療法では、専用のサポーターやバンドを用いて、膝下の脛骨粗面にかかる負担を軽減させます。これにより、運動時や日常生活における痛みの緩和が期待できます。
オスグッド病専用のサポーターは、脛骨粗面を圧迫するように装着することで、大腿四頭筋の引っ張る力を分散させ、炎症部位への直接的な刺激を和らげます。特にスポーツ時に装着することで、膝にかかる負荷を減らしながら運動を継続できる場合もあります。
ただし、装具はあくまで補助的な役割のため、痛みが強いときには無理に運動を続けず、安静を保つことが重要です。また、ストレッチや筋肉の柔軟性を高めるリハビリ、姿勢の改善などと組み合わせて取り入れることで、より効果的に症状を改善することができます。
遊離骨片摘出手術
オスグッド病の治し方のひとつとして、「遊離骨片摘出手術」があります。これは、保存療法や装具療法などを行っても症状が長引き、痛みが慢性的に続いて日常生活やスポーツに支障が出ている場合に検討される治療法です。
オスグッド病では、脛骨粗面に過度な牽引力がかかり続けることで、骨の一部が剥がれて小さなかけら(遊離骨片)となることがあります。この骨片が膝の動きに合わせて刺激を受けると、炎症や痛みが慢性的に続く原因になります。遊離骨片摘出手術では、皮膚を切開してその骨片を取り除くことで、痛みの原因を根本から解消することができます。
手術は通常、局所麻酔や全身麻酔で行われ、入院期間も比較的短く済むケースが多いです。術後はリハビリを行いながら徐々に運動を再開し、多くの人が痛みから解放され、スポーツにも復帰できるようになります。ただし、手術は最終手段であり、まずは安静、ストレッチ、装具の使用など保存療法を優先し、改善が見られない場合に医師と相談のうえ選択されます。
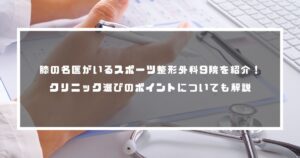
【自宅できる】オスグッド病の症状を予防・緩和するセルフケア

オスグッド病は、重症の場合に手術を要する病気にもかかわらず、スポーツに励む成長期の子どもに起こりやすい病気です。
治し方も大切ですが、そもそもオスグッド病にならないための予防策や、自宅でできるセルフケアについて認識しておきましょう。
前述した安静第一であることや大腿四頭筋のストレッチなども含まれていますが、あらためて確認してみてください。
安静にする
オスグッド病の症状を予防・緩和するためには、安静を基本とした自宅でできるセルフケアが効果的です。無理に運動を続けると膝への負担が増し、痛みが悪化するおそれがあるため、まずは膝を休ませることが大切です。以下のような方法を自宅で取り入れることで、症状の緩和や予防につながります。
まず、痛みがある場合は安静を保ち、膝にかかる負担を最小限にするよう心がけましょう。階段の昇り降りやしゃがむ動作など、膝に強い力がかかる行動は避けるようにします。
次に、太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)のストレッチを行うことで、膝下への牽引力を減らす効果が期待できます。ストレッチは、入浴後など筋肉が温まっているタイミングに無理のない範囲で行いましょう。
また、必要に応じて冷却(アイシング)を行うのも有効です。運動後や痛みが強いときに、膝下を10〜15分程度冷やすことで炎症を抑える効果があります。
さらに、オスグッド病用のサポーターや膝バンドを装着することで、脛骨粗面への負荷を軽減し、動作中の痛みを和らげることができます。
日常生活では姿勢や重心の偏りにも注意し、体に無理な負担がかからないように意識することも予防に役立ちます。定期的にストレッチや体幹を整えるトレーニングを取り入れることも、症状の予防に効果的です。
スポーツ活動を見直す
成長期の子どもは、骨がまだ柔らかいため、過度な運動による負担が蓄積しやすく、オスグッド病のリスクが高まります。自宅でできる対策として、運動量や内容を適切にコントロールすることが効果的です。
まず、痛みが出ている間は一時的に運動を中止し、膝を休ませることが基本です。症状が軽い場合でも、ジャンプやダッシュ、急停止など膝に大きな負担がかかる動作は避けた方がよいでしょう。無理をして続けると、炎症が悪化し、回復が長引く可能性があります。
また、練習の頻度や強度が過剰になっていないかを振り返り、必要に応じて休養日を設けることも大切です。自宅でできる軽いストレッチや体幹トレーニングに切り替え、筋肉の柔軟性や姿勢の改善を図ることは、膝への負担を軽減し、再発予防にもつながります。
保護者や指導者と相談しながら、体の状態に合った運動計画を立てることが、オスグッド病の予防と早期回復に効果的です。痛みのサインを見逃さず、身体の声に耳を傾けながらスポーツ活動を見直すことが大切です。
食事の栄養バランスを整える
成長期の子どもは骨や筋肉が急速に発達する時期であり、適切な栄養が不足すると体の回復力や柔軟性に悪影響を与え、オスグッド病のリスクが高まります。
まず、骨の健康を支えるカルシウムをしっかり摂ることが重要です。乳製品や小魚、青菜類などが代表的なカルシウム源です。また、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも欠かせません。鮭や卵、きのこ類に加え、日光を適度に浴びることもビタミンDの生成に役立ちます。
筋肉や腱の修復を助けるたんぱく質も積極的に取り入れましょう。肉類、魚、大豆製品、卵などをバランスよく組み合わせることで、運動後のダメージからの回復を促進します。
さらに、ビタミンCや亜鉛といった栄養素も、炎症を抑えたり、組織の修復を助けたりする働きがあります。果物や野菜、ナッツ類などを取り入れて、偏りのない食事を心がけることが大切です。
食事は毎日の積み重ねが重要です。栄養バランスの整った食生活を続けることで、オスグッド病の予防や症状の改善をサポートし、元気な身体づくりにつながります。
筋肉をほぐすストレッチをする

本記事でも多く解説してきましたが、オスグッド病はストレッチによって改善できる病気です。
とくに大腿四頭筋のストレッチが効果的とされているため、太ももの前側を伸ばすようなストレッチをおこないましょう。
座ったままの状態で片膝を曲げて大腿四頭筋を伸ばすストレッチが多く紹介されていますが、むしろ悪化させる危険があるともいわれています。
正しいストレッチの方法をここで認識しておきましょう。
太ももと脛のストレッチ
太ももと脛の筋肉をやさしくほぐすためのストレッチは、体の柔軟性を高め、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。まず太ももの前側(大腿四頭筋)を伸ばすには、立った状態で片足を後ろに引いて膝を曲げ、足首を手で持ちます。かかとをお尻に近づけるようにして太ももの前が伸びているのを感じながら、体が前に倒れないように注意して姿勢を保ちます。必要であれば壁やイスにつかまってバランスを取ってもかまいません。
次に太ももの裏側(ハムストリング)を伸ばすストレッチです。床に座って片足をまっすぐ前に伸ばし、もう一方の足の裏を伸ばした足の内ももに当てるように曲げます。背中を丸めずに、ゆっくりと伸ばした足のつま先に向かって体を倒していくと、太ももの裏に心地よい伸びを感じられます。無理せず、呼吸をゆっくり続けながら行うのがポイントです。
脛の前側(前脛骨筋)を伸ばすには、まず正座をして足の甲を床につけます。そのまま少しずつ上体を後ろに倒していくと、スネの前側がじんわり伸びていきます。膝や足首に無理がかからない範囲でゆっくり伸ばすようにします。また、立った状態でスネを伸ばすには、片足のつま先を床につけたまま足の甲を下に向けて後ろに引き、体重を軽く乗せるとスネの前側に伸びを感じることができます。
これらのストレッチは、筋肉が温まっている状態、たとえば運動後やお風呂上がりに行うとより効果的です。リラックスしながら、痛みを感じない範囲で、毎日少しずつ続けることが大切です。
骨盤のストレッチ
骨盤まわりの筋肉をほぐすストレッチは、腰や股関節の柔軟性を高め、姿勢の改善や腰痛予防にもつながります。特に骨盤にはお尻や太ももの付け根、腰まわりの筋肉が集まっているため、緊張をゆるめてあげることが大切です。
まず、仰向けに寝た状態で片膝を胸に引き寄せるストレッチがあります。片足を伸ばしたまま、もう片方の膝を両手で抱えて胸に近づけるように引き寄せていくと、お尻や腰の奥にある筋肉がじんわりと伸びます。左右交互に行いながら、それぞれ20秒ほどかけてゆっくり伸ばすようにします。
次に、あぐらをかくように座って股関節を広げるストレッチです。両足の裏を合わせて、膝を外側に開いていきます。背筋を伸ばしたまま、体を少し前に倒すと骨盤の内側や股関節まわりが伸びていくのを感じられます。膝を無理に床に近づけようとせず、自然な位置でリラックスして行うのがコツです。
さらに、横になって体をひねるストレッチも骨盤には効果的です。仰向けで膝を立て、片膝を反対側へ倒し、上半身は逆方向に軽くひねるようにします。このとき腰まわりがねじられることで、骨盤のまわりの筋肉がゆるみ、リラックス効果も得られます。
ストレッチはゆっくりとした呼吸とともに行い、痛みを感じる手前で止めることが大切です。骨盤の動きがよくなると、体のバランスや動きのスムーズさも改善されていきます。日常的に取り入れると、腰や股関節の不調の予防にもつながります。
トレーニングをする

オスグッド病は、大腿四頭筋の発達が著しい際に起こりやすい病気と解説しましたが、筋肉の左右差や大腿四頭筋にほかの筋肉が追い付いていない可能性も原因の一つです。
そのため、トレーニングをおこないバランスの取れた筋肉をつけることを意識しましょう。
とくにオスグッド病の予防または痛みが軽減したあとにおこなうことがおすすめのフロントランジスクワットやカーフレイズがおすすめです。
大腿四頭筋に合わせて前脛骨筋や、ふくらはぎの筋肉である腓腹筋を鍛えることがオスグッド病の予防策となるため、それぞれ詳しく解説します。
フロントランジスクワット
フロントランジスクワットは、太ももやお尻の筋肉を鍛える効果が高く、スポーツ選手などのトレーニングによく取り入れられている種目です。ただし、オスグッド病の人が行う場合には注意が必要です。
オスグッド病は、膝下の脛骨(すねの骨)の成長軟骨部分に負担がかかって炎症や痛みが出る症状で、特に成長期の子どもに多く見られます。フロントランジスクワットは、膝を深く曲げたり伸ばしたりする動作が含まれているため、膝への負担が大きく、オスグッド病の症状を悪化させる可能性があります。
もしオスグッド病の痛みがある時期であれば、フロントランジスクワットは避けたほうが安全です。特に膝が痛い、腫れている、ジャンプや階段の上り下りで強く痛むといった状態では、筋トレや負荷の大きい運動は控えたほうがよいでしょう。
痛みが落ち着いてきた回復期には、医師や理学療法士の指導のもとで、膝に負担をかけすぎない範囲で軽いスクワットやストレッチを始めるのが一般的です。その際には、動作中に膝がつま先より前に出ないように意識したり、フォームをしっかり確認することが大切です。
まとめると、オスグッド病の症状があるときには、フロントランジスクワットのような膝に負担がかかる運動は基本的に避けるべきです。痛みが落ち着いてきたら、医療の専門家と相談しながら、段階的に筋力トレーニングを再開することが望まれます。
カーフレイズ
カーフレイズ(つま先立ち運動)は、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋やヒラメ筋)を鍛えるシンプルなトレーニングです。膝の曲げ伸ばしを大きく伴わないため、オスグッド病の人でも比較的安全に取り組める運動のひとつです。
オスグッド病は、膝下の脛骨の一部に繰り返しの負荷がかかることで炎症が起こり、痛みや腫れを生じる成長期特有の障害です。主に太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)の強い牽引力が関係しています。カーフレイズはこの大腿四頭筋を大きく使わないため、オスグッドによる痛みが強くなければ、ふくらはぎの血流を促し、下半身の安定性を高める目的で取り入れても問題ないケースが多いです。
ただし、痛みがあるときや運動中に膝に違和感が出るようであれば、無理に続けないことが大切です。また、段差などで行う負荷の高いカーフレイズ(かかとを深く下げるタイプ)は避け、床でのシンプルな上下動から始めるとよいでしょう。
膝に負担をかけずに筋力や血流を維持したいときに、カーフレイズは有効な補助的運動となります。運動前後にはふくらはぎや太ももの軽いストレッチを取り入れると、より効果的に筋肉の緊張を和らげられます。
テーピングで固定
オスグッド病に対してテーピングを行うことは、膝下の痛みをやわらげたり、運動時の負担を軽減する目的で有効です。特にジャンプやダッシュ、階段の上り下りなどで痛みが出やすい場合、テーピングで脛骨への引っ張りを軽減することで症状を抑えることができます。
テーピングでは、大腿四頭筋の緊張をサポートしつつ、膝蓋靱帯(膝のお皿の下)へのストレスを減らすような巻き方がよく使われます。膝のお皿のすぐ下、痛みが出やすい部分に圧をかけるようにテープを巻くことで、膝下の突出部分への負担を抑えることができます。専用のパッド付きサポーターを使う方法も同様の効果があります。
ただし、テーピングはあくまで「補助的な対処法」であり、根本的な治療にはなりません。痛みが強い時期は、運動量を減らしたり、アイシングやストレッチで炎症をおさえるケアが必要です。無理に動き続けると症状が悪化し、治癒が長引くこともあります。
学校や部活でどうしても動かざるを得ないときや、日常動作での痛みを軽減したい場合には、テーピングやサポーターでの固定は有効です。ただし、長時間の使用は血流を妨げることもあるため、必要な場面だけにとどめ、使用後は肌や筋肉の状態をしっかり確認するようにしましょう。
インソールの使用
オスグッド病の対策として、インソール(靴の中敷き)を使用することには一定の効果が期待できます。特に、足裏のバランスや着地時の衝撃を調整することで、膝下への負担を軽減できる場合があります。
オスグッド病は、主に太ももの前側にある大腿四頭筋が膝下の骨(脛骨粗面)を強く引っ張ることで炎症を起こす疾患です。ジャンプや走行動作など、繰り返し膝に衝撃が加わることで悪化しやすいため、足元からその衝撃を和らげることは重要です。インソールには、足のアーチを適切に支えたり、重心の偏りを改善したりする機能があります。これにより、膝の曲げ伸ばしの軌道が安定し、脛骨への負担が軽くなる可能性があります。
特に扁平足や回内足(かかとが内側に倒れる癖)がある場合、歩行や運動のたびに膝へのストレスが増しやすいため、アーチサポート付きのインソールが効果的です。また、クッション性の高いタイプを選べば、着地時の衝撃を和らげる役割も期待できます。
ただし、インソールの効果には個人差があり、市販のものが合わない場合もあります。できれば整形外科やスポーツ専門の医療機関で足の状態を確認してもらい、自分に合ったインソールを選ぶと安心です。
インソールはテーピングやサポーターと同様、補助的なサポート手段です。痛みが強いときはまず安静にし、アイシングやストレッチなどの基本的なケアと併用して使うことが大切です。
オスグッド病の治療に必要な期間

オスグッド病の治療に必要な期間は、症状の程度や日常の運動量によって異なりますが、一般的には数週間から数か月かかることが多いです。比較的軽度な場合は、運動を一時的に控えて安静にし、アイシングやストレッチを行うことで二〜四週間ほどで痛みが落ち着くこともあります。ただし、部活動などで痛みを我慢して運動を続けていたり、症状が強く出ている場合には、三か月以上の治療期間が必要になることもあります。
オスグッド病は成長期に見られる症状であり、骨の成長が落ち着くと自然に治ることが多いとされています。ただし、痛みを感じながら無理に運動を続けると、症状が長引いたり悪化する可能性があります。そのため、早い段階で膝への負担を減らし、太ももの前側の筋肉をほぐすストレッチを習慣づけることが回復の近道になります。
また、アイシングで炎症を抑えたり、テーピングで膝の安定をサポートすることも効果的です。歩き方や足のアーチに問題がある場合は、インソールを使って足元のバランスを整えると膝への負担を軽減できます。症状が強いときには整形外科を受診し、運動再開のタイミングを専門家に判断してもらうことも大切です。痛みが治まったあとも、再発を防ぐために日頃のストレッチや姿勢の見直しを続けるよう心がけましょう。
オスグッド病の治し方に関する注意点
オスグッド病の治し方にはいくつかの注意点があり、適切な対応をしないと症状が長引いたり悪化する可能性があります。まず大切なのは、痛みがある間は無理に運動を続けないことです。特にジャンプやダッシュ、しゃがみ込みといった動作は膝下に強い負荷をかけるため、痛みを悪化させる原因になります。痛みがあるときは思い切って休むことが、結果的に早い回復につながります。
また、アイシングを行う際には冷やしすぎに注意し、1回につき15分から20分程度を目安にしましょう。凍傷を防ぐために、保冷材にはタオルを巻いて使用することが大切です。ストレッチやマッサージを行う際にも、痛みが強い部位を無理に押したり、急に強く伸ばしたりすることは避ける必要があります。ストレッチは痛気持ちいい程度にとどめ、呼吸を止めずにゆっくり行うようにしましょう。
テーピングやサポーターは膝への負担を一時的に軽減する手段ですが、これらを使って痛みを我慢しながら運動を続けるのは避けるべきです。あくまで補助的な手段として、日常動作のサポートや通学時の不快感を軽減する目的で活用するのが望ましいです。
さらに、オスグッド病は骨の成長が続いている時期に起こるため、成長が落ち着くまで完全に再発を防ぐのは難しい面もあります。そのため、症状が治まってもすぐに激しい運動に戻るのではなく、段階的に運動量を増やすことが重要です。違和感が出たらすぐにペースを落とし、再び安静にする判断が必要になります。
最後に、痛みが長く続く場合や、膝の形に明らかな異常が見られる場合は、自己判断での対応をやめて整形外科を受診することが必要です。適切な診断と指導を受けることで、安心して症状の改善に取り組むことができます。
オスグッド病の治し方についてよくある質問
 最後にオスグッド病の治し方についてよくある質問に回答します。
最後にオスグッド病の治し方についてよくある質問に回答します。
オスグッド病の再発に関することや後遺症に関する内容をまとめているため、不安や疑問を取り除くためにも、最後まで読んでみてください。
オスグッド病は治療をしなくても大丈夫?
オスグッド病は、必ず治療してください。成長痛と混同されやすく放置しても問題ないとする医師もいますが、オスグッド病は治療しなければ痛みが続きます。
放置すると手術しなければならなくなるほか、大人になっても後遺症が残り、スポーツするたびに膝が痛むようになるため、必ず治療するようにしましょう。
整形外科以外でも診察できる?
オスグッド病は、成長期の子どもに多い病気であることから小児科でも診察は可能です。
しかし、診断や治療は整形外科に任せている病院が多くあるため、診てもらったあとに整形外科を紹介されることになります。
オスグッド病であるか定かではない段階では、小児科で診察を受けてみても問題ありませんが、膝周りの痛みの多くは整形外科の方が専門的に診察できるため、なるべく整形外科にいきましょう。

運動をしない方がよい?
オスグッド病の最善の治し方は、安静に過ごすことのため、できる限り運動は控えてください。
しかし、オスグッド病患者の多くが部活やスポーツに熱中する年齢であることから、完全に運動を断つことは難しいかつ、子どもにとって精神的に辛い経験として残ります。
そのため、医師の診断を第一に考え、セルフケアやストレッチを入念におこなったうえで、過度にならない範囲で参加させましょう。
成長期は筋肉や骨を著しく成長させる大切な時期でもあるため、様子を見守ってあげることが大切です。
大人になって再発する?
オスグッド病は、大人になってから再発する可能性があります。
しかし、正しい治し方で治さなかった場合に起こり得るため、自身の判断ではなく、必ず医師に相談したうえで、治療に専念してください。
大人になってからオスグッド病になることは非常に少ないため、あくまで成長期による脛骨粗面が剥がれやすいことや、筋肉の硬化が原因とされています。
正しい治し方で完治させることが重要なため、今後のことを考慮する場合はスポーツを断念せざるを得ない状況にもなりかねません。
苦渋の選択ですが、子どもの将来を見据えた判断が大切です。
オスグット病の治療にはシン・整形外科がおすすめ

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- 安心の保証制度あり
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科のオスグット病の治療は、以下の理由からおすすめです。
・専門知識と経験豊富な医師陣
・最新の医療技術
・安心の手術
・パーソナライズされたケア
専門知識と経験豊富な医師陣
シン整形外科は専門知識を持つ医師がいるため、患者の症状や状態について本質的な診断や治療プランを提供しています。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ
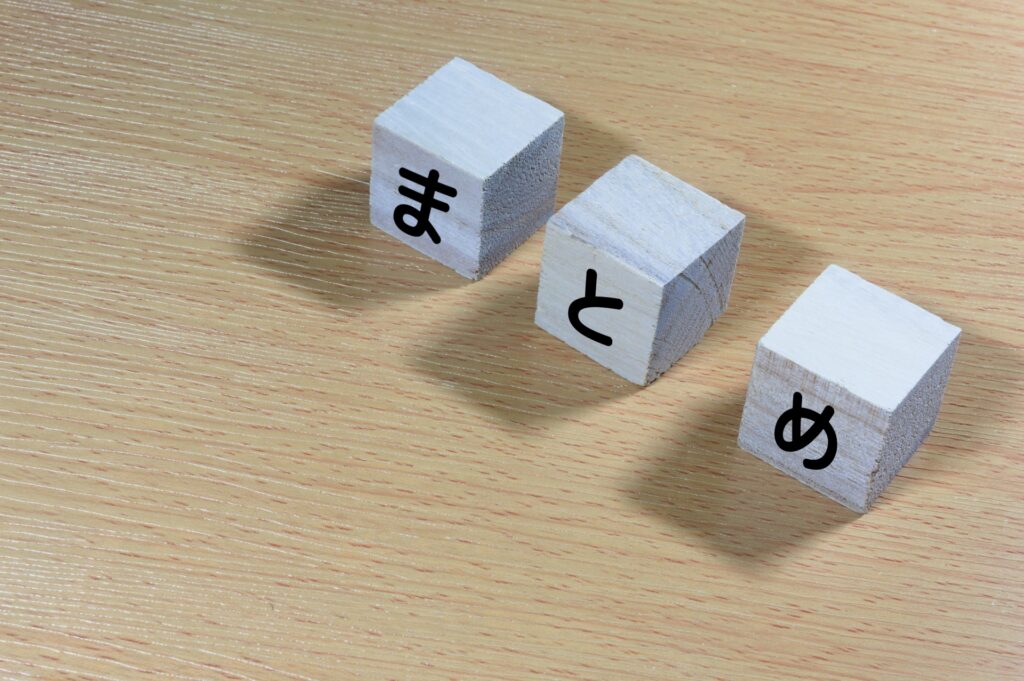
今回は、成長期のスポーツ障害として代表的なオスグッド病の原因から治し方、予防策などについて解説しました。
オスグッド病は、重症かつ症状に改善が見られない場合、手術を受ける必要があるほどの病気です。
成長痛と混同され、これまで重要視されていませんでしたが、子どもの将来を左右する病気にもなりかねないため、必ず医師に相談してください。
正しい治し方やストレッチをはじめとしたセルフケアで、オスグッド病をできる限り早く治し、万全の状態でスポーツに臨めるように、周りの大人がしっかりと支えてあげましょう。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。