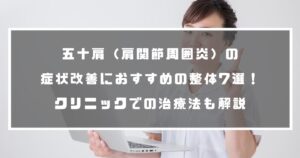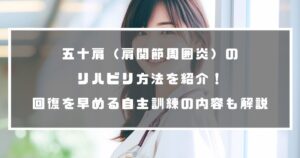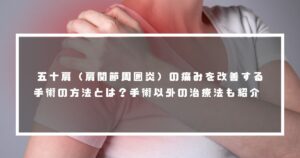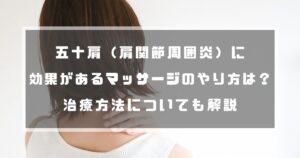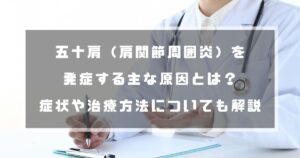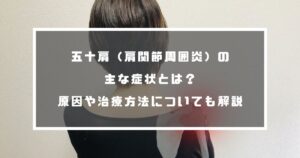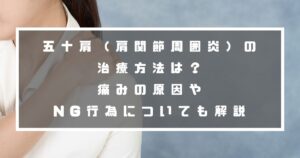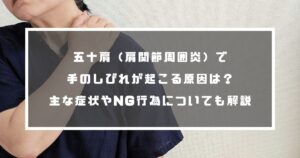腱板損傷のリハビリは痛みの軽減や可動域の回復、筋力の向上を目的におこないます。リハビリ方法は損傷の程度や個人の状態に応じて異なりますが、一般的に2つの治療パターンがあります。
一つ目は保存療法として投薬と一緒にリハビリをおこない症状を緩和する方法、二つ目は手術後に肩の機能の回復を目的におこなう方法です。
本記事では、腱板損傷のリハビリ方法を2つの治療パターンに分けて詳しく解説します。腱板損傷のリハビリテーションは、専門的な指導と継続的な取り組みが大切です。医師やリハビリスタッフの指示を守り、早期回復のためにも毎日続けましょう。
腱板損傷の原因や症状

腱板損傷とは、肩のインナーマッスルである腱板筋群が損傷する症状です。手を上げたり、横になったりすると痛みを感じることから、放置すると日常生活に影響を与える可能性があります。
また、一度損傷すると自然治癒する可能性は低いため、痛みがひどくなるようなら適切な治療が必要です。ここでは、腱板損傷になる原因や症状の特徴をまとめました。腱板損傷の疑いがある方は、ぜひチェックしてみてください。
腱板断裂の原因
腱板断裂の原因は大きく分けて、加齢や慢性的な負荷によるものと、外傷によるものの2つがあります。加齢とともに腱の血流が低下し、柔軟性や強度が失われることで、日常的な動作でも断裂が起こりやすくなります。さらに、野球や水泳などのスポーツ、重労働などで肩を長期間酷使すると、腱に小さな損傷が蓄積し、やがて断裂に至ることがあります。一方、転倒や肩を強く打つなどの外傷により、突然腱板が断裂することもあります。特に肩の脱臼を伴う場合には、腱板も一緒に損傷することが少なくありません。加えて、喫煙、糖尿病、家族歴なども腱板断裂のリスクを高める要因とされています。
腱板損傷の症状
腱板損傷の症状は、損傷の程度や範囲によってさまざまですが、代表的なものとしては肩の痛み、可動域の制限、筋力低下、そして引っかかり感や異音などが挙げられます。肩の痛みは、特に腕を上げたり後ろに回したりするときに強くなり、夜間に痛みが増して眠れないこともあります。また、腕が思うように動かせなくなり、上げにくい・後ろに回しにくいといった動作制限が生じることもあります。筋力の低下もみられ、特に腕を持ち上げる動作が難しくなる場合があり、重度の損傷では自力で腕を持ち上げられなくなることもあります。さらに、肩を動かした際にゴリゴリ・コリッといった音や引っかかるような感触があることも特徴です。これらの症状は日常生活に支障をきたすことが多く、早期の診断と適切な治療が重要です。
完全断裂と部分断裂の違い
腱板の完全断裂は、腱が完全に切れて骨から剥がれている状態で、肩の痛みや筋力低下が強く、自力で腕を上げられないこともあります。放置すると筋肉が萎縮するため、手術が必要になることが多いです。一方、部分断裂は腱の一部が損傷している状態で、痛みはあるものの動かすことが可能で、リハビリや薬による保存療法で改善する場合が多いです。ただし、放置すると完全断裂に進行するリスクもあります。
腱板損傷と似ている病気
腱板損傷と似た症状を示す病気には、肩関節周囲炎(五十肩)、肩関節インピンジメント症候群、肩の脱臼後遺症、関節リウマチや変形性肩関節症などがあります。これらは肩の痛みや動かしにくさが共通しており、正確な診断には専門医の診察や画像検査が必要です。
腱板断裂
腱板断裂とは、肩の腱板(肩甲骨と上腕骨をつなぐ4つの筋腱の集合体)が部分的または完全に切れてしまう状態を指します。主に加齢や肩の使いすぎによる変性、あるいは転倒や外傷が原因で起こります。症状は肩の痛みや動かしにくさ、筋力低下があり、特に腕を上げる動作で痛みが強くなることが多いです。診断は問診や身体検査、MRIや超音波検査で行い、治療は保存療法(安静、リハビリ、薬物療法)から手術まで、断裂の程度や症状に応じて選ばれます。
五十肩
五十肩は、主に40〜60代に多く見られる肩の痛みと運動制限を特徴とする疾患です。肩の関節や周囲の組織に炎症や癒着が起こり、肩がこわばって動かしにくくなります。原因ははっきりしないことが多いですが、加齢や肩の使いすぎ、運動不足などが関係すると考えられています。症状は肩の強い痛みと共に、腕が上がらない、後ろに回せないといった可動域制限が現れます。治療は痛みの緩和を目的に薬物療法や理学療法が中心で、自然に改善することも多いですが、重症の場合は注射や手術が検討されることもあります。
腱板損傷の治療方法

腱板損傷の治療法には、大きく分けて保存療法と手術療法、再生医療の3つがあります。基本的に腱板損傷は、一度症状が出ると自然治癒しないため、痛みがつらい場合は早めに治療しましょう。
ここでは、腱板損傷の治療法をまとめました。腱板損傷の治療を検討中の方は、ぜひチェックしてみてください。
保存療法
腱板損傷の保存療法は、手術をせずに痛みや炎症を抑え、肩の機能を回復させる方法です。具体的には、肩を安静に保ち、NSAIDsなどの薬で痛みを和らげます。理学療法で筋力強化や可動域の改善を図り、必要に応じてステロイド注射で炎症を抑えることもあります。ただし、症状が改善しない場合は手術が検討されます。
手術療法
腱板損傷の手術療法は、保存療法で効果がない場合や完全断裂に対して行われます。主な方法は、断裂した腱を骨に縫い付ける「腱板縫合術」で、関節鏡を用いた低侵襲手術が一般的です。損傷が大きい場合は他の腱や人工素材を使った再建術や、重度の機能障害がある高齢者には人工肩関節置換術が行われることもあります。術後はリハビリが重要で、回復には数か月を要します。
再生医療
腱板損傷に対する再生医療は、損傷した腱の修復や再生を促す新しい治療法で、主にPRP療法や幹細胞治療が用いられます。PRP療法は血小板由来の成長因子で組織の回復を促し、幹細胞治療は損傷部に再生能力のある細胞を用いて腱の修復を助けます。また、バイオマテリアルを併用した治療も研究されています。現在は一部で自由診療として行われており、手術を避けたい人や軽度の損傷に対して有望な選択肢とされています。
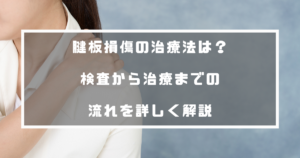
腱板損傷で手術をしない方のリハビリ方法

腱板損傷の手術をしない場合は、投薬とリハビリで症状の緩和をおこないます。
ここでは、腱板損傷の手術をしない場合のリハビリ方法をまとめました。メスを使わず、自身で症状の改善を図りたい方は、ぜひチェックしてみてください。
手術をしない方のリハビリ期間は3~4か月
通常3〜4か月かけて段階的に進めます。リハビリの目的は、痛みの軽減、肩関節の可動域の回復、肩の安定性の向上、そして日常生活やスポーツへの復帰です。
まず第1期(1〜3週)は急性期で、安静を保ち、アイシングや振り子運動など軽い運動を通じて炎症を抑えます。痛みの出ない範囲で肩を動かし、姿勢にも注意を払います。
第2期(2〜6週)は可動域改善期で、タオルや棒を使ったストレッチや壁を使った肩挙上運動などを行い、固まりかけた関節の動きを取り戻します。痛みのない範囲で行うことが重要です。
第3期(6〜12週)は筋力回復期で、セラバンドを使った内旋・外旋運動によって腱板を構成する筋肉を強化し、同時に肩甲骨を安定させる周囲筋のトレーニングも取り入れます。
第4期(3〜4か月)は機能回復・予防期で、洗濯物干しや棚の物を取るといった日常動作や、軽いスポーツ動作の再習得を進めます。リハビリ終了後も再発予防のため、肩周囲のトレーニングを継続することが勧められます。
リハビリは必ず無理をせず、痛みが出る場合は中止し、必要に応じて医師や理学療法士に相談することが大切です。経過が思わしくない場合は、再評価も検討されます。
筋力トレーニング
筋力トレーニングが肩の安定性を高め、再発を防ぐために重要な役割を果たします。リハビリ中期から後期(おおよそ6週目以降)にかけて、適切な筋力トレーニングを段階的に取り入れることが勧められます。
まず、ローテーターカフ(腱板)を構成する筋肉の強化が重要です。具体的には、チューブ(セラバンド)を使った肩の外旋運動と内旋運動があります。外旋運動では棘下筋や小円筋、内旋運動では肩甲下筋が主に鍛えられます。いずれも肘を90度に曲げ、体側に固定してチューブを引っ張る動作を10〜15回、2〜3セット行うのが一般的です。
次に、肩甲骨周囲の筋肉を強化することも欠かせません。肩甲骨の内転運動では、僧帽筋や菱形筋を意識して、両肩をゆっくりと後ろに引き、肩甲骨を寄せるようにします。また、うつ伏せの状態で腕を「Y」や「T」の形に持ち上げる「プローンY/T運動」も効果的で、軽いダンベルを使って肩甲骨を安定させる力を高めます。
さらに、腕全体の連動性と肩の安定性を高めるために、体幹トレーニングも取り入れます。たとえば、プランクの姿勢で反対側の肩を交互にタッチする「プランク+肩タップ」や、壁に向かって行う「壁プッシュアップ」などが挙げられます。これらの運動は肩への負担を軽減しつつ、三角筋や前鋸筋も同時に鍛えることができます。
トレーニングを行う際は、痛みの出ない範囲で、正しいフォームを意識しながら週に2〜3回を目安に継続することが大切です。また、不安がある場合は理学療法士の指導のもとで行うとより安全です。筋力トレーニングは無理なく継続することで、肩の機能回復と再発防止につながります。
甲骨や関節を動かす
肩関節だけでなく肩甲骨の動きを改善することが非常に重要です。肩のスムーズな動きには肩甲骨の安定性と可動性が欠かせないため、これらを意識した運動がリハビリの中心となります。
まず、肩甲骨の動きを良くするために、肩甲骨を上下・内外に動かす運動や、肩甲骨を寄せる内転運動、四つ這い姿勢で肩甲骨を前後に動かす「スキャプラ・プッシュアップ」などを行います。
次に、肩関節の可動域を広げるために、振り子運動や壁歩き運動、タオルや棒を使った補助的なストレッチを取り入れます。これにより、関節を無理なく安全に動かすことができます。
また、姿勢の改善や肩甲骨と上腕の連動を意識した動作訓練も有効です。胸を開くストレッチや、日常動作の中で肩甲骨が正しく動いているかを確認しながら繰り返し練習することで、再発予防にもつながります。
これらの運動は痛みの出ない範囲で毎日少しずつ継続することが大切で、無理をせず違和感がある場合は専門家に相談するようにしましょう。
正しい姿勢の確保
正しい姿勢の確保が回復と再発予防の重要な要素となります。姿勢が崩れると肩関節や肩甲骨の動きが悪くなり、腱板に負担がかかって痛みや可動域の制限を引き起こすことがあります。
正しい姿勢とは、耳・肩・骨盤が一直線に並び、胸を開いて顎を軽く引いた状態です。この姿勢を意識することで、肩の筋肉や関節の動きがスムーズになり、リハビリ効果が高まります。
姿勢を整えるための基本的なエクササイズには、壁に背をつけて立つ「姿勢チェック」や、肩甲骨を寄せる運動、顎を引いて首を伸ばす「チンイン運動」などがあります。これらを毎日継続して行うことで、猫背や巻き肩などの悪姿勢を改善し、肩への負担を軽減できます。
また、日常生活でも正しい姿勢を意識することが大切です。デスクワーク中の姿勢やスマホの使い方、立ち姿勢などにも注意し、肩が前に出ないようにすることで、リハビリの効果が持続します。
姿勢の改善はすぐに結果が出るものではありませんが、継続することで肩の機能回復に大きく貢献します。
腱板損傷で手術をする方のリハビリ方法

腱板損傷の手術には、太ももの人工素材を腱板の代わりに移植する方法や、特殊な人工関節を挿入する方法などがあります。体に負担はかかるものの、腱板損傷の症状を緩和するのではなく、根本的に解決したい方には有効な方法です。
ただし、術後のリハビリを継続しておこなう必要があります。ここでは、腱板損傷で手術をしたあとのリハビリ方法をまとめました。
手術後のリハビリ期間は約3か月
腱板損傷で手術を受けた場合、リハビリ期間は約3か月かけて段階的に進められます。リハビリの目的は、肩の可動域と筋力を安全に回復させ、日常生活に復帰することです。
術後〜4週目までは、肩を三角巾などで固定し、理学療法士による他動運動で関節の動きを維持します。肩以外の部位は積極的に動かし、痛みや腫れの管理も行います。
5〜8週目からは自分の力で肩を動かす自動運動が始まり、壁歩きや振り子運動などで徐々に可動域を広げていきます。肩甲骨の動きや姿勢にも注意を向けます。
9〜12週目には筋力トレーニングを開始し、腱板や肩周囲の筋肉を強化して肩の安定性を高めます。チューブやダンベルを使った外旋・内旋運動、姿勢保持運動などが中心となります。
このように、手術後のリハビリは段階的に進めることで、肩の機能回復と再発予防を図ります。
術後は装具で固定
腱板損傷の手術後は、修復した腱板を守るために約3〜4週間、装具で肩を固定します。主にアブダクションスリング(外転位保持装具)が使われ、肩に負担がかからない姿勢を保ちます。
この期間中は、肩を動かさず安静を保ちつつ、肘・手首・指の運動を行い、血流や関節の柔軟性を維持します。必要に応じて理学療法士による他動運動も行われます。無理に肩を動かすと再損傷のリスクがあるため、装具の着用や運動は医師や専門家の指示に従うことが重要です。
徐々に自身の力で動かす
板損傷の手術後、約4〜6週が経過すると、固定を外し、徐々に自分の力で肩を動かす「自動運動」を開始します。これは肩の可動域と機能を回復させるための重要なステップです。
リハビリでは、壁歩き運動や振り子運動、棒を使った補助的な動きなどを取り入れ、肩関節と肩甲骨のスムーズな動きを促します。痛みが出ない範囲で行うことが原則で、無理をすると再損傷のリスクがあるため、段階的に進める必要があります。
この時期の訓練は、日常生活への復帰や筋力トレーニングへの移行を円滑にするための基礎となります。
腱板のトレーニング
腱板損傷の手術後リハビリでは、術後約8〜12週から腱板の筋力トレーニングを開始します。主に、肘を固定して行う外旋・内旋運動や肩甲骨を安定させる運動、軽い負荷の抵抗運動をゆっくり痛みなく行うことが大切です。これにより肩関節の安定性が高まり、痛みの軽減や再損傷予防、日常生活の改善につながります。負荷は徐々に上げ、痛みが出たら無理せず専門家に相談しましょう。
肩甲骨のトレーニング
腱板損傷の手術後リハビリでは、術後約6〜8週から肩甲骨のトレーニングを始めます。肩甲骨を中央に寄せる運動や上下に動かす運動、四つん這いでの肩甲骨の動きなどをゆっくり痛みなく行い、肩関節の安定性と可動域を高めます。これにより腱板への負担が減り、肩の動きがスムーズになります。動作は反動を使わず、無理のない範囲で行うことが大切です。
肩の可動域練習
腱板損傷の手術後、約4〜6週目から医師の指示で肩の可動域練習を始めます。主な運動は、腕を力を抜いて揺らす振り子運動、壁に指をつけてゆっくり手を上げる壁歩き運動、健側の腕で棒を使い患側の腕を補助する棒体操です。これらは肩への負担が少なく、痛みのない範囲でゆっくり行うことが重要です。
可動域練習は肩関節の硬さを防ぎ、柔軟性を保つことで、日常生活の動作改善や早期の社会復帰につながります。痛みや違和感が強い場合は無理せず専門家に相談しながら進めましょう。
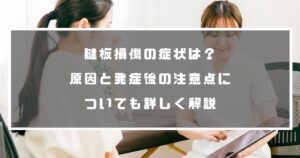
腱板損傷の禁止動作

腱板損傷と診断された場合は、基本的に肩回りや腕に負担をかけないことが大切です。肩や腕に負担をかけすぎると、腱板損傷が悪化して痛みが強くなります。
そのため、ここでは腱板損傷の禁止動作をまとめました。禁止動作をチェックし、日常生活でも注意しながら過ごしましょう。
重い物を持ち上げる
腱板損傷では、重い物を持ち上げる動作は腱に強い負担がかかるため禁止されています。無理に持ち上げると損傷の悪化や再断裂のリスクが高まり、回復を妨げる原因になります。特に腕を上げた状態での動作や急な力の使用は避け、日常生活では荷物を軽くし、肩に負担をかけない工夫が必要です。リハビリ中は医師や理学療法士の指示に従い、筋力の回復に応じて徐々に負荷を調整します。
首の後ろで腕を動かす
首の後ろで腕を動かす動作(結髪動作)は禁止されています。肩を大きく外旋・挙上するため、腱板に強い負担がかかり、炎症や再損傷の原因になります。髪を結ぶ、背中の上部を洗う、首の後ろに手を当てるなどの動作は避け、肩の可動域が十分に回復するまでは無理をしないことが大切です。必要に応じて、日常動作の工夫や方法の変更も行いましょう。
腕に負荷がかかる運動
腕に強い負荷がかかる運動は避ける必要があります。たとえば、重いダンベルやバーベルを使ったトレーニング、腕立て伏せ、懸垂、テニスや野球などの肩を大きく使うスポーツは、腱板に強いストレスを与え、損傷の悪化や再断裂の原因になります。特にリハビリ初期には、痛みが出ない範囲で軽い負荷から始め、運動は必ず医師や理学療法士の指導のもとで進めることが重要です。
腱板損傷のリハビリについてよくある質問

腱板損傷の本格的な治療を検討中ならば、リハビリの期間や入院日数などが気になる方もいるでしょう。
ここでは腱板損傷のリハビリについてよくある質問をまとめました。治療法で迷っている方や、仕事への影響が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
腱板損傷はリハビリで治る?
腱板損傷は、損傷の程度によってリハビリで改善が期待できる場合と手術が必要な場合があります。部分断裂や軽度の損傷では、痛みの軽減・可動域改善・筋力強化などのリハビリによって症状が改善することがあります。一方、完全断裂や重度の損傷ではリハビリだけでは改善が難しく、手術が必要になることもあります。適切な治療法は医師の診断に基づいて判断されます。
腱板損傷のリハビリはいつから実施する?
腱板損傷のリハビリは、手術の有無によって開始時期が異なります。手術をしない場合は、痛みや炎症が落ち着いてきたら数日~1週間ほどでリハビリを開始し、可動域訓練や軽い筋力トレーニングを行います。手術をした場合は、まず指や肘の運動から始め、肩は装具で固定し、4~6週目から肩の他動運動、6~8週目以降に自分で動かす訓練を始めます。リハビリの進行は医師や理学療法士の指示に従い、無理なく行うことが大切です
腱板損傷のリハビリのための入院期間は?
腱板損傷のリハビリ入院は、2~4週間程度の期間が目安です。手術のみであれば、日帰りが可能なクリニックもあります。
手術をした場合は、退院後に週2~3回程度の頻度でリハビリに通うことになるでしょう。
肩の治療ならシン・整形外科

- 再生医療で痛みを根本解決
- 手術不要・日帰り治療OK!
- パーソナライズされた治療ケア
| 施術費用 | ■初診 3,300円 ■MRI検査 8,000円〜12,000円 ■注入治療 198,000円〜1,078,000円※1 ■リハビリ 29,800円〜49,800円 |
| 診療時間 | ■受付 9時〜18時 ■MRI診断予約 24時間受付 |
| 支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー バーコード決済 |
| アクセス | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-15 銀座清月堂ビル5F |
シン整形外科の腱板損傷の治療は、以下の理由からおすすめです。
- 専門的な肩の治療
- 最新の医療技術
- 個別の治療プラン
- 安心の手術
- パーソナライズされたケア
専門的な肩の治療
シン整形外科は肩の痛みや問題に特化した専門的な治療を提供しています。経験豊富な専門医が、患者様の症状を正確に評価し、最適な治療法を選択します。肩に関する専門知識を持つ医師陣が、あなたの健康と快適な生活のために全力を尽くします。
最新の医療技術
シン整形外科は常に最新の医療技術を導入し、最良の治療を提供しています。物理療法、関節内注射、手術など、幅広い治療オプションを取り入れることで、患者様の症状に合わせた効果的なアプローチを実現します。
個別の治療プラン
患者様一人ひとりの状態やニーズに合わせて、カスタマイズされた治療プランを提供します。一般的な治療だけでなく、患者様のライフスタイルや目標に合わせて、最適なアドバイスや指導を行います。
安心の手術
必要な場合、シン整形外科では最新の外科手術技術を駆使して、最小限の侵襲で手術を行います。安全性と効果を重視し、患者様の健康と安心を第一に考えた手術を提供します。
パーソナライズされたケア
シン整形外科は、患者様の信頼と満足を最優先に考えています。親切で丁寧なスタッフが、あなたの質問や不安に対応し、治療プロセスをサポートします。あなたの声に耳を傾け、共に健康な未来を築いていきます。
まとめ
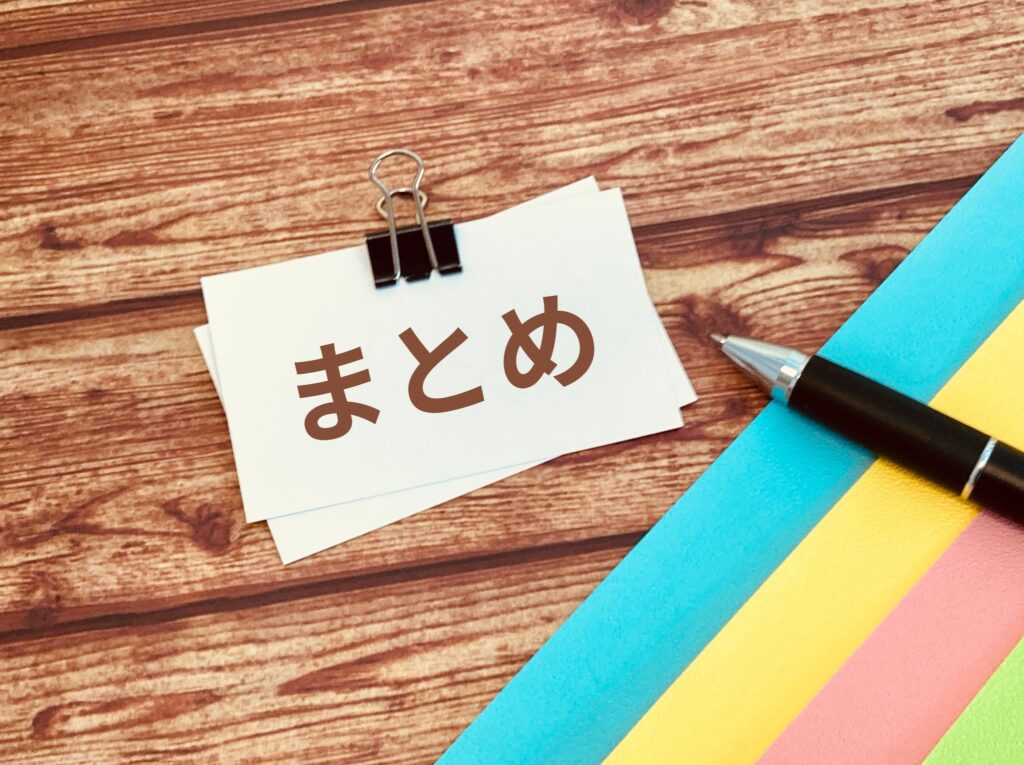
腱板損傷の治療法には、保存療法と手術療法、再生医療の3つあります。なかでも保存療法の投薬とリハビリは、手術せずに症状を緩和できる方法です。
ただし、腱板損傷は悪化する可能性もあることから、リハビリをする際は肩や腕に強い負荷をかけないように注意しましょう。本記事でも簡単にできるリハビリ方法を紹介しているため、肩の様子を見ながら毎日少しずつ実践してみてください。
腱板損傷が悪化すると、手術療法もしくは再生医療が必要になります。なるべく費用や治療期間をカットしたい方は、リハビリで症状の緩和を図りましょう。